創業200年超の製薬メーカー「天藤製薬」がECサイトを立ち上げた理由
ーまず御社の事業について教えてください。
濱井 菜月氏(以下、敬称略):天藤製薬は痔疾用薬「ボラギノール®」を展開している創業200年を超える製薬会社です。どうしても世間ではボラギノールの会社といったイメージが強いかと思いますが、最近では痔の発症要因でもある生活習慣の乱れに伴う悩みにアプローチする「BORRA®」、女性ホルモンの乱れに伴う悩みを改善する「FEMBORRA®」といったブランドを展開する等、新しいことに精力的に取り組んでおります。本日は、そうした新しい取り組みの中で、2022年より開始したEC事業に関してお話しできればと思います。

米 楽氏(以下、敬称略):EC事業を運営していく上で、これまで以上にレスポンス型広告は活用しており、そうした中でデジタル広告での獲得実績が最も高いです。その他にも、お電話やハガキ、FAXでのご注文も承っています。特にご高齢のお客様ですと、今もFAXで注文される方も少なくありません。自社EC以外にも楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazonなどモールでも販売しています。
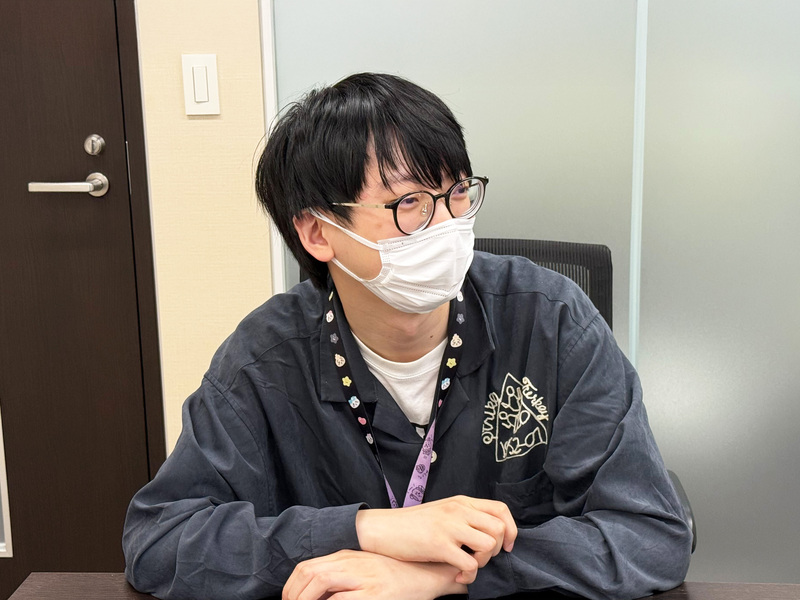
濱井:お客様の層に関していいますと、男女で大きな偏りはなく、年齢に関しても「ボラギノール®」のお客様の層と「BORRA®」のお客様の層は近く、60代から70代あたりがメインとなります。特にご高齢の方は、ボラギノールに対する信頼感が購入の後押しになっていることを強く感じます。
淺井 早希氏(以下、敬称略):若いお客様からも、「ECサイトで購入できてとても助かった」というメールを何度かいただいたことがあります。お客様からの声を受けて、幅広い世代の方にご利用いただけていることを実感しています。
ーECサイト立ち上げ時の背景を教えてください。
濱井:BORRAオンラインショップ立ち上げ時の背景としましては、まず生活者の健康意識の高まりがあります。予防や未病対策の重要性が注目され、そこに各社具体的なサービスが次々に展開される中、弊社もそこに重点を置いた製品展開を進める必要性を強く感じました。これまで弊社は、痔の症状が現れてから対処する製品を展開してきましたが、昨今の生活者の意識の変化に合わせて、予防や発生原因にアプローチする製品を展開していくべきだという考えが、社内で徐々に拡がっていきました。また、2021年にロート製薬グループに参画することになったことで組織体制が変化し、新たなチャレンジをしていこうという気運も高まっていました。
このような流れの中で、痔の予防を意識した便通改善サプリメントとして、約30年ぶりに満を持して「ボラケア®バランスwith乳酸菌」が新しく誕生しました。ただ、販売当初の同製品に対するお客様の反応は薄かったですね。痔と便秘は密接に関係しているという学術的な考えから、便通改善のカテゴリーにおいてもボラギノールのブランド力を押し出していけば一定数は売れると考えていましたが、その期待は裏切られ、実際に販売を開始してみると全く反応がなく、ボラギノールはあくまで痔の薬のカテゴリーのブランドであって、便通改善のカテゴリーではそれだけで手に取っていただけるほど強いブランドではないことに気づかされました。そこで、ターゲットである便通に悩む人についてあらためて考え抜いた結果、商品選定時に重視することは「知っているブランドである」こと以上に「品質への信頼」と「効き目の根拠」にあるのではないかという考えに至りました。それをふまえた訴求内容として、『100年以上続く実績による信頼感』と『エビデンスに基づいた商品設計と情報提供』の2点をしっかり打ち出すようにしたところ、徐々にお客様に選ばれる商品になっていきました。

機能拡充への期待とサポート体制の安心感を決め手にecforceへ移行
ー以前のカートシステムではどのような課題があったのでしょうか。
淺井:課題は二つありました。一つ目は、システム間の連携がうまく取れていなかったことです。カートシステムとLP管理、販売データの分析システムがそれぞれ別で存在しており、各データ間の整合性を保つのが難しい状況でした。たとえば、受注データにキャンセル分が含まれているかどうかという点において差違が生じてしまうことで、定期契約の残存率がバラバラになってしまうというようなことが起きていました。この問題を解消するために、カートだけではなくLPや販売分析も一元で管理できるシステムを探していました。
二つ目は、商品コードの管理が複雑化していたことです。事業の立ち上げ当初は特に問題はなかったのですが、商品数が増えるにつれてまとめ買いオファーも増え、それに応じて商品コードもどんどん増えていきました。一つの商品を登録する場合、30日・60日・90日といったように定期コースの配送間隔ごとに商品コードを個別で登録する必要があり、管理が煩雑になってしまったのです。今後も商品数が増えていくことを考えると、より管理しやすいシステムに移行する必要があると感じていました。

ーecforceへ移行を決めた理由を教えてください。
淺井:まず、カートシステムを選ぶ条件を四つ決めていました。一つ目は、クロスモール(複数ネットショップ一元管理クラウド)とデータの連携がスムーズにできること。二つ目は、カートとLP、それから販売分析を一元管理できること。三つ目は、システム移行時のサポートが手厚いこと。四つ目は費用面で、以前のカートシステムよりプラス10万円程度で運用できるカートシステムを探していました。
これらの条件を踏まえ、ecforceを選んだ理由は、エラー発生時の迅速な対応と手厚いサポート体制、自社開発による今後の機能拡充への期待、そして業界内での高い知名度と信頼感が挙げられます。今後、弊社でも会計システムなどの機能を追加導入する可能性もあったので、ecforceなら連携しやすいだろうと考えました。
ー今回システム移行にあたってecforce data transfer*を活用されましたが、システム移行の具体的なプロセスやスケジュール、体制を教えてください。
安田 奈月氏(以下、敬称略):2024年3月頃からecforceの導入の話を進めて6月に契約、同年11月にECサイトをリニューアルしたので、5カ月ほどでシステム移行が完了しました。弊社としては2回目のシステム移行でしたが、私たちのチームにとっては初めての経験でした。そのため、どれだけ時間がかかるのかが見越せていなかったのですが、ecforceの担当者から具体的なロードマップを細かく提示いただき、それによって自分たちが次に何をすべきなのかが明確でした。一部、情報システム部の力を借りた部分もありますが、移行はとてもスムーズに進んだと思います。
*ecforce data transfer:メーカーがECシステムの切り替えを行う際のデータ移行を自動化するツール。

ーecforceへの移行にあたって苦労したことはありましたか?
安田:大変だったことは二つあります。一つ目はクレジットカード情報の移行です。旧カートシステムとecforceでは決済処理に必要なIDの管理方法が違ったので、旧カートシステムの方と何度かやり取りをする必要がありました。ただ、ecforceの担当者が連携して対応してくださったので、問題なく進めることができました。
もう一つは、新旧システムの商品設定における構造の違いです。旧カートシステムでは配送サイクルが最上位概念でしたが、ecforceでは商品が最上位概念にあるといったように、そもそも商品コードの体系が異なっていたので、そこでつまずきがありました。商品コードの修正が必要だったのですが、そちらに関してもecforceの担当者が何度も修正しながら丁寧に対応してくださったので、現在は問題なく運営できています。
ーecforceの機能の中で特に使い勝手のよいものはありますか?
安田:定期販売機能とLP管理機能です。定期販売については、サプリメントなどは同じ商品でも30日分、60日分など配送サイクルが異なったり、初回と二回目で商品を入れ替えたりなど、複雑な設定となることもあります。ecforceはそのような複雑な変更においても柔軟に対応できるため、希望の内容を設定することができています。

米:もう一つのLP管理機能については、旧カートシステムではLP管理に外部ツールを使用していたのですが、カートシステムに入ってくるデータとズレが生じるケースがありました。ecforceを導入してからは、全てecforceの管理画面から一元管理できるようになったのでデータの正確性が大幅に向上しましたし、かなり使いやすくなったと感じています。
効果検証が容易になり、高速でPDCAサイクルを回せるように
ーecforceへ移行後、なにか影響はありましたか。
濱井:いくつかありますが、まずはecforce efo*の導入で効果検証が容易になったことでしょうか。以前は別のシステムを使っていたのですが、自社管理ではなかったため、システムの担当者に問い合わせてレポートを出していただく形で対応していました。これだと時間がかかってしまうことが多く、スピーディーな改善やA/Bテストのしづらさが課題だったのですが、ecforce efoを導入したことで自分で管理画面を見て離脱ポイントやエラー箇所などの問題点を確認し、タイムリーに修正することができるようになりました。EC運営では、いかにPDCAサイクルを速く回して改善していくかということが重要なので、ecforce efoの導入は非常に大きなメリットだと思っています。また、ecforceの担当者との定例会で、他社の取り組みや最近のトレンドなども教えていただいています。社内でも、まだまだecforce efoの活用の余地があるのでは、という空気感になっており、今後も活用を進めていきたいです。
*ecforce efo:チャット型対話式EFO。ECサイト上にチャット形式の注文フォームを簡単に設置できるサービス。CVRを向上させ、広告投資のROIを最大化させる。
また、Web広告周りで新しいクリエイティブや新しい訴求内容をテストしているのですが、新規ページを作りやすかったり、スムーズにA/Bテストができたりと、ecforceの機能のおかげでスピード感のある施策の実行や改善につながっています。
安田:旧カートシステムでは、商品コードを付ける際、一つの商品につき6~7パターンのコードが必要だったのですが、現在はその作業が減ったので作業時間を大幅に短縮することができています。あくまで感覚的なものですが、運営コストは三分の一ぐらいになったと感じています。
ワンプロダクトだからこそ叶えられたデータの正確性、ecforce biもプロフェッショナルプランを導入
ーecforce biの導入による成果はありますか。
米:旧カートシステムにはデータを分析、整形、可視化できるツールがないため、カートシステムから月ごとのデータをダウンロードし、手作業で整形、外部の分析ツールにアップロードするといった作業が毎月発生していました。特定の製品に対して施策の効果を分析したり、特定期間の残存データをCRMチームに共有したりするような単発案件でも、分析したいデータをダウンロード、整形することに手間がかかっていました。ecforce bi*を導入してからは、ecforce biによって可視化されたデータをそのままCRMチームが分析、活用できる状態になっているので大幅に手間が省けています。データ処理が苦手なメンバーでも、わかりやすいUIで直感的に操作できるので助かっています。
また、カートシステムのecforceとダッシュボードツールのecforce biがワンプロダクトでシームレスに連携されているため、データの正確さが担保されています。定期残存率や離脱率などCRM関連のデータは、弊社では非常に重要視している指標ですので、データ分析の精度が格段に上がっているのは非常にポジティブです。
*ecforce bi:データ活用における可視化・分析を行うダッシュボードツール。煩雑なデータ設計や連携等が不要で、EC特有のデータの可視化・分析が容易となる。また、複数のチャネルを跨いだデータの可視化・分析も可能とする。
ープロフェッショナルプランをご契約いただいていますが、どのように活用されていますか。
濱井:経路別やURL別で流入するお客様の定期契約の残存率がどう変化するかなど、見たい指標を自由にカスタマイズして活用しています。主力製品の残存率を確認し、そのときに打っていた施策が何でどういう成果があったのか、残存率はどう変化しているか、効果検証しながら試行錯誤しているところです。今は自社ECのデータの可視化・分析が中心ですが、いずれはオフラインデータも含めた分析も考えています。
ー今後、データ活用で実現していきたいことはありますか?
米:これまでは定期契約の残存率をメインに見ていたのですが、自社ECの立ち上げから3年目になりある程度データが蓄積できているので、LTVの観点でのデータ分析も視野に入れています。手作業でのLTVの計算は非常に複雑で難しかったのですが、ecforce biには予測分析機能(β版)のタブから簡単にLTV関連の指標を確認できるようになっているので今後活用していきたいです。
ー今後の展望について教えてください。
濱井:商品を通じて接点を持ったお客様への理解を深め、健康を守る存在であり続けたいと思います。最近では顧客インタビューを積極的に実施しています。これまでもアンケートは実施していましたが、1時間ほどみっちりインタビューし、お客様の生の声を聞くと、異なる角度からの学びがあると感じています。お客様への理解を深めることで、新規獲得率や残存率の向上にもつながっていくと思うので、今後もecforceを活用しつつ、お客様への理解を高められたらと思っています。
ー最後に、ecforceの導入を検討されている方へメッセージをお願いします。
淺井:ecforceは機能面はもちろんですが、カスタマーサポートの対応が迅速で、電話やチャットで問い合わせるとすぐに回答いただけます。プロダクトだけでなくサポート体制も万全なので、とても安心できると思います。
安田:導入時のサポートはもちろんですが、導入後も非常に手厚くサポートしていただけており、安心感がまったく違うと感じています。また、カートシステムだけでなく、付随するアプリケーションも豊富で、それらのシームレスな連携も魅力の一つだと思います。これから事業を大きく成長させていきたいと考えるブランドには特におすすめしたいです。
ー本日はありがとうございました。
※掲載内容は取材当時のものです。



