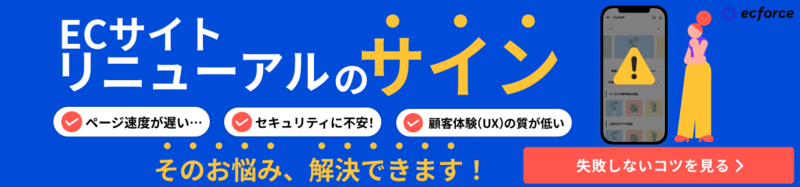この記事でわかること
※この記事は 時点の情報をもとに執筆しています。
ECサイトの売上が伸び悩んでいたり、運営効率が悪化していたりする場合、サイトリニューアルがビジネス成長のカギとなることがあります。
しかし、タイミングや理由を見誤ると、手間やコストばかりが増えてしまい、かえって逆効果になりかねません。
本記事では、ECサイトの見直しが必要なサイン、リニューアルに踏み切るべき判断基準やリニューアルの手順、注意点、成功事例について解説します。
これからの成長を支える土台をつくるためにも、今のサイトに潜む問題点を客観的に見直してみましょう。
関連するテーマについては、下記の記事もぜひチェックしてみてください。
【2025年最新版】ECサイト構築に使える補助金ガイド|3大制度と失敗しない申請のコツ
【決済で売上が変わる?】ECサイトのための決済方法・代行サービス徹底比較

ECサイトの見直し時期は?再構築すべき5つのサイン
ECサイトの運用を長く続けていると、少しずつ見えにくくなるのが「変えるべきタイミング」です。
売上が落ちてからでは遅く、サイトの問題点に早めに気づいて対処することが重要です。
この章では、ECサイトをリニューアルすべきかどうかを判断するための4つの明確なサインをご紹介します。
ビジネスの成長を妨げないためにも、今の状態をチェックする材料としてぜひ参考にしてください。
1. 古いシステムでトラブルやコストが増加
ECサイトの構築から数年が経過している場合、インフラやシステム構成が現在の技術水準に追いついていない可能性があります。
サーバーやCMSの老朽化により、頻繁なエラーやセキュリティリスク、速度低下などが起きやすくなるのです。
また、ベンダーのサポートが終了している、あるいは機能のアップデートが受けられないといった状況も、見過ごせない問題です。
保守対応のたびに外部エンジニアへの依頼が必要になったり、トラブル対応にかかる時間やコストが増加している場合、リニューアルの検討は急務と言えるでしょう。
2. 現在の機能がビジネスの成長に追いついていない
事業規模の拡大に伴い、EC運営に求められる機能も複雑化していきます。
定期購入、予約販売、販促施策の自動化、在庫連携、顧客セグメントごとの施策など、成長に合わせた対応が必要になります。
しかし、現在のシステムではそれらを実現するのが難しく、手作業で補っている状態が続いているなら、すでに運用の限界に達している可能性があります。
機能の拡張性がない、API連携が困難、管理画面が煩雑など、日々の業務に支障が出ているなら、成長を見据えたリニューアルが有効です。
3. デザインやUIが時代遅れ
ユーザーは数秒でECサイトの印象を判断します。
特にスマホユーザーが主流となった現在、モバイル対応が不十分だったり、UI設計が古く使いづらいと、すぐに離脱されてしまいます。
また、業界の競争が激しくなる中で、他社サイトと比べて洗練されていないデザインは、商品やブランドそのものの価値を下げかねません。
コンバージョン率の低下や直帰率の上昇が見られるなら、UX改善を伴うリニューアルが必要な時期です。
4. サービスや運用に不満がある
現在のECプラットフォームに対して、「管理画面が使いにくい」「サポート対応が遅い」「カスタマイズの自由度が低い」といった不満が蓄積している場合は、リニューアルの検討ポイントです。
こうした小さなストレスは、業務の非効率や人的リスク、さらには売上損失につながる可能性があります。
加えて、契約中のプランが割高で、コストパフォーマンスに見合っていない場合も、乗り換えによってコスト最適化を図る好機となります。
5.売上が停滞している
ECサイトの売上が思うように伸びない場合、サイト構造や導線、ユーザー体験に何らかの問題が潜んでいる可能性があります。
特に、集客ができているにも関わらず「購入に至らない」状態が続いている場合は、UI/UXの最適化や機能面での見直しが必要です。
たとえば、以下のような兆候は、リニューアルを検討すべきサインです。
- スマートフォンでの表示や操作性が悪く、離脱率が高い
- 商品ページからカートへの導線がわかりづらく、かご落ちが多発している
- レコメンド機能やレビュー表示など、購買を後押しする仕組みが不十分
- SEOや広告での集客数に対して、CVR(コンバージョン率)が低い
こうした問題の背景には、ユーザーの購買行動の変化や市場ニーズの多様化に対する対応不足があることが少なくありません。
競合他社と比較してサービス面・操作性・デザイン性で見劣りする状態が続けば、ユーザーはすぐに離れてしまいます。
リニューアルによって、サイト全体の導線を整理し、モバイルファーストの設計を導入することで、離脱率やCVRの改善が期待できます。
売上が頭打ちになっていると感じたときこそ、「今のサイトはユーザーにとって最適か?」を見直す絶好の機会です。
ECサイト移行の事前準備と計画

ECサイトのリニューアルやプラットフォーム移行は、一朝一夕で完了するものではありません。
事前準備が不十分なままスタートすると、スケジュール遅延や想定外のコスト増、機能不足による再開発など、さまざまなトラブルを引き起こしかねません。
成功するリニューアルには「現状把握」「理想像の明確化」「技術と業務要件の定義」「信頼できるプラットフォーム選び」といった段階的な準備が不可欠です。
この章では、移行前に押さえるべき6つのステップについて詳しく解説します。
1. 移行の目的を明確にする
まずは、「なぜリニューアルするのか?」という目的を言語化するところから始めましょう。これが曖昧なままだと、プロジェクトの方向性がぶれたり、関係者間で認識のズレが生じたりして、効果的な改善につながりません。
たとえば、「ページの表示速度を改善したい」「定期購入や予約販売の機能を導入したい」「サイト全体のUI/UXを現代的に見直したい」など、目的は企業によって異なります。
可能であれば「CVRを2%に向上させる」「離脱率を20%削減する」など、定量的な目標を立てることで、プロジェクトの評価指標も明確になります。
2. 現状サイトの課題を洗い出す
次に行うのは、現行サイトの問題点を洗い出すことです。
これは単なる不満点の列挙ではなく、売上や業務にどのような影響があるかを明らかにする作業です。
たとえば、ページの読み込み速度が遅かったり、特定の導線でユーザーの離脱率が高かったり、業務上の対応が属人化していたりと、さまざまなボトルネックが潜んでいるかもしれません。
Google Analyticsやヒートマップ、社内の運用フロー、カスタマーサポートで得た声などを組み合わせることで、表面化していない根本的な課題も発見しやすくなります。
3. リニューアル後のゴールを設計する
課題が明らかになったら、次は「どういうサイトを目指すのか」を具体化するステップです。
UIや導線の改善、商品カテゴリの見直し、スマホでの使いやすさなど、ユーザーの操作感や印象に関わるポイントは特に重要です。
加えて、運用面でも「誰でも簡単に商品を登録・編集できるようにする」「キャンペーンを短時間で設定できるようにする」といった改善目標があるかもしれません。
これらを関係者全員で共有するために、簡易なワイヤーフレームやサイトマップを作成しておくと、プロジェクトの方向性がぶれずに進行できます。
4. システム要件を定義し、企画書に落とし込む
理想のサイト像が固まったら、それを実現するために必要な機能や性能条件をまとめます。これが要件定義のプロセスです。
ここでは以下のような視点が重要になります。
- 実装が必須な機能(例:カート機能、会員登録、定期購入など)
- 連携したい外部サービス(例:LINE、CRM、倉庫管理システムなど)
- 管理画面で必要な操作や設定
- セキュリティ対策(例:SSL、管理画面のアクセス制限)
これらの内容を明文化し、開発会社や関係者と共通理解を持てるように企画書としてまとめます。
言葉の解釈にズレが出ないよう、具体的な画面イメージやフロー図を交えるのも効果的です。
5. 最適なプラットフォームを選定する
どんなに綿密な計画を立てても、移行先のプラットフォームが自社に合っていなければ、サイトのパフォーマンスや運用効率に大きな支障をきたします。
使いやすさや機能の柔軟性、将来的な拡張性など、さまざまな視点で見極める必要があります。
とくに意識したいのが、以下の5つのポイントです。
- 必要な機能が備わっているか
商品登録、カート機能、会員管理、クーポンや定期購入など、自社のビジネスにとって「必須」といえる機能が、標準で用意されているかを確認します。必要な機能が後から追加開発になると、想定外のコストと工数が発生します。 - 将来的に機能を拡張しやすいか
事業の成長や販売チャネルの追加(BtoB販売・海外展開など)に応じて、あとから柔軟に機能を追加できるかも大切です。API連携や外部ツールとの接続のしやすさも確認しましょう。 - 運用しやすい管理画面か
毎日の業務に関わる部分なので、管理画面の使い勝手は軽視できません。非エンジニアでも直感的に操作できるか、複数人で役割分担しやすい設計になっているかを見ておくと安心です。 - 費用が現実的か
初期費用や月額料金に加えて、決済手数料や拡張時の開発費なども含めてトータルでのコスト感を把握します。「最初は安くても成長すると高くつく」といったケースもあるため、長期的な視点での試算が必要です。 - サポート体制が整っているか
不具合や運用トラブルが発生した際、どれだけ迅速かつ丁寧にサポートを受けられるかは安心材料になります。チャット・電話・メール対応の有無や、対応時間帯なども確認しておきましょう。
こうした観点で複数のプラットフォームを比較し、自社の運用体制や中長期的な成長戦略に最もフィットする選択肢を選ぶことが、リニューアルの成功を左右します。
社内スタッフだけでなく、可能であれば第三者やユーザー目線でのチェックも取り入れると、より信頼性が高まります。
6. データを整理し、バックアップを準備する
移行時のトラブルで最も影響が大きいのが、顧客情報や注文履歴といったデータに関するミスです。
リニューアルはシステムやデザインだけでなく、情報資産の移行作業でもあることを強く意識しましょう。
移行対象のデータには以下のような種類があります。
- 顧客情報(会員ID、氏名、メールアドレス、購入履歴 など)
- 商品情報(商品名、SKU、在庫数、カテゴリ、価格、説明文、画像)
- 注文情報(受注番号、購入商品、金額、支払い・配送ステータス)
- コンテンツ情報(LPやブログ、バナー画像、メタ情報など)
- クーポン・ポイント履歴やレビュー投稿データ
これらのデータを安全かつ正確に移行するためには、以下のステップを実施します。
- 不要データの整理:使っていない商品、無効な会員、古いレビューなどを削除。
- 重複チェック:同一情報が複数登録されていないかを確認。特にSKUやメールアドレスの重複は要注意。
- データ形式の整備:移行先プラットフォームの仕様に合わせてCSV等のフォーマットや文字コード、日付形式などを調整。
- バックアップ取得:すべてのデータを移行前にエクスポートし、別環境に保管。万が一の復旧に備える。
- テスト移行と検証:本番前にテスト環境へインポートし、データ件数、レイアウト、リンク切れ、エラー有無を確認。
データ移行は、完了後のチェックも非常に重要です。
移行後に「顧客データが一部欠損していた」「注文履歴が一部消えていた」といったことが発覚すると、大きな信頼損失になります。
可能な限り人の目とツールの両方で検証を重ねましょう。
ECサイトリニューアルの具体的手順
ここからは、実際にECサイトを移行する際の主要なステップについて解説します。
事前準備をしっかり行っていても、移行作業自体が雑になってしまうと、ユーザーや運営チームに大きな混乱をもたらします。
特に、データ移行や機能検証などは繊細な作業です。
各フェーズを丁寧に進めることで、トラブルのないスムーズな切り替えが可能になります。
1. 新しいサイトの設計と開発
移行に向けた第一歩は、新しいECサイトの構築です。単なるシステムの引っ越しではなく、機能改善やデザイン刷新などを含めて「より良いサイトに作り直す」ことが大切です。
このフェーズでは、以下のような要素を整理しながら設計・開発を進めます。
- サイトデザインの再構築(ブランドに合ったUI・UX)
- 新たに必要な機能の実装(定期購入、レビュー、タグ管理など)
- 管理画面の操作性向上(業務効率を意識した導線設計)
また、ユーザーの回遊性や購入率に関わる導線設計や、レスポンシブ対応も忘れてはいけません。
スマートフォン利用が主流となっている今、モバイルファーストの考え方で設計することが、コンバージョン改善にもつながります。
2. データ移行の実施
サイトの構築と並行して進めるのが、既存データの移行作業です。
顧客情報や注文履歴、商品マスタなど、失ってはならない情報が含まれるため、非常に慎重に行う必要があります。
データ移行の手順としては、おおむね以下の流れになります。
- 現行データのエクスポート(CSV・APIなど)
- 新システムへの対応形式に変換・整形
- テスト環境での仮インポートと確認
- 本番環境にインポート
- 移行後の整合性チェック(件数・データ内容・リンク切れなど)
特に重要なのは検証を徹底することです。
データがすべて移ったように見えても、住所が文字化けしていたり、受注データに不備があったりすることがあります。
事前にフォーマットをそろえる、不要データを削除しておくなど、準備段階での対応が移行の精度を高めます。
3. テスト運用と確認
データを移行してすぐに本番公開するのではなく、テスト運用期間を設けて動作確認を行うことが、トラブル防止の鍵になります。
特にチェックすべきなのは以下の機能です。
- 商品ページ〜カート〜決済〜購入完了までの一連の導線
- 会員登録・ログイン・マイページ操作
- 管理画面での受注・出荷処理の流れ
- クーポンやポイントの適用処理
- 外部連携(決済代行、配送会社、MAツールなど)
複数パターンでのテスト(例:ゲスト購入/会員購入、PC/スマホ表示、異なる決済手段など)を行い、抜け漏れがないかを確認しましょう。
このフェーズで確認作業を怠ると、リニューアル直後にユーザーからの問い合わせが殺到したり、売上損失につながる可能性もあります。
社内スタッフだけでなく、可能であれば第三者やユーザー目線でのチェックも取り入れると、より信頼性が高まります。
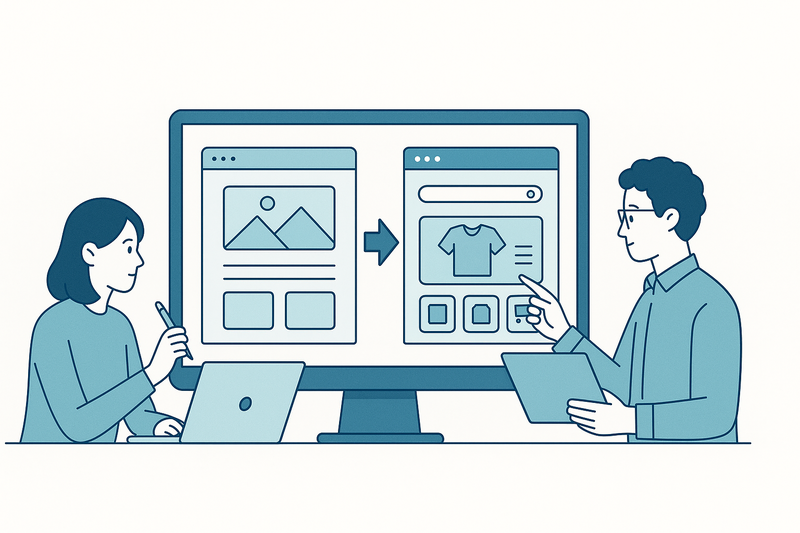
ECサイト移行の費用と予算管理
ECサイトの移行には、一定のコストが発生します。
初期費用だけでなく、継続的に発生するランニングコストや、予期しないトラブルに備えるための追加費用なども見込んでおく必要があります。
この章では、移行プロジェクトに必要な費用の内訳と、その予算をどのように管理すべきかを解説します。
事前に総額感をつかみ、無理のないスケジュールと予算計画を立てることが、プロジェクト成功の鍵となります。
移行にかかる主な費用項目
ECサイトの移行では、下記のような費用が段階的に発生します。
- 初期費用:サイト構築やデザイン、機能開発などにかかる一時的なコスト
- ランニングコスト:サイト公開後に継続的に発生する固定費や手数料
- 追加費用:想定外のトラブル対応、仕様変更による追加開発など
それぞれの費用を正確に把握することで、後から「こんなにかかるとは思わなかった」といった予算オーバーを防ぎましょう。
初期費用
初期費用は、サイトリニューアルの最初のフェーズで最も大きく発生する費用です。主に以下のようなものが含まれます。
- プラットフォーム導入費用:新たに契約するECシステムの初期設定費やアカウント発行費用など
- デザイン費用:サイトのUI/UXデザインを刷新する場合の外注費やテンプレートカスタマイズ費
- 機能開発費:標準機能では足りない部分を開発で補う場合のエンジニア工数(例:定期購入機能、予約販売、外部連携)
- 要件定義・設計・検証費:設計フェーズでのディレクション、テスト環境構築などに伴う費用
特に「カスタマイズ開発」が必要な場合、要件定義が甘いと追加費用が膨らみやすいため、初期の段階で要件をしっかり固めておくことが重要です。
ランニングコスト
サイト公開後に継続して発生する費用は、移行直後は見落とされがちですが、運用の収支に大きく影響するため注意が必要です。
- サーバー・インフラ費用:クラウドサーバーやCDN、セキュリティ証明書(SSL)の維持費など
- 決済手数料:クレジットカード・後払い・コンビニ決済など各種決済サービスにかかる手数料
- 月額利用料:SaaS型のECプラットフォームを利用している場合のライセンス費用
- 保守・サポート費:障害対応や機能保守、軽微な改修にかかるベンダー費用
これらのコストは、売上が増えても一定以上は発生し続けるため、運営体制とのバランスを見て「どこまで内製化できるか」なども検討材料になります。
追加費用
予算には必ず予備枠を設けておくことをおすすめします。
実際の移行プロジェクトでは、以下のような理由で追加費用が発生することが多いです。
- データ移行時にフォーマット不備があり、修正工数がかかった
- テスト段階で想定外の不具合が見つかり、再調整が必要になった
- リリース直前に仕様変更が発生した(UIや導線の調整など)
- 公開後、ユーザーからの要望で緊急の改修が発生した
予備費の目安としては、総予算の10〜20%程度を確保しておくと、突発的な対応にも柔軟に対応できます。
予算管理のポイント
移行プロジェクトでは「作って終わり」ではなく、その後の運用も見据えたコスト設計が必要です。以下の4つのポイントをおさえておきましょう。
- 全体の費用感を初期の段階でざっくり把握する
- 各工程の費用を項目ごとに分解して見積もる
- 契約時にはスコープ外作業の費用感も確認する
- 月次/四半期単位で発生するランニングコストも計算に入れる
特に、外注先との契約では「追加費用が発生しやすいポイント」「費用に含まれる対応範囲」を明確にしておくことで、後々のトラブルを避けやすくなります。
このように、初期・ランニング・追加と三層構造で費用を整理し、適切なタイミングで見直しや調整を行うことで、想定外の出費を抑えつつ、最適な予算配分が実現できます。
ECサイトのリニューアルでよくある失敗例とその対策
ECサイトの移行は多くの準備を要する分、注意すべきポイントも数多く存在します。
計画通りに進めたつもりでも、些細な見落としが大きなトラブルにつながるケースは少なくありません。
この章では、実際のプロジェクトで起こりやすい失敗例とその対策を具体的に解説します。
自社の移行計画を進めるうえで「事前に備えるべき落とし穴」として、ぜひチェックしておいてください。
1. 移行後にデータが欠損・不整合になっていた
顧客情報や注文履歴が正しく移行されていなかった、というトラブルは特に頻発します。
データの項目数が合っていない、文字コードが異なる、特殊文字でエラーが出るなど、細かな不整合が積み重なることで問題になります。
【対策】
移行前に重複・不要データを整理し、移行形式(CSVやAPI仕様)に沿ってフォーマットを整えます。
テスト環境で仮インポートを実施し、データ件数や内容を実機で必ず検証することが重要です。
加えて、すべてのデータを事前にバックアップしておくことで、万が一の際にも復旧が可能になります。
2. 決済やカートなど重要機能に不具合があった
移行直後、「カートが動かない」「クレジットカード決済でエラーが出る」など、ユーザーにとって致命的な機能が正常に動かないケースがあります。
売上に直結するため、最も慎重にチェックすべきポイントです。
【対策】
テスト環境で、注文フローのすべてのパターン(会員購入・ゲスト購入・各種決済手段)を動作確認しましょう。
想定される複数パターンでテストを行い、どの条件でも正常に完了することを確認してください。
公開前に「サンドボックス環境での決済確認」も欠かさずに行うことが重要です。
3. SEO施策が移行後に失われた
リニューアルによってURL構造やディレクトリ設計が変わると、これまで積み上げたSEO評価がリセットされてしまうリスクがあります。
結果として、検索順位が急落し、アクセスや売上が大幅に減少する可能性も。
【対策】
旧URLから新URLへの301リダイレクト設定を必ず行いましょう。
また、metaタグ・titleタグ・hタグなど、SEOに関わる構成要素が正しく引き継がれているかも確認が必要です。
移行直後にサーチコンソールでクロール状況をチェックし、問題があればすぐに修正対応できる体制も整えておきましょう。
4. リダイレクト設定を忘れて流入が激減した
SEOの延長で起こりがちなのが、リダイレクト設定の漏れです。
移行後に「404エラー」が多発している、というのはまさにこのケースが挙げられます。
旧ページから新ページに適切な橋渡しがされていないと、検索エンジンからもユーザーからも評価を落とします。
【対策】
リニューアル前に全URLの一覧を取得しておき、移行先との対応表(マッピング)を作成することをおすすめします。
主要ページは手動で対応し、数が多い場合はリダイレクトルールを使って一括処理も可能です。
5. UI・UX改善のはずが、かえって使いにくくなった
サイトの見た目を「今風」にリニューアルしたものの、かえって使い勝手が悪くなり、購入率が落ちるというケースもあります。
デザイン性を優先しすぎた結果、ナビゲーションが分かりにくくなった、というのは典型的な失敗例です。
【対策】
ユーザー行動をベースに導線を設計しましょう。
実際のヒートマップや離脱率などのデータをもとに、「どこが使いにくいと感じられているのか」「何を改善すべきか」を明確にした上で設計することが重要です。
また、施策前後でのA/Bテストも有効です。
6. 中長期の成長を見据えた設計ができていなかった
目先の機能や見た目だけに集中し、2〜3年後の拡張性や事業方針の変化に対応できないサイトを構築してしまうこともあります。
「この機能はあとから追加しようと思っていたけど、想定よりコストが高かった」というケースも少なくありません。
【対策】
現在の課題解決に加えて、「将来的にどんな販売形態や連携機能が必要になるか」を見据えて設計しておくことが大切です。
CMSやAPIの拡張性、カスタマイズ対応の可否なども含めて、スケーラブルな構成を意識しましょう。
リニューアル後の運用と改善
ECサイトのリニューアルは、移行完了がゴールではありません。むしろ移行の直後からが「本当のスタート」です。
新しい環境で安定運用し、パフォーマンスを最大化するためには、継続的なモニタリングと改善が欠かせません。
この章では、リニューアル後に必ず取り組むべき運用改善ポイントを3つに分けて解説します。
1. パフォーマンスの継続的な監視
移行後の初期段階でまず取り組むべきは、サイト全体のパフォーマンス監視です。
デザインや機能が刷新されても、速度が遅くなっていたり、特定ページでエラーが出ていたりすれば、ユーザー体験を損ねてしまいます。
具体的には、以下のような項目を日次・週次でチェックしていきましょう。
- ページ表示速度(Google PageSpeed InsightsやGTmetrixなどを活用)
- エラーログ(サーバー側、フロント側双方)
- モバイルとPCでの表示・挙動の差異
- 特定商品やカテゴリでの直帰率・離脱率の変化
万が一トラブルや不具合が発覚した際には、影響範囲と原因を早急に特定し、ベンダーや開発チームと連携して対処を行います。
スムーズな運用開始を実現するためには、この「移行直後の初動」が非常に重要です。
2. ユーザーからのフィードバック収集と反映
新しいサイトになってから数週間〜1ヶ月間は、ユーザーの声を積極的に拾うタイミングです。
実際の使い勝手や混乱、気づきは、社内では見落としがちな視点をもたらしてくれます。
次のような方法でフィードバックを集めると効果的です。
- 購入完了メールにアンケートリンクを設置する
- サイト内にフィードバックフォームやチャットボットを設置する
- SNSやカスタマーサポートに届いた意見を集計・分類する
集まった声は、定量データ(GAやヒートマップ)とあわせて分析することで、次の改善施策のヒントになります。
「UIが分かりにくい」「特定操作で迷う」といった声は、最優先で見直しを検討しましょう。
3. コンテンツ・販促施策の最適化と更新体制の整備
リニューアルが落ち着いたタイミングで、サイトコンテンツや販促施策のアップデートに着手することも重要です。
特に旧サイトでは対応が難しかったページ構成や更新作業の効率化などを、あらためて見直せる機会になります。
- 特集ページやLPのテンプレート化で回遊強化
- カテゴリ構成の見直しで導線最適化
- スマホファースト視点での再設計(例:ファーストビュー改善)
- CMSの権限設計と更新フローの整備
また、運用体制そのものも「属人化しない仕組み」に変えていくことが理想です。
誰がどの情報を更新し、どのタイミングでレビューを通すかなど、運用ルールをドキュメント化しておくことで、社内のナレッジが蓄積されていきます。
ECサイトリニューアルの成功事例から学ぶ 業界移行戦略
ECサイトのリニューアルは、単なるデザイン刷新やシステム更新にとどまらず、事業成長の転換点となり得る重要なプロジェクトです。
本章では、ecforceを活用してリニューアルを実施した3社の事例を紹介します。
それぞれの成功事例を通じて、業界特性に応じたリニューアルの方向性や、システム移行における実践的なポイントを学びましょう。
化粧品|移行事例(スタージュ株式会社)
スタージュ株式会社は、複数ブランドを展開する化粧品EC事業において、従来のカートシステムから統合型プラットフォーム「ecforce」へ移行しました。
移行の主な目的は、ブランドサイトの統合による運用効率化と、MA/CRM機能を通じた顧客体験(CX)強化です。
移行後は、ecforce MAを活用した自動配信やセグメント配信により、顧客との継続的なコミュニケーションが実現しました。
同社は「やりたいことを実現できる状態へ移行できた」と評価しており、MAとカート機能の一体的活用によって、CRM強化と売上最大化の両立を推進しています。
出典:ecforceへの移行でやりたいことを実現できる状態へ。ecforce maの活用で顧客体験を向上させたスタージュの施策とは
医薬品・化粧品・機能性表示食品等|移行事例(天藤製薬株式会社)
創業200年を超える天藤製薬株式会社は、自社ブランド「BORRA」「FEMBORRA」などを中心に展開するEC事業において、システムの分断によるデータ管理の課題を抱えていました。
従来はカートシステム、販売分析、商品コード管理がそれぞれ異なる環境で運用されており、業務効率やデータ整合性の面で改善が求められていました。
同社はこれらの課題を解消するため、カート・LP・分析機能を統合的に管理できるecforceへ移行しました。
移行後は商品コード登録工数が約3分の1に短縮され、分析業務の効率化と可視化が進み、データドリブンなEC運営体制を構築しています。
さらに、ecforce biの活用により、LTVを軸としたCRM施策の精度向上にも取り組んでいます。
出典:ecforce biの導入で業務効率とデータ分析精度が向上。創業200年の製薬メーカー「天藤製薬」がecforceで実現したデータドリブンなEC運営とは
セクシャルウェルネス|移行事例(株式会社TENGA)
株式会社TENGAは、公式オンラインストアの運用効率向上およびブランド体験の最適化を目的として、既存のカスタマイズパッケージからSaaS型プラットフォーム「ecforce」へ移行しました。
従来のシステムでは更新作業やキャンペーン対応に柔軟性がなく、運用面での制約が課題となっていましたが、リニューアル後は運用スピードが大幅に改善しました。
また、複数ブランドサイトの一元管理が可能となり、UI/UXの最適化によって購入導線が改善しています。
結果として、ECサイト全体のコンバージョン率は約124%、売上は約120%に伸長しました。
同社はSaaS型の柔軟性を活かし、オフラインとオンラインを連携させたOMO戦略を推進する基盤を整備しています。
出典:ecforceに移行後、売上約120%に伸長。大手企業がSaaSを選択するメリットとは。
まとめ:ECサイト移行の成功のために
ECサイトの移行やリニューアルは、単なる「引っ越し作業」ではありません。ビジネスの成長を支えるインフラを再設計する、大きな転換点でもあります。
その成功には、明確な目標設定と入念な事前準備が欠かせません。
「なぜ移行するのか」「移行によって何を実現したいのか」をチーム全体で共有し、目的に沿った設計と実行を進めることが第一歩です。
また、データ移行やシステム設計、テスト運用など、各工程にはそれぞれ重要な役割があります。
想定されるリスクを事前に洗い出し、トラブルを未然に防ぐための対策を講じることが、プロジェクトの成否を分けるポイントです。
移行完了後も終わりではなく、継続的な改善と最適化を通じて、ユーザー体験や業務効率の向上、売上拡大を実現していくフェーズに入ります。
移行は「成功のゴール」ではなく、「成長のスタート」と捉えて、長期的な視点で運用を続けていきましょう。
※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比
※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月