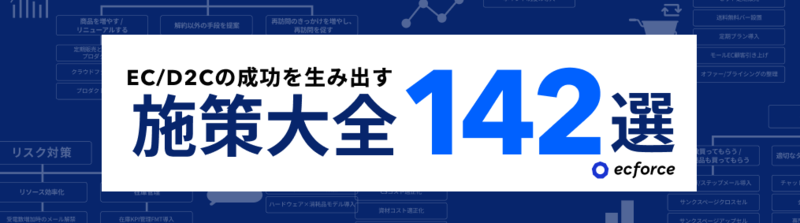この記事でわかること
※この記事は 時点の情報をもとに執筆しています。
EC事業とは、インターネットを通じて商品やサービスを販売するビジネスモデルのことを指します。
スマートフォンの普及、キャッシュレス決済の進化、物流やデジタル広告の発展により、ECは今や誰もが利用するインフラの一部となりつつあります。
また近年では、個人やスモールビジネスでも簡単にオンラインショップを立ち上げられるようになり、企業規模を問わず多くの事業者が参入しています。
本記事では、EC事業の基本的な仕組みから、この事業の魅力と将来性、成功のための具体的なポイント、そして立ち上げまでのステップを解説します。
これからECを始めてみたい人や、リアル店舗をオンラインに移したい人に向けて、今の市場の流れやトレンドも交えながら、役立つヒントをまとめました。
関連するテーマについては、下記の記事もあわせてチェックしてみてください。
EC販売とは?メリットとデメリット・開業ステップを完全ガイド
ECサイト運営の基本業務と必要スキルとは?【初心者向けガイド】
EC事業とは

EC事業とは、インターネット上で商品やサービスを売買するビジネスのことです。「EC」はElectronic Commerce(電子商取引)の略で、日常的には「ネット通販」や「オンライン販売」とも呼ばれます。
一口にECといっても、その形態はさまざまです。たとえば企業が個人に向けて商品を販売する「BtoC(Business to Consumer)」、企業同士で取引を行う「BtoB(Business to Business)」、個人間で商品を売買する「CtoC(Consumer to Consumer)」、そしてメーカーが自社サイトを通じて直接顧客に販売する「D2C(Direct to Consumer)」などがあります。
また、販売チャネルも多様です。自社でECサイトを構築する方法に加え、Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングといった大手ECモールに出店する方法もあります。
さらに、ShopifyやBASEのようなASP型サービスを活用すれば、初期費用を抑えながらスピーディにECサイトを立ち上げることも可能です。
このように、EC事業は事業者の目的や商材、ターゲット層に応じて柔軟に設計できるのが特長です。事業の成長フェーズや運用リソースに合わせて、最適な運営スタイルを選択できるのも、大きな魅力のひとつといえるでしょう。
EC市場の拡大
EC事業が注目される背景には、市場そのものの成長があります。
近年、日本をはじめ世界各国でEC市場は急速に拡大しており、その規模は年々右肩上がりに伸び続けています。
新型コロナウイルスの影響による非対面ニーズの高まりや、スマートフォン経由での購買が一般化したことも、この成長を後押ししています。
ここでは、具体的な市場規模のデータや成長要因に注目し、なぜ今ECがビジネスチャンスとして魅力的なのかを解説していきます。
市場規模の推移
経済産業省の「令和5年度電子商取引に関する市場調査」によると、2023年の日本国内のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模は、前年比9.23%増の24兆8,435億円に達しました。
そのうち物販系分野の市場規模は14兆6,760億円(前年比4.83%増)で、食品、生活雑貨、衣料品など幅広いジャンルでEC化が進んでいます。
また、サービス系分野やデジタル分野も含めると、ECの利便性が生活のあらゆるシーンに浸透していることがわかります。
さらに、企業間取引を対象としたBtoB-EC市場は、2023年に465兆2,372億円となり、前年比で10.7%の伸びを記録。
EC化率は40%に達しており、商取引全体の中でもECの割合が非常に大きな位置を占めるようになっています。
これらのデータから言えるのは、もはやECは「成長している業界」ではなく、「ビジネスの中心的なチャネル」として機能し始めているということです。
特にBtoB領域での成長が顕著で、今後は業種・業態を問わずEC対応が必須になるフェーズに入っているといえるでしょう。
BtoCでも市場規模の伸びとEC化率の上昇が継続しており、新規参入の余地がまだ十分にあることも、事業者にとって追い風となっています。
出典: 経済産業省「令和5年度電子商取引に関する市場調査」https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240925001/20240925001.html
市場成長の背景
EC市場がこれほどまでに成長した背景には、いくつかの社会的・技術的な要因が重なっています。
まず大きな要因のひとつが、スマートフォンとインターネットの普及です。
現在では多くの人が日常的にスマホから商品を検索・比較し、購入まで完結させており、ECは「場所を選ばない購買行動」として完全に定着しています。
次に挙げられるのが、物流インフラと決済手段の進化です。
大手宅配業者を中心とした配送ネットワークの高度化により、当日配送や日時指定など、消費者のニーズに合わせた柔軟な配送サービスが整備されました。
また、クレジットカードだけでなく、スマホ決済や後払い、ポイント払いなど、多様な決済手段が登場したことで、利便性が格段に向上し、購買の心理的ハードルも低くなっています。
さらに、2020年以降の新型コロナウイルスの感染拡大は、EC利用の加速を象徴するターニングポイントとなりました。
外出自粛や対面販売の制限により、消費者はオンラインでの買い物を選ぶようになり、これまでECを利用してこなかった層にも浸透が進みました。
この流れは一時的なものではなく、アフターコロナにおいても継続しており、生活インフラとしての地位を確立しつつあります。
こうした複合的な要因によって、ECは単なる代替手段から当たり前の購買チャネルへと進化し、今後もその成長が止まる兆しはありません。
EC事業のメリット
EC事業には、実店舗型のビジネスにはない多くのメリットがあります。
特に、販売チャネルの柔軟性や運営コストの削減、データ活用のしやすさなど、デジタルならではの強みが光ります。こうした利点を最大限に活かすことで、限られたリソースでも大きな成果を上げることが可能になります。
ここでは、ECを展開することで得られる代表的なメリットについて詳しく解説します。
場所や時間に縛られない販売手法
ECサイトの最大の特長のひとつは、営業時間や立地に制限されることなく、商品を販売できる点です。
実店舗では営業時間や店舗場所に応じて集客が左右されますが、ECでは24時間365日、全国・全世界の顧客に向けて商品を提供できます。
顧客側にとっても、深夜や通勤中、移動中など自分の都合に合わせて自由に買い物できるため、利便性が高く、購買のタイミングも多様化しています。
つまり、販売機会を最大化できるのがECの大きな魅力です。
販売エリアの拡大
ECのもう一つの強みは、地理的な制約がほとんどないことです。
実店舗では商圏が限定されるのに対し、ECではネット接続環境さえあれば、全国どこからでもアクセス・購入が可能になります。
加えて、越境EC(海外向けの販売)にも取り組めば、グローバル市場への進出も視野に入ります。
言語や物流、決済といった障壁も、今では各種ツールやプラットフォームの進化により解消しやすくなっており、海外顧客をターゲットとした戦略も現実的な選択肢になっています。
運営コストの削減
ECでは、実店舗のように高額な賃料や内装工事、人件費が不要なため、運営コストを大きく抑えることができます。
最小限の人員と設備でスタートできる点は、起業や副業としてEC事業を検討する方にとって大きなメリットです。
また、クラウド型ECサービスを利用すれば、初期投資を抑えながらも本格的なサイト運営が可能です。
さらに、在庫管理や受注処理、発送業務などのオペレーションもツールや外注で効率化しやすいため、スケーラブルな運営体制を築くことも可能です。
顧客データの収集と活用
ECサイトは、ユーザーの行動データを収集・活用しやすいという強みがあります。
購入履歴や閲覧履歴、カゴ落ち(カート放棄)などの情報を分析すれば、顧客のニーズや傾向を可視化し、パーソナライズされた提案やリピート施策に繋げられます。
たとえば、特定の商品を何度も見ているユーザーに限定クーポンを配信したり、購入者に対して関連商品をおすすめするなど、1to1のマーケティングが実現しやすい環境が整っています。
こうしたデータドリブンな施策は、LTV(顧客生涯価値)の最大化にも大きく寄与します。
スモールスタートが可能
従来のビジネスでは、在庫確保や店舗構築などにまとまった資金が必要でしたが、ECでは最小限のリスクで小さく始めることができます。
在庫を持たずに商品を販売できるECビジネスモデルであるドロップシッピングや受注生産といった在庫を持たないビジネスモデルも登場しており、「まずはテスト的に販売してみる」というアプローチが現実的に可能なこともメリットとして挙げられます。
このように、仮説検証型でビジネスを進められる点は、特にスタートアップや副業としてECを考えている方にとって、大きな利点となります。
EC事業の課題
EC事業は多くのメリットがある一方で、課題も少なくありません。
市場が成熟し競合が増えた今、ただ商品を並べるだけでは売上は立たず、継続的な改善と差別化の工夫が求められます。
ここでは、EC運営で特に多くの事業者が直面する課題と、その背景にある要因について解説します。
競争の激化
EC市場が成長を続けるなかで、新規参入者は年々増加しています。その結果、あらゆるジャンルで競争が激しくなり、価格勝負に陥るケースも少なくありません。
「他社と何が違うのか」「なぜ自分たちの商品を選ぶべきなのか」といった、明確な価値の打ち出しが不可欠です。
特に大手ECモールでは、似たような商品が大量に並ぶため、見た目や価格だけで選ばれにくくなっています。
SEOや広告運用などの集客施策だけでなく、商品の独自性やブランドストーリーといった「差別化要素」を育てていく視点が重要です。
顧客とのコミュニケーションの難しさ
ECでは、実店舗のような「顔が見える接客」が難しく、顧客との関係構築に工夫が必要です。商品に対する質問や不安をその場で解消できず、説明不足が機会損失につながることもあります。
そのため、わかりやすい商品説明や写真、動画を充実させるのはもちろん、チャット機能やFAQ、レビューの活用など、間接的なコミュニケーションの質を高めることが求められます。
購入後のフォローやパーソナライズされた対応も、顧客ロイヤルティを高める上で欠かせません。
集客のハードルの高さ
多くのEC事業者が直面するのが「集客が思ったより難しい」という壁です。
サイトを作っただけではアクセスは集まらず、検索エンジンやSNS、広告など、複数のチャネルを使って認知を広げる必要があります。
また、集客にはコストもかかります。広告を出してもすぐに成果が出るわけではなく、投資対効果を意識した長期的な設計が求められます。
SEOやコンテンツ施策など、継続的に資産になる集客手段を持つことが、じわじわ効いてくる中長期の戦略となります。
運営負荷とリソースの限界
EC事業は手軽に始められる一方で、日々の運営には意外と手間がかかります。
受注対応、在庫管理、商品登録、カスタマー対応、発送手配、広告運用など、やることは多岐にわたります。
特に少人数や個人で運営している場合、すべてを自力でこなそうとすると、次第にリソース不足に陥ることも。
最初から自動化ツールを導入したり、外部の支援サービスをうまく活用するなど、「やらないことを決める」視点も重要になってきます。
EC事業の業務内容
EC事業は、ただ「商品をサイトに並べて売る」だけでは成り立ちません。運営にはさまざまな業務が関わっており、事業の成長とともに業務の幅も広がっていきます。
ここでは、EC運営における代表的な業務を「販売に関わる業務」と「管理に関わる業務」に分けて解説します。
EC事業を始めるにあたって、自分で担うべき業務と外注・ツールを活用すべき部分を見極めるためにも、全体像を把握しておくことが大切です。
各業務に必要なスキルや進め方については、以下の記事でも詳しく解説しています。あわせて参考にしてみてください。
ECサイト運営の基本業務と必要スキルとは?【初心者向けガイド】|ecforce blog
商品を売るための業務
顧客がECサイトで商品を見つけ、購入に至るまでの流れを設計・改善するのが「販売まわり」の業務です。たとえば以下のようなタスクが含まれます。
- 商品の仕入れ・企画
- 商品ページの作成(写真、説明文、価格設定など)
- サイト全体のデザイン・導線設計
- SEO対策や広告運用
- SNSやメールによるプロモーション
「どうすれば売れるか」を常に考え、顧客の行動を分析しながら改善を重ねていくことが重要です。
また、魅力的な打ち出し方やキャンペーン設計も、EC運営の腕の見せ所です。
注文後の対応と管理業務
商品が売れた後には、スムーズに顧客へ届けるための運営業務が発生します。こちらは「管理まわり」にあたる部分です。
- 受注管理(注文確認、発送準備など)
- 在庫管理(リアルタイムの在庫把握、仕入れ調整)
- 発送・配送(梱包、伝票発行、配送会社連携)
- カスタマー対応(問い合わせ、返品・交換など)
- 会計・経理(売上集計、月次処理など)
運営業務が滞ると、顧客体験にも直接影響します。
作業の一部はツール導入や外注で自動化・効率化できるため、手間のかかる工程ほどシステム活用を検討するのが賢い運営方法です。
分析・改善業務
EC事業では「やって終わり」ではなく、「やったことを振り返って改善する」ことが極めて重要です。
日々の業務を回すだけでなく、数字を見ながら改善していく姿勢が欠かせません。
アクセス解析ツールを使って、どのページが見られているか、どこで離脱しているかを把握したり、商品ごとの売上やコンバージョン率を確認したりすることで、売れる仕組みを少しずつ最適化していくことができます。
また、顧客レビューや問い合わせ内容を拾い上げて商品ページに反映したり、メール配信や広告のABテストを行ったりするなど、ユーザー視点の改善も有効です。
こうした小さな改善の積み重ねが、長く売れ続けるECサイトを育てるうえでとても重要です。
EC事業を成功させるためのポイント

EC事業は始めること自体は簡単でも、継続して成果を出し続けるのは決して容易ではありません。
競合との差別化、顧客との関係構築、効率的な集客と運営体制づくりなど、多角的な視点からの戦略が求められます。
このセクションでは、特に重要な成功の要素を4つのポイントに分けて解説します。
魅力的な商品訴求
ECでは、実物を手に取れない分、商品の魅力をどれだけ的確に・わかりやすく伝えられるかが勝負になります。
高品質な商品画像、使い方がイメージできるシーン写真、わかりやすい説明文など、購入の後押しになる要素を丁寧に整えることが重要です。
また、レビューや口コミの掲載、比較表の活用、Q&Aの設置なども、購入の不安を解消し信頼感を高めるポイントとなります。
動画やライブ配信による紹介コンテンツも、ブランドの雰囲気や使用感を伝える手段として有効です。
ロイヤル顧客の育成
リピーターを増やすためには、単なる商品提供にとどまらない関係づくりが鍵となります。
購入後のサンクスメール、配送状況の丁寧な連絡、問い合わせ対応の速さなど、細やかなフォローが顧客満足につながります。
また、レビューへの返信や、誕生日クーポン、定期的なフォローメールなど、一人ひとりの顧客を大切にする姿勢が伝わると、自然とリピート率やLTV(顧客生涯価値)も上がっていきます。
ロイヤル顧客の育成は、長期的な安定経営の土台になります。
集客チャネルを複数持つ
「良い商品をつくったから売れる」という時代ではなくなり、集客こそがECの最重要課題と言えます。
SEO対策をベースにしながら、SNS運用、リスティング広告、インフルエンサー連携、YouTubeやブログなど、多角的なチャネルを組み合わせて集客導線を作ることが必要です。
重要なのは、施策ごとの役割を明確にすること。
認知拡大、再訪促進、比較検討の後押しなど、顧客の行動ステージに合わせて使い分けると、効率よく成果につながります。
PDCAを回して売れる仕組みを育てる
一度作った商品ページや広告を放置せず、定期的に見直して改善を重ねていくことが、売上を安定して伸ばすうえで不可欠です。
たとえば、アクセス数があるのに売れないページは、商品写真や価格設定、説明文に改善の余地があるかもしれません。
数値を見ながらPDCAを回し続けることで、集客・転換・リピートすべてのステージで成果が積み重なっていきます。
「売れない理由を数値で探す」「うまくいった施策を再現する」視点を習慣にすることが、強いEC事業をつくる基本姿勢です。
EC事業立ち上げのステップ
EC事業を始めるには、アイデアや商品があればすぐに始められるイメージがありますが、実際にはいくつかの段階を踏んで準備を進めることが成功のカギになります。
この章では、初めての方でも取り組みやすいように、EC立ち上げまでの基本的なステップを順を追って解説します。
事業計画の策定
まず大切なのは、売りたい商品やサービスを明確にし、「誰に」「どのように」届けるのかを考えることです。
ターゲット層や市場ニーズをリサーチし、競合のECサイトや販売方法も分析します。
あわせて、どのくらいの予算でスタートできるか、売上目標や採算ラインはどこかなど、簡単な収支モデルを作るのもおすすめです。
ここでの設計が後々の意思決定をスムーズにしてくれます。
サイトの構築
販売チャネルを「自社サイト」で構築するのか、「モール型プラットフォーム」に出店するのかによって、準備の内容や方向性は大きく変わります。
たとえば、ShopifyやBASEなどのASPサービスを使えば、コーディング不要で短期間に自社ECサイトを立ち上げることができます。
一方、Amazonや楽天市場などの大手モールに出店すれば、集客力や信頼性を活用しながら販売に集中することが可能です。
商品の写真撮影や説明文の作成、決済方法の設定、配送会社との連携、特商法に基づく表記など、サイト開設前にやるべきことは多岐にわたります。
以下の記事を参考に、全体の流れを事前に把握しておくと安心です。
ECサイトの仕組みとは?ECサイト一覧や4つの作り方をご紹介|ecforce blog
集客施策の実行
サイトを公開したら、次に必要なのは「見込み客をどう集めるか」です。
ECサイトは作っただけでは誰にも見つけてもらえません。だからこそ、早い段階から集客チャネルの選定と運用がカギとなります。
集客方法には、おもに以下のような手段があります。
- SEO(検索エンジン対策):商品名やカテゴリで検索されたときに上位表示されるよう、サイト構造やコンテンツを最適化。
- SNS運用:InstagramやX(旧Twitter)、TikTokなどを活用し、ファンづくりや商品情報の発信。
- Web広告:Google広告、Instagram広告などを用いたターゲティング広告で、短期的な集客を強化。
- メルマガ・LINE配信:見込み顧客のリストを獲得し、継続的に情報を届ける手段として活用。
立ち上げ初期は、どのチャネルに注力するかを絞り込み、「テスト → 反応確認 → 改善」を繰り返しながら、最適な集客スタイルを見つけるのがポイントです。
分析と改善
集客を始めた後は、「アクセスは集まっているのに売れない」「カートに入るのに決済されない」といった壁に必ず直面します。
そこで重要なのが、データをもとに改善を繰り返す視点です。
主にチェックすべきポイントは以下の通りです。
- アクセス解析:どのページがよく見られているか、どこで離脱しているかをGoogleアナリティクスなどで確認。
- コンバージョン率(CVR):商品ページに来た人のうち、何人が購入しているか。CVRが低ければ、写真や説明文の改善が必要です。
- カゴ落ち率:カートに入れたものの、決済まで進まないケース。送料や会員登録の手間が障壁になっていないか検証します。
- レビューや問い合わせの内容:顧客の声から気づく改善点は多く、商品説明や導線設計のヒントになります。
改善に終わりはありません。
売れた商品や反応がよかった施策は再現性を検証し、うまくいかなかった部分は丁寧に原因を探るといった「地道ながら着実な改善」の積み重ねが、EC事業を持続的に成長させる大きな原動力になります。
まとめ
EC事業は、インターネットを通じて商品やサービスを販売する現代的なビジネスモデルであり、今や多くの企業や個人にとって欠かせない販売チャネルとなっています。
市場は年々拡大を続けており、スマートフォンやSNS、物流・決済の進化といった要素が、さらなる成長を後押ししています。
本記事では、EC事業の基本からメリット・課題、業務内容、成功のためのポイント、そして立ち上げのステップまでを一通りご紹介しました。
ECは低リスクで始められる一方で、継続的に成果を出すには、商品訴求・顧客対応・集客・改善といった複数の観点で戦略的な運営が求められます。
特にこれからECを始める方にとっては、「まずは小さく始めて、数字を見ながら改善していく」姿勢が何より大切です。
ツールや外部サービスも活用しながら、売れる仕組みを少しずつ育てていくことが、成功への最短ルートとなるでしょう。
ぜひ本記事をヒントに、ECビジネスへの一歩を踏み出してみてください。
※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比
※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月