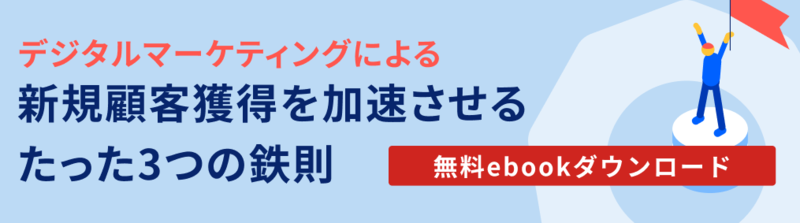この記事でわかること
※この記事は 時点の情報をもとに執筆しています。
はじめに
EC市場の成長と共に、広告コストの高騰や競合の激化が進む中、「自社で顧客との接点を持ち続ける手段」として注目されているのがオウンドメディアです。
SNSや広告だけに依存せず、独自に情報発信する仕組みは、ブランド価値の醸成・SEO集客・ファン化において極めて重要な役割を果たします。
本記事では、EC事業者がゼロから成果を出すオウンドメディアを構築・運営するための具体的なステップ、成功事例、活用ツールまでを網羅的に解説します。
関連するテーマについては、下記の記事もぜひチェックしてみてください。
ECサイトの売上を伸ばすマーケティング戦略|集客・CVR改善・リピーター獲得のポイント
ECサイト集客術|売上を伸ばすための成功ポイントと注意点まとめ

オウンドメディアとは?基本と最新トレンド
オウンドメディアの定義と特徴
オウンドメディアとは、企業が自社で所有・管理する情報発信媒体を指します。
自社のドメインで構築されるブログ、Webメディア、ブランドサイトなどが該当します。
広告に頼らず、自社の資産として蓄積される点が大きな特徴です。
ペイド・アーンドメディアとの違い
- ペイドメディア(広告):Google広告、SNS広告などお金を払って一時的に露出を得る手段
- アーンドメディア(第三者評価):SNSでの拡散やレビュー記事など、第三者による発信
- オウンドメディア:自社がコントロール可能な持続的チャネル
上記3つのメディアをどう連携させるかが戦略の鍵になります。
最新のトレンドとユーザー行動の変化
近年、オウンドメディアのトレンドは、単なるSEO対策や情報発信の場から、よりユーザー体験(UX)を重視した設計へと進化しています。
スマートフォン経由での閲覧が主流になったことで、ページの読みやすさや導線設計だけでなく、読者が心地よくストーリーを体感できるようなコンテンツ設計が求められるようになっています。
さらに、SNSや動画との連携強化も顕著です。InstagramやTikTokを活用した商品体験投稿やブランドストーリー動画をメディア内に組み込む事例が増加し、検索流入だけでなく、SNSからメディアへの誘導、さらにECへのスムーズな導線構築が重要になっています。
加えて、Googleなどの検索エンジンを通じた一般的なキーワード流入だけでなく、ブランド名やサービス名での指名検索の重要性も高まっています。
ユーザーは複数サイトを比較し、納得した上で購入する傾向が強くなっており、そのためにもブランドの思想や体験価値を語るコンテンツのニーズが高まっています。
こうした変化に対応するためには、オウンドメディアを情報を並べる場からブランド体験の場へと進化させる視点が不可欠です。
なぜ今、EC事業者にオウンドメディアが必要なのか?
EC市場は拡大を続けていますが、同時に広告費の高騰、顧客獲得競争の激化、プラットフォーム依存のリスクも深刻化しています。
従来のリスティング広告やSNS広告だけでは、顧客の獲得単価(CPA)が跳ね上がり、収益性が低下するケースが増えています。
こうした背景から、自社で顧客との接点を持ち、ブランドや商品の魅力を語れる場として、オウンドメディアの重要性が再評価されています。
集客コストの高騰と依存脱却
近年、Google広告、Meta広告など主要チャネルの広告費は前年比10〜20%で高騰しています。
特にEC業界では競合が多く、特定キーワードのクリック単価(CPC)が高騰し、1件あたりの獲得コストが利益率を圧迫する状況が続いています。
こうした状況下で注目されているのが、SEOを活用したオーガニック集客です。
オウンドメディアによる検索流入は、初期投資は必要ですが、中長期的に見れば広告に頼らず資産型の集客チャネルになるため、広告依存体質からの脱却を図れます。
また、広告停止=集客停止というリスクも低減でき、安定した流入を自社メディアで持つことが、EC事業の持続可能性を高めるポイントになります。
顧客との長期的関係構築
オウンドメディアは、単なる集客装置ではなく、顧客と長く付き合い、信頼を育てる場としても重要な役割を果たします。
例えば、商品購入前の悩み解決記事や、購入後の使い方ガイド、体験インタビュー記事などを通じて、購入前後の顧客接点を密にし、継続購入やLTV(顧客生涯価値)向上につなげることが可能です。
SNSや広告のような一過性の接触ではなく、検索やメルマガを通じて何度もコンテンツに触れてもらうことで、顧客との間に関係性を築き、ファン化→リピート化→LTV最大化という黄金ルートを形成できます。
ブランドの信頼獲得と差別化
EC事業者が価格競争から抜け出すためには、単に「安い」「便利」ではない独自のブランド価値を伝える必要があります。
その際、オウンドメディアはブランドの世界観や想いを丁寧に伝え、顧客と共感を育むための最適なチャネルになります。
たとえば、商品開発ストーリー、社員インタビュー、顧客との共創エピソードなどをメディア内で発信することで、他社との違いを言葉と体験で伝え、信頼とブランド認知を強化できます。
検索や広告だけでは伝わらないブランドの深い価値を、顧客が自ら見つけ、理解し、共感する流れを作ることが、オウンドメディアの最大の強みと言えるでしょう。
オウンドメディア構築の全体ステップ
オウンドメディアは単なる記事を並べる場所ではなく、ブランドや商品を理解し、共感し、購入まで導く資産型チャネルです。
しかし、やみくもに記事を量産しただけでは、成果につながらず、運営コストだけが膨らむケースが少なくありません。
そこで重要になるのが、明確な戦略設計のもと、段階的に構築ステップを進めることです。
以下に、EC事業者が押さえるべき全体のプロセスを解説します。
目的とKPIの明確化
構築前に最優先で行うべきは、「何のためにオウンドメディアを作るのか」という目的の言語化と社内共有です。
これが曖昧なまま進めると、記事の方向性も評価指標もブレてしまいます。
具体的には、次のような目的が考えられます。
- 新規顧客獲得
- ブランド認知拡大
- リピーター育成・LTV向上
- 購入導線への誘導
目的に応じて、PV(ページビュー)、CVR(コンバージョン率)、検索順位、流入キーワード数、滞在時間、会員登録数など、具体的なKPIを設計し、モニタリング体制を整えます。
ペルソナ設計とカスタマージャーニー分析
「誰に届けたいのか」を明確にすることは、コンテンツの精度と成果を左右する最重要ポイントです。
ターゲット層の属性(年齢、性別、職業、趣味)、抱えている課題や悩み、情報収集の習慣などを言語化し、社内で共有します。
その上で、以下のようなカスタマージャーニー(購買行動フロー)を設計し、各ステージで必要な情報をマッピングします。
- 認知:まだ商品やブランドを知らない
- 興味:興味を持ち、調べ始める
- 検討:他社と比較し、購入を検討する
- 購入:購入に至る
- 継続:リピート購入、ファン化
このジャーニーに沿って、必要な記事やコンテンツの型を計画することが、成果を最大化する鍵になります。
コンテンツ戦略の設計
ペルソナとジャーニーが明確になったら、実際のコンテンツ戦略を策定します。
- 何を書くか(記事ジャンル、テーマ、形式)
- どう書くか(語り口、構成、表現トーン)
- どう届けるか(SEO・SNS・メルマガ・広告など)
重要なのは、「SEO対策」「ブランディング」のどちらか一方に偏らず、検索ニーズとブランド価値訴求の両輪で設計することです。
たとえば、SEOを意識した「〇〇の選び方ガイド」だけでなく、ブランドストーリーや開発秘話など、共感型のコンテンツも計画的に組み込むことがポイントです。
CMS・ドメイン・デザインの選定
メディア構築には、適切なCMS(コンテンツ管理システム)の選定も不可欠です。
使い勝手や運用負荷、社内リソース、セキュリティ要件に応じて選びましょう。
CMSにはさまざまな種類がありますが、以下は特に多くの企業で導入されています。
- WordPress https://wordpress.com/(運営会社:Automattic Inc.)
特徴:自由度とカスタマイズ性が高く、SEO対策しやすい - microCMS https://microcms.io/(運営会社:株式会社microCMS)
特徴:ヘッドレス型CMSでAPI連携が可能。開発体制が整っている場合に最適 - note pro https://biz.note.com/(運営会社:note株式会社)
特徴:スピーディーに記事運営を開始したい企業におすすめ
ドメインは、ECサイトと同一ドメイン配下か、独立ドメインかも事業戦略に応じて選びましょう。
立ち上げ・初期公開までの流れ
準備が整ったら、いよいよ立ち上げフェーズです。
ただし、いきなり全力投入するのではなく、まずはミニマムでスタートし、検証しながら育てる姿勢が重要です。
- テンプレート/構成案を策定
- 初期10〜20記事を執筆(ペルソナとジャーニーを元に優先テーマを選定)
- CMS・デザイン設定
- 初回公開&社内外での認知施策
この立ち上げまでには、1〜2ヶ月程度の準備期間を見込むのが現実的です。
その後、検証フェーズを経て、コンテンツ改善や流入拡大施策を本格化していきます。
コンテンツ設計の具体的手法
オウンドメディアで成果を出すためには、「どのようなコンテンツを、どのような順序で、どんな目的で発信するのか」を明確に設計する必要があります。
記事数を増やすことだけに注力すると、検索順位が上がらない、読まれない、CVにつながらないといった結果になりかねません。
重要なのは、ペルソナの情報ニーズ、ジャーニーごとの役割、SEOとブランド訴求のバランスを踏まえ、戦略的にコンテンツ設計を行うことです。
SEOを意識したコンテンツ戦略
オウンドメディアの安定した流入を確保するためには、Googleなどの検索エンジンからの流入獲得が基本です。
特にEC事業では、SEO施策が集客の土台となります。
まず、狙うべきキーワードを選定し、そのキーワードが持つ検索意図(情報収集・比較・購入など)を把握します。
たとえば「白Tシャツ おすすめ」という検索キーワードなら、ユーザーは商品そのものより「どれを選べばいいのか」「どんなブランドがあるのか」を知りたいはずです。
そのため、単なる商品一覧ではなく、比較表や選び方ガイドなど、検索意図に合ったコンテンツ企画が必須になります。
加えて、記事構成ではH2・H3タグを正しく使い、読者が迷わず情報にたどり着けること、E-E-A-T(専門性・経験・権威性・信頼性)を意識した、実体験や監修入りの記事を作成することで、SEO評価とコンテンツの説得力を同時に高めることが可能です。
ECと相性の良いコンテンツジャンル
EC商材によって、相性の良いコンテンツジャンルは異なります。
以下のような切り口を参考に、自社の商材特性に合わせた企画を行いましょう。
- アパレル:着回しコーディネート特集、季節別スタイルガイド、素材・サイズ比較
- 食品・飲料:レシピ提案、食材の選び方、産地レポート、シーズナル商品特集
- コスメ・美容:使用レビュー、スキンケア手順、肌タイプ別おすすめ記事、悩み別FAQ
- ライフスタイル雑貨:使い方シーン提案、収納術、長持ちさせる手入れ法、プロ監修記事
重要なのは、単なる商品紹介にとどまらず、読者の課題解決や新しい発見につながる情報を加えることです。
これにより、SEO対策だけでなく、商品理解と購入意欲の醸成が期待できます。
記事制作・外注・編集体制の整備
高品質なコンテンツを継続的に生み出すためには、社内外の体制整備も欠かせません。
特にEC企業では、制作体制が整わないまま開始し、途中で運用が止まるケースが多いため注意が必要です。
- 社内に編集責任者(メディアマネージャー)を置く
- 記事制作ガイドライン(トンマナ、語尾ルール、NGワードなど)を文書化
- 外部ライター活用時は、構成案、SEO要件、チェックリストを共有
- 校正・ファクトチェック体制を明確にし、リライトや改善前提の運用にする
1人担当型で全てを担うと破綻しやすいため、分業型のプロセス構築を早期に行うことが、持続可能な運営の鍵です。
更新頻度とスケジュール設計
どれだけ高品質なコンテンツでも、更新が途切れればSEO評価は落ち、ユーザーの期待にも応えられません。
最低でも週1〜2本の更新を目安とし、コンテンツの種類やシーズン性を加味したカレンダー形式で運用管理することが重要です。
たとえば、毎月の運用では、季節特集記事を1本、HOW TOガイドやレビュー記事を2本、ブランドストーリーや社員インタビューを1本組み込むなど、バランスの取れたコンテンツラインナップを組み立てると、SEO集客・ブランド強化・LTV向上のすべてを意識した運用がしやすくなります。
このように、SEO集客向けコンテンツとブランド価値訴求コンテンツの双方を計画的に織り交ぜることが、EC事業者のメディア運営における最適解になります。
集客・拡散施策とSNS連携
せっかく作成したコンテンツも、届け方を工夫しなければ埋もれてしまいます。
SEOだけでなく、SNS、広告、メルマガとの連携を戦略的に行うことで、複数の接点からユーザーを呼び込み、検索以外の流入チャネルを強化する仕組み作りが重要です。
SEO・広告・SNS・メルマガの連携
オウンドメディアの集客の基盤はSEOですが、検索流入だけでは不十分です。
特にEC領域では、SNS経由の比較検討や、リターゲティング広告による再訪問施策が成果を左右します。
よく活用されている手法には以下があります。
- Instagram、X、TikTokでの記事ハイライトとURL付き投稿。特にTikTokコマース連携による「視聴→購入」の動線は近年のトレンド。
- Meta広告やGoogleディスプレイ広告を活用し、メディア訪問者へのリターゲティング配信を実施。記事コンテンツ自体をLPの代替として広告出稿する事例も増加しています。
- メルマガ配信では、単なる記事紹介ではなく、購入特典、限定クーポン、関連商品のバンドル提案を併記することで、CVへの寄与度を高める。
これらを連携させ、1本の記事が複数チャネルに波及し、購買行動を後押しする流れを仕組み化することで、メディアとしてのROI(投資対効果)を高めることができます。
SNSでのUGC活用と顧客共創型施策
ユーザー自身の体験談(UGC:User Generated Content)は、広告よりも信頼性が高く、共感を呼ぶ力があります。
ハッシュタグ設計や、ユーザーの投稿をオウンドメディアで紹介する仕組みは基本施策ですが、近年は顧客を巻き込んだ共創コンテンツ(たとえば「商品レビュー座談会」「モニター体験レポート」)や、ファンコミュニティの設立・運営まで進化しています。
- SNS投稿募集を行い、投稿事例をまとめて記事化する
- ブランド公式SNSで、ユーザー投稿を定期的にリポストするUGCキャンペーンを実施
- オウンドメディア内に「みんなの使い方特集」「私たちのお気に入り商品投稿」など、顧客参加型の常設コーナーを設置
このような取り組みは、UGCを一過性ではなく、自社コンテンツ資産に昇華し、ECへの信頼醸成→購入促進につなげる流れを生み出します。
ECサイトとメディアの相互導線最適化
メディアからECへの導線設計は、単なる商品リンク挿入だけではなく、ユーザー行動データを元に最適化を行うことがポイントです。
- 記事中に関連商品のリンク・画像・CTA(行動喚起)を自然に差し込む。特にヒートマップで読了率を確認し、適切な位置にCTAを配置することで、CVRを高めることができます。
- 商品ページに「この商品を使ったアイデア記事はこちら」といったメディア導線を逆設計で設置し、EC→メディア→リピート促進の循環をつくる。
- 比較記事から個別商品記事、体験記事→購入ページへの動線を、ジャーニーごとに設計し、導線ごとの効果をGA4で検証・改善を繰り返す。
これらを実施することで、オウンドメディアはブランドの情報発信基地ではなく、売上に貢献する収益装置型メディアへと進化します。
効果測定と改善運用
オウンドメディアの成果は、ただ記事を公開するだけでは測れません。
重要なのは、定期的にデータを確認し、改善のアクションを起こすことです。
データ分析が形骸化しがちな企業も多いため、「見て終わり」ではなく「行動を変えるための分析」を意識する必要があります。
ここでは、基本的な分析ツールと、実践的な改善運用のステップを紹介します。
GA4・GSCなどの基本的な解析ツール
まず、必須の解析ツールは以下の通りです。
- Google Analytics 4(GA4)
→ ユーザーの流入経路、滞在時間、スクロール率、イベントデータなどを把握可能。最近はGoogle DiscoverやPush通知経由の流入も計測対象になってきています。
https://analytics.google.com/ - Google Search Console(GSC)
→ 検索クエリごとの表示・クリック・CTRを把握し、特に指名検索(ブランド名流入)比率のモニタリングも重要です。
https://search.google.com/search-console/ - Microsoft Clarity や Ptengineなどのヒートマップツール
→ ページ内の読了率、クリック位置、離脱箇所などを可視化でき、コンテンツ改善だけでなく、CTA位置の最適化にも活用可能です。
これらを活用することで、「読まれているけれどCVしていない」「最後まで読まれていない」「SNS流入は高いがSEO流入は低い」など、課題を構造的に把握しやすくなります。
KPI達成度のチェックとPDCAサイクル
KPIを達成するためには、仮説→実行→効果検証→改善の流れを継続することが重要です。
しかし、よくある失敗は「データは取っているのに、改善アクションにつながらない」ことです。
その原因は、KPIがPVや順位など短期指標だけに偏り、中長期的なLTV貢献や指名検索増などのブランド指標が評価対象から漏れてしまうことが挙げられます。
月次の振り返りでは、以下の指標をバランスよく確認します。
- PV数/セッション数:記事全体・カテゴリ別・記事単体の推移比較
- 平均滞在時間/直帰率/読了率:コンテンツの魅力度やUXの確認
- 流入キーワード数/表示回数:SEO施策の広がりと深さ
- CVR(コンバージョン率)/クリック数:問い合わせ、商品クリック、購入などへの寄与
- 指名検索(ブランド名流入)/ブランド名CTR:ブランド認知・信頼形成指標
KPIの定点観測を通じ、注力すべきジャンルや伸び悩んでいるテーマを洗い出し、コンテンツ改善・導線改善を実行します。
コンテンツリライトと再活用
オウンドメディアの運用では、新規記事を作るだけでなく、既存記事のリライトや再構成がROI改善の鍵となります。
特にSEO評価が低下しやすい情報ジャンルでは、リライト優先順位付けと、運用フローの整備が重要です。
リライト優先順位をつける際の視点
- 検索順位が10〜30位台で止まっている記事(改善余地大)
- 流入はあるが、CVRが低い記事(導線改善対象)
- Google Discover流入が強い記事(更新頻度と情報鮮度維持が必要)
改善例
- 最新情報の追記
- 見出し構成の整理
- CTA強化と配置の見直し
- 内部リンクの最適化
- キーワードカニバリゼーション(競合記事同士の整理)
さらに、SEOだけでなく、関連記事を束ねた「完全ガイド化」や、記事シリーズをホワイトペーパー化してリード獲得施策への転用もおすすめです。
社内でのリライトプロセスを整備する際は、SEO担当と編集チームの連携フローを整え、改善ログを必ず残すことで、PDCAの属人化を防ぐこともポイントです。
EC事業者向けの成功事例3選
ここでは、実際にオウンドメディアを長期的に育て、成果を生み出しているEC関連企業の事例を紹介します。
各社ともに独自のブランド哲学とユーザー体験設計を重視し、単なる販売チャネルではなく、生活者との関係性を深めるメディアへと進化させています。
運用の姿勢や導線の工夫など、他社EC事業者が学ぶべき視点に注目しながら紹介します。
北欧、暮らしの道具店(運営:株式会社クラシコム)
「北欧、暮らしの道具店」は、生活雑貨やファッションなどを販売するECサイトですが、オウンドメディアの役割は単なる商品紹介にとどまりません。
エッセイやショートドラマなどを通じて、暮らしの空気感や季節感を丁寧に伝え、ブランド世界観を体験できるコンテンツを展開しています。
オウンドメディアで接触した読者が、ストーリーの延長線上で商品に出会い、購入に至るまでの導線設計も秀逸です。
購買導線が押し付けがましくなく、読者にとって自然な流れで構築されている点が、他社ECでも参考にしたいポイントです。
長期的にファンを育て、生活の一部としてブランドを感じてもらうメディアとして、オウンドメディアの可能性を拡張している好事例と言えるでしょう。
niko and ...(運営:株式会社アダストリア)
ファッションブランド「niko and ...」が運営する独自メディアは、コーディネート提案だけでなく、カルチャー、音楽、インタビューなどを交えたライフスタイルメディアとして展開しています。
特にZ世代〜30代のライフスタイル感にフィットしたビジュアル設計やSNSとの親和性の高さが強みで、記事を読んだ流れの中で商品ページにスムーズに遷移できる導線設計も秀逸です。
ブランドメッセージやトレンド情報を読み物として楽しんでもらうことで、単なる通販サイトを超えたメディア価値を提供しており、生活者との距離感を近づける戦略が際立っています。
LIFULL HOME'S PRESS(運営:株式会社LIFULL)
「LIFULL HOME'S PRESS」は、不動産・住宅関連情報を提供するメディアですが、単なる情報提供にとどまらず、専門家インタビューや調査データをもとにした社会的価値の高い記事を継続的に発信しています。
SEO面でも高評価を得ており、指名検索や長期的な情報資産の構築にもつながっている点が特徴です。
検索流入だけでなく、SNSでのシェアやメディア引用も多く、業界内外から信頼される情報発信メディアとしての地位を築いています。
記事からの送客に加え、企業ブランディングや事業領域への信頼形成にも貢献しており、EC事業者にとっても信頼を醸成するメディア作りのヒントが詰まった好事例です。
オウンドメディア構築に役立つツール紹介
オウンドメディアを成果につなげるためには、単に記事を作成するだけでなく、企画・執筆・運用・分析まで、各フェーズで適切なツールを活用することが不可欠です。
ここでは、カテゴリ別にEC事業者が取り入れやすいツールを紹介します。
ツール選定の際は、社内のリソース状況や運用フェーズに合わせて、無理なく導入できるものを選びましょう。
CMS(コンテンツ管理システム)
WordPress(運営:Automattic Inc.)
https://wordpress.com/
世界的に利用されているオープンソースCMSです。柔軟なカスタマイズ性が魅力で、SEO対策にも適しており、ECサイトとオウンドメディアを統合して運用したい場合にも向いています。
microCMS(運営:株式会社microCMS)
https://microcms.io/
日本製のヘッドレスCMSで、API連携によってフロントとバックを分離できるのが特長です。デザインの自由度を高く保ちながら、高速でコンテンツ運用を進めたい場合に適しています。
note pro(運営:note株式会社)
https://biz.note.com/
法人向けプランで、すぐに記事投稿・管理ができるシンプルなUIが特徴です。短期間でメディア立ち上げをしたい企業や、社内リソースが少ない場合でもスムーズに運用を始められます。
SEO・解析ツール
Ahrefs(運営:Ahrefs Pte. Ltd.)
https://ahrefs.com/ja
競合調査やキーワード難易度分析、被リンク調査などSEO戦略を設計する上で役立つ高機能ツールです。競合メディアの分析や、新たなコンテンツ企画のネタ出しにも活用されています。
Google Search Console(運営:Google LLC)
https://search.google.com/search-console/about
SEO流入やインデックス状況、クリック率などを無料で把握できる必須ツールです。ブランド名流入や指名検索の比率も確認できるため、ブランド価値の育成にも活用できます。
Similarweb(運営:Similarweb Ltd.)
https://www.similarweb.com/ja/
自社と競合サイトのトラフィックや流入チャネル構成を比較できるツールです。業界全体のポジション把握や、自社メディアの改善ポイントの発見に役立ちます。
執筆・編集支援ツール
ChatGPT(運営:OpenAI)
https://chat.openai.com/
構成案やタイトル案、下書き作成を支援できる生成AIツールです。企画出しや記事作成の効率化に活用されていますが、最終的な品質確認や表現調整は人の手によるチェックが必要です。
Grammarly(運営:Grammarly Inc.)
https://www.grammarly.com/
英語記事中心のツールですが、文章の構成や表現の重複確認にも使えるため、英語対応やグローバルメディア運営の場合は導入価値があります。
Kafkai(運営:合同会社LaLoka Labs)
https://kafkai.com/ja/
AIによる記事生成ツールです。SEO記事やブログの下書き作成に役立ちますが、最終的な品質担保のため、校正やリライト前提で活用するのが基本です。
EC×オウンドメディアの未来
オウンドメディアの役割は、単なる情報発信やSEO対策のためのチャネルから、ブランド価値を育て、生活者と継続的な関係を築くための基盤へと進化しています。
EC領域では特に、メディアを通じて顧客とつながり、売上を生み出す体験設計が求められるようになっています。
今後、さらに注目すべきトレンドとして、以下の3つが挙げられます。
AI・自動化による編集支援
ChatGPTをはじめとする生成AIや自動化ツールの進化により、構成案作成やタイトル案出し、仮原稿作成までが効率的に行えるようになってきました。
実際、記事制作の初期段階をAIで補助し、編集チームは企画の精度向上や、ブランド視点での品質チェックに専念する流れが主流化しています。
また、CMSと連携した記事の自動リライト提案や、キーワード選定の自動化、過去記事の改善候補提示など、データドリブンで運営効率を高める施策も今後スタンダードになるでしょう。
ただし、AIはあくまで支援ツールであり、ブランドストーリーや顧客体験に寄り添うコンテンツには、人間の感性や編集目が不可欠です。
AIを活用しながら、人のクリエイティブで磨き上げるバランスが、今後より重要になります。
コマースメディアの進化
オウンドメディアとECサイトの垣根がなくなり、記事から直接商品購入ができるようなUI/UX設計が加速しています。
ShopifyやSTUDIOなどのCMSでもメディア機能とEC機能を一体化できる環境が整っており、「読む→共感する→買う」をひとつの体験として設計することが、EC事業者の勝ち筋になるでしょう。
さらに、ライブコマースやSNS動画、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を連動させ、メディア内で商品の使い方やレビューを動画で見せ、その場で購入させる仕組みも増えています。
ECサイト単体では作りきれない生活者の視点に立った情報と購買体験の融合が、これからのオウンドメディアには求められます。
ファンコミュニティとの融合
近年、オウンドメディアの進化系として、ファンコミュニティとの融合も進んでいます。
単に情報を一方的に届けるだけでなく、顧客参加型企画やコミュニティイベント、ユーザー同士の交流コンテンツなど、“共創型メディア”への進化がブランドのLTV最大化につながります。
たとえば、メディア記事のコメント欄やSNS連携だけでなく、会員限定コミュニティ、顧客モニター企画、ユーザー参加型コンテンツなど、生活者を巻き込む設計が当たり前になりつつあります。
顧客との距離を縮め、ファンを育てることが、今後のECにおけるメディア戦略の鍵になるでしょう。
まとめ
EC事業において、オウンドメディアは今や必須のマーケティングチャネルのひとつになっています。
広告やSNSだけに依存しない独自の情報発信基盤として、中長期的な集客の安定化、ブランド認知の強化、LTV最大化に寄与できる点が大きなメリットです。
また、オウンドメディアは短期的な成果だけを求めるのではなく、ユーザーとの接点を積み重ね、関係を深化させるための中長期投資型施策として取り組むことが求められます。
本記事で紹介した通り、明確な目的設定とKPI設計、ユーザー理解を前提としたコンテンツ設計、適切な運用体制の構築、そして継続的な改善が、成果につながるポイントになります。
まずは小規模なテーマやターゲットからスタートし、PDCAを繰り返しながら、自社に最適なメディアの形を見つけていくことが現実的なアプローチと言えるでしょう。
※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比
※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月