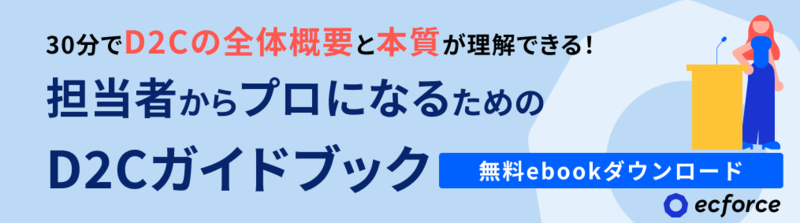この記事でわかること
※この記事は 時点の情報をもとに執筆しています。
EC事業を運営する上で、商品の適切な管理と効率的な出荷は非常に重要です。
そこで注目されているのがWMS(倉庫管理システム)です。
WMSは、倉庫内の様々な業務を管理し、EC物流の課題解決に貢献するシステムです。
本記事では、WMSの基本的な定義から主要な機能、導入によって得られるメリット、そして選ぶ際のポイントまで詳しく解説します。
関連するテーマについては、下記の記事もぜひチェックしてみてください。
今さら聞けないEC倉庫(EC物流倉庫)とは?メリットや特徴・費用・選び方まで完全網羅
OMS(注文管理システム)とは?機能・メリット・選び方をわかりやすく解説

WMS(倉庫管理システム)とは?
WMS(Warehouse Management System)とは、倉庫管理システムのことを指す用語です。
これは、倉庫内で行われる入荷、保管、ピッキング、出荷、棚卸といった一連の作業を効率的に管理するためのシステムです。
WMSを導入することで、倉庫業務の精度向上、効率化、そしてコスト削減を目指すことができます。
EC事業においては、多様な商品の少量多品種管理や、リアルタイムでの正確な在庫把握にWMSが役立ちます。
WMSの定義と基本的な役割
WMSの定義は、倉庫や物流センターにおける入出荷、在庫、棚卸といった一連の業務をデータに基づいて管理し、倉庫内の業務を効率化・標準化するシステムです。
その基本的な役割は、倉庫内の「物と人の流れを最適化する」ことにあります。
WMSは、商品の保管場所や数量、状態などを正確に把握し、必要な情報をリアルタイムで「見える化」することで、入出庫作業やピッキング、棚卸などの基本機能を効率的に実行できるようにサポートします。
また、バーコードやハンディターミナルなどのツールと連携し、作業の精度を高めることも重要な役割の一つです。
WMSが注目される背景
WMSが近年注目されている背景には、EC市場の急速な拡大があります。
消費者ニーズの多様化により、多品種小ロットでの出荷や迅速な配送が求められるようになり、従来の属人的な管理方法では対応が困難になってきています。
また、物流業界全体で人手不足が深刻化していることも、業務効率化や省力化を実現するWMSへの関心を高める要因となっています。
さらに、新型コロナウイルスの影響によるEC利用の増加は、物流現場の課題をより一層顕在化させました。
こうした状況下で、倉庫業務の正確性と効率性を高め、変化する需要に柔軟に対応できるWMSの必要性が高まっているのです。
EC物流業務に共通する特徴
EC物流は、企業間(BtoB)の物流とは異なり、主に個人消費者向けの取引であるBtoC物流が中心です。
特徴としては配送先が多く、一度あたりの物量は少ない「多頻度小口配送」となる点が挙げられます。
また、顧客ごとに異なる配送時間や料金への対応、ギフトラッピングなどの個別対応が求められることもEC物流の大きな特徴と言えます。
これらの特徴が、おもにEC物流における複雑さや課題を生み出す要因となっています。
リアルタイム在庫管理
EC物流では、24時間365日注文が発生するため、在庫情報を常に最新の状態に保つリアルタイム在庫管理が不可欠です。
在庫情報の反映が遅れると、在庫切れにも関わらず注文を受けてしまい、顧客からのクレームにつながる可能性があります。
リアルタイムでの正確な在庫把握は、販売機会の損失を防ぎ、顧客満足度を高める上で非常に重要です。
WMSを導入することで、入出庫の度に在庫情報がシステムに反映され、リアルタイムでの正確な在庫状況の把握が可能となります。
少量多品種に対応
EC物流では、一度の注文で様々な種類の商品が少量ずつ購入されるため、少量多品種の出荷が多いことが特徴です。
これにより、SKU(Stock Keeping Unit:在庫管理の最小単位)が細分化され、在庫管理が複雑になります。
例えば、同じ商品でも色やサイズ、デザインなどの細かい違いによってSKUが増加し、正確な管理が求められます。
この多品種少量での管理は、ピッキングや梱包作業を複雑化させ、人的ミスが発生しやすいという課題があります。
個別対応力
EC物流では、購入者一人ひとりに合わせた柔軟な個別対応が求められるケースが多く存在します。
例えば、ギフトラッピングやメッセージカードの添付、購入履歴に応じたサンプルの同梱など、顧客満足度を高めるための様々なカスタマイズが発生します。
これらの個別対応は作業をより複雑にし、確認不足や入れ間違いといった人的ミスのリスクを高める要因となります。
WMSの中には、同梱物管理機能など、こうした個別のニーズに対応するための機能を備えたシステムもあります。
このような機能を活用することで、個別対応によるミスの削減と効率化を目指すことが可能です。
WMSの主要な機能
WMSには、倉庫内の様々な業務を効率化するための多岐にわたる基本機能が搭載されています。
本セクションでは、そうした機能の概要を項目ごとに紹介します。
入荷に関する機能
WMSの基本機能の一つが入荷管理です。
入荷予定の事前登録、入荷商品の検品、指定保管場所への格納といった一連の作業を効率化する機能が含まれています。
ハンディターミナルなどを使って商品をスキャンすることで、システムに正確な情報を登録でき、発注データとの照合もスムーズに行えます。
これにより、入荷時の人的ミスを防ぎ、その後の在庫管理や出荷作業の精度向上につながります。
在庫と保管に関する機能
在庫と保管に関する機能も、WMSの基本機能です。
WMSでは、倉庫内のどこに何が、いくつあるのかをリアルタイムで管理できます。ロケーション管理機能により、商品の保管場所を明確にし、ピッキング効率の向上を実現します。
さらに、商品の入庫日や製造年月日、消費期限、ロット番号などの詳細な情報も管理できるため、適切な在庫引き当てや商品の回転を促進し、廃棄ロスの削減にも貢献します。
出荷に関する機能
出荷に関する機能も、WMSの主要な基本機能です。
WMSでは受注情報に基づき、適切な在庫を引き当て、効率的なピッキングリストを作成し、作業者はリストに従い商品を収集し、検品・梱包を行います。
これら一連の出荷プロセスをシステム上で管理し、誤出荷や遅延を防止。
さらに、納品書や送り状といった帳票の発行にも対応し、出荷関連の事務作業を効率化します。
また、複数の荷主の商品を扱う倉庫では、荷主ごとの管理機能も欠かせません。
適切な機能を備えたWMSを導入することで、出荷業務の品質向上と効率化が期待できます。
棚卸に関する機能
WMSの基本機能には、棚卸作業を効率化する機能も含まれます。
定期的に実施する棚卸は、実在庫とシステム上の在庫との差異を確認するために欠かせないものですが、手作業では多くの時間と労力を要します。
WMSを活用すれば、ハンディターミナルなどで商品のバーコードをスキャンするだけで、棚卸データを効率的に収集可能です。
さらに、システムが差異を自動で計算し、棚卸報告書を作成する機能も備わっているため、棚卸業務にかかる負担を大幅に軽減できます。
倉庫業務全体を最適化する機能
WMSには、上記以外にもさまざまな基本機能があります。
たとえば、返品された商品の管理を行う返品管理機能や、倉庫内の作業員の配置・作業時間の管理、KPI分析など、ヒトに関する管理機能を備えたシステムもあります。
さらに、帳票・ラベル発行機能では、納品書や送り状だけでなく、商品ラベルや荷札の発行も容易に行えます。
これらの基本機能を活用することで、倉庫業務全体の可視化と最適化を進めることが可能です。
WMSと関連システムの違い
WMS以外にも、物流や企業の業務をサポートする様々なシステムがあります。
これらのシステムはそれぞれ異なる役割を持っており、WMSと連携することでより効果的な物流管理が実現できます。
ここでは、WMSと混同されやすい関連システムとの違いや連携について、用語を交えながら解説します。
在庫管理システム
WMSと混同されやすいシステムに在庫管理システム(Inventory Management System:IMS)がありますが、これらは管理の対象と目的に違いがあります。
在庫管理システムは、企業全体の在庫データを管理することを目的としており、倉庫内の在庫だけでなく、店舗や工場など複数の拠点の在庫を一元的に把握します。
これに対し、WMSは倉庫内の業務に特化し、商品の入出荷や保管場所といった、より詳細な現場の在庫状況を管理します。
基幹システム
基幹システム(ERP:Enterprise Resources Planning)は、企業の経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を統合的に管理するシステムです。
販売管理、財務会計、人事など、企業活動の根幹に関わる情報を幅広く扱います。
WMSが倉庫内の物流業務に特化しているのに対し、ERPは企業全体の活動を管理対象としています。
ERPシステムの中には在庫管理機能を備えるものもありますが、倉庫現場の詳細なオペレーション管理にはWMSが適しています。
WMSと基幹システムを連携させることで、在庫情報と販売情報などを統合的に管理でき、より精度の高い経営判断が可能になります。
TMS(輸配送管理システム)
TMS(Transportation Management System)は、輸配送管理システムのことを指し、商品の「倉庫から出荷された後」の物流、つまり配送に関わる業務を管理するシステムです。
具体的には、最適な輸送手段の選定、配送料金の計算、配送状況の追跡などを行います。
WMSが倉庫内の業務を管理するのに対し、TMSは倉庫から先の輸送プロセスを対象としています。
WMSとTMSを連携させることで、商品の出荷から配送までの一連の流れをスムーズに管理でき、物流全体の効率化が期待できます。
OMS(受注管理システム)
OMS(Order Management System)は、受注管理システムのことを指し、ECサイトなどで発生した顧客からの注文情報を一元管理するシステムです。
注文受付、入金確認、在庫の引き当て、出荷指示といったバックエンド業務を効率化します。
WMSは、OMSから送られた出荷指示に基づき、倉庫内で作業を進行し、OMSとWMSを連携させることで、受注から出荷までのプロセスを自動化・効率化でき、注文処理のスピード向上や誤出荷の削減にもつながります。

WMSの導入で得られるメリット
WMSを導入することで、EC事業者は倉庫業務において大きな成果を得られます。
特に、業務効率の向上、コスト削減、顧客満足度の向上といったメリットは、ECビジネスの成長に直結する重要な要素です。
次のセクションでは、WMS導入がもたらすこれらのメリットについて詳しく解説していきます。
業務効率と生産性の向上
WMSを導入することで、倉庫業務の効率と生産性を大きく高めることができます。
システムによる最適なピッキングルートの指示や、入荷・出荷作業の自動化によって、作業時間を大幅に短縮。
さらに、リアルタイムで在庫情報や作業進捗を把握できるため、無駄な動きを減らし、業務全体の流れをスムーズにします。
限られた人員でも多くの業務をこなせる環境を整えられる点も、大きなメリットです。
人的ミスの削減
手作業や紙ベースでの管理に比べ、WMSを導入することで人的ミスを大幅に削減できます。
入出荷時の検品は、作業指示に従ってバーコードをスキャンする方式により、商品の数量や種類の誤りを防止し、正確なロケーション管理によって、誤った商品をピッキングするリスクも低減します。
ミスが減れば、再発送にかかる手間やコスト、顧客からのクレームも抑えられ、業務全体の負担軽減につながります。
リアルタイムな情報把握
WMSを導入することで、倉庫内の情報をリアルタイムで把握できるようになります。
在庫数や商品の保管場所、入出荷の進捗などが常に最新の状態でシステムに反映され、迅速な意思決定や柔軟な対応が可能に。
これにより、欠品による販売機会の損失を防ぎ、急な注文にもスムーズに対応できる体制が整います。
また、リアルタイムの情報は、現場以外の担当者でも離れた場所から倉庫の状況を把握できるため、管理業務の効率化にも貢献します。
コストの抑制
WMSの導入は、さまざまなコスト削減にもつながります。
業務効率の向上により、残業代などの人件費を抑制し、正確な在庫管理によって過剰在庫のリスクが減ることで、保管コストや廃棄ロスも削減できます。
さらに、誤出荷の防止は返品にかかる送料や対応コストの削減にも直結。
これらのコスト削減効果が、EC事業の収益性向上を後押しします。
作業の標準化
WMSを導入すれば、倉庫内の作業も標準化できます。
システムが作業手順を指示するため、経験の浅いスタッフでも迷わず正確に作業を進められます。
これにより、特定のベテランスタッフに業務が集中する属人化を防ぎ、誰でも一定の作業品質を維持できる環境が整います。
作業の標準化は、新人スタッフの教育にかかる工数削減や、人員配置の柔軟性向上にもつながります。
導入の際の注意点
WMSの導入は多くのメリットをもたらしますが、注意すべきポイントも存在します。
特に、既存システムとの連携やコスト面、運用体制の構築は、スムーズな導入と安定した運用に直結する重要な課題です。
これらの要素を事前に把握し、他システムとの比較を行いながら慎重に検討を進めることが、効果的なWMS活用への近道となります。
次のセクションでは、導入前に押さえておきたいポイントについて詳しく解説していきます。
導入に伴う費用と手間
WMSの導入には、システム費用だけでなく、初期設定やスタッフの教育にかかる手間とコストが発生します。
導入形態(クラウド型、オンプレミス型など)やシステムの種類によって費用は大きく異なります。
自社の予算や必要な機能を考慮し、複数のシステムを比較検討することが重要です。
また、新しいシステムに慣れるまでの期間は、一時的に業務効率が低下する可能性も考慮に入れる必要があります。
既存システムとの連携
既にECサイトの受注管理システム(OMS)や基幹システムなどを利用している場合、WMSとの連携が可能かどうかの確認は非常に重要です。
システム間の連携がスムーズに行われないと、データの二重入力や情報の分断が発生し、かえって業務効率が悪化する可能性があります。
導入前に、API連携やCSVでのデータ連携など、どのような連携方法が可能か、既存システムとの互換性があるかを必ず確認しましょう。
運用体制の構築
WMSを効果的に運用するためには、適切な運用体制の構築が不可欠です。
システムを操作する担当者の教育や、トラブル発生時のサポート体制、そして定期的なシステムのメンテナンスや改善計画など、導入後の運用についてもしっかりと計画を立てる必要があります。
現場の意見を聞きながら、実際にシステムを使うスタッフがスムーズに業務を行えるような体制を整えることが成功の鍵となります。
WMSの導入は倉庫内業務の効率化に直結しますが、EC物流全体の最適化には、倉庫選びそのものも重要な要素となります。
以下の記事では、在庫管理の効率化や出荷精度向上といった観点から、EC事業に最適な倉庫の選び方について詳しく解説されているので、ぜひこちらもお読みください。
自社に適したWMSを選ぶには
数多く存在するWMSの中から、自社に適したシステムを選ぶことは、導入効果を最大化するために欠かせません。
自社の規模や業種、抱える課題によって最適なWMSは異なります。
複数のシステムを比較検討し、後悔のない選択をすることが重要です。
ここでは、WMSを選定する際に押さえておきたい比較ポイントをご紹介します。
導入形態で比較する
WMSの導入形態には、主にクラウド型、パッケージ型、オンプレミス型の3種類があります。
クラウド型はインターネット経由で利用し、比較的初期費用を抑えながら、短期間での導入が可能です。
パッケージ型は既存のソフトウェアをベースに一部カスタマイズでき、導入しやすさと柔軟性を兼ね備えています。
オンプレミス型は自社サーバーにシステムを構築するため、高いカスタマイズ性とセキュリティを実現できる一方、初期コストや運用負担が大きくなります。
自社のIT体制や予算、求めるカスタマイズ性を踏まえて、最適な導入形態を比較検討しましょう。
必要な機能を確認する
WMSを選ぶ上で最も重要なポイントの一つが、自社業務に必要な機能が備わっているかの確認です。
標準搭載されている機能はシステムによって異なり、業種特化型の機能が求められる場合もあります。
たとえば、食品業界であれば賞味期限管理、アパレル業界であればカラーやサイズ別の在庫管理が重要です。
自社の倉庫業務フローを細かく洗い出し、必要な機能を明確にした上で、各システムの機能を比較検討しましょう。
外部システムとの連携を確認する
既存のOMSや基幹システム、ECカートシステムなど、外部システムとの連携可否も重要な比較ポイントです。
スムーズなデータ連携が実現できれば、情報の正確性が高まり、業務効率の向上に繋がります。
API連携やCSV連携など、対応する連携方式を事前に確認しておきましょう。
特にリアルタイムでの情報連携が必要な場合は、連携方式の対応範囲をしっかり比較することが大切です。
サポート体制を確認する
WMS導入後の運用においては、提供会社のサポート体制も欠かせません。
操作方法に関する問い合わせ対応や、トラブル発生時の迅速なサポートが受けられるかを確認しましょう。
対応時間やサポート手段(電話・メール・チャットなど)、FAQやマニュアルの充実度なども比較検討することをおすすめします。
特に24時間365日稼働するEC物流を想定する場合、休日や夜間のサポート体制も必ずチェックしておきましょう。
操作性を確認する
システムを実際に利用する現場スタッフにとって、操作性は非常に重要なポイントです。
どれだけ機能が優れていても、操作が難しければ定着せず、導入効果も得にくくなります。
直感的でわかりやすいインターフェースかどうか、ハンディターミナルなどのデバイス連携がスムーズかなどを確認しましょう。
可能であればデモ版やトライアル期間を活用し、現場スタッフ複数人で操作性を実際に試すことをおすすめします。
費用を確認する
WMSの導入費用や月額利用料は、システムの種類や提供形態、利用機能によって大きく異なります。
初期費用だけでなく、ランニングコストも含めた総費用を把握し、自社の予算と比較することが重要です。
オプション機能の追加費用や、ユーザー数に応じた課金体系も確認しておきましょう。
複数のシステムを比較検討し、費用対効果に優れたWMSを選ぶことが求められます。
WMSの市場動向
WMS(倉庫管理システム)市場は、eコマースの急速な拡大や物流業務の効率化ニーズの高まりを背景に、近年著しい成長を遂げています。
さらに、AIなどの先端技術の進化が市場の拡大を後押ししており、今後もWMSの高度化と普及が進むと予想されています。
市場規模と成長率
世界のWMS市場は、2023年に約36億5,000万米ドルと評価され、2032年には131億4,000万米ドルに達すると予測されています。
(引用元:Straits Research「倉庫管理システム市場規模、シェア、2032年までの予測」)
この成長は、ECの普及、効率的なロジスティクスへの需要増加、そして人工知能(AI)やIoTといった技術の進歩に牽引されています。
最新技術の活用
WMS市場では、最新技術の導入が進んでいます。
AIを活用した需要予測や最適なロケーション管理、ロボティクスとの連携による自動化など、より高度な機能がWMSに搭載されるようになっています。
また、クラウドベースのWMSの普及も進み、中小企業でも比較的容易にWMSを導入できる環境が整っています。
今後は、IoTデバイスによるリアルタイムデータの収集・分析や、ブロックチェーン技術を活用したトレーサビリティの強化など、さらなる技術革新が進み、市場の成長を加速させると見込まれています。
(引用元:Mordor Intelligence「倉庫管理システム(WMS)市場規模・シェア分析」)
まとめ
WMS(倉庫管理システム)は、EC物流の複雑な業務を効率化し、精度を高めるために欠かせない存在です。
リアルタイム在庫管理、作業の標準化、コスト削減など、WMS導入によって得られるメリットは多岐にわたります。
特に、多品種少量出荷や個別対応といったEC特有の課題に対して、WMSは有効なソリューションとなるでしょう。
システム選定にあたっては、自社の業務フローに適した機能や導入形態、外部システムとの連携可否、操作性、サポート体制、費用といったポイントをしっかり比較検討することが重要です。
物流の効率化は、EC事業の成長を支える大きな鍵となります。
最適なWMSを導入し、より強い物流基盤を築いていきましょう。
※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比
※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月