この記事でわかること
ECサイト構築とは、インターネット上で商品やサービスを販売するWebサイト(オンラインショップ)を企画・制作・運用するプロセスを指します。
単なるWebサイト制作ではなく、商品登録やカート機能、決済、配送管理、会員システム、マーケティング支援機能など、販売運用に必要な機能を備えた仕組みの整備が求められます。
2025年現在、EC構築は「より手軽に」「より柔軟に」「よりデータドリブンに」進化を遂げています。SaaS型のサービスが広く普及し、ノーコードでのスピーディな立ち上げが可能になり、生成AIを活用した商品説明文の自動生成やAIチャットボットによる顧客対応など、運用の自動化・省力化も進んでいます。
一方で、選択する構築方法やプラットフォームによって、費用・自由度・拡張性に大きな差が生まれるのも事実です。商材や運用体制、目指すブランド像に合わない選択をしてしまうと、期待した効果を得られず、コストや時間ばかりがかかってしまうこともあります。
本記事では、EC構築に関する基礎知識からシステム別の特徴・費用感、構築手順、最新トレンドに至るまで、これからECを始めたい方・見直したい方に向けて徹底的に解説します。
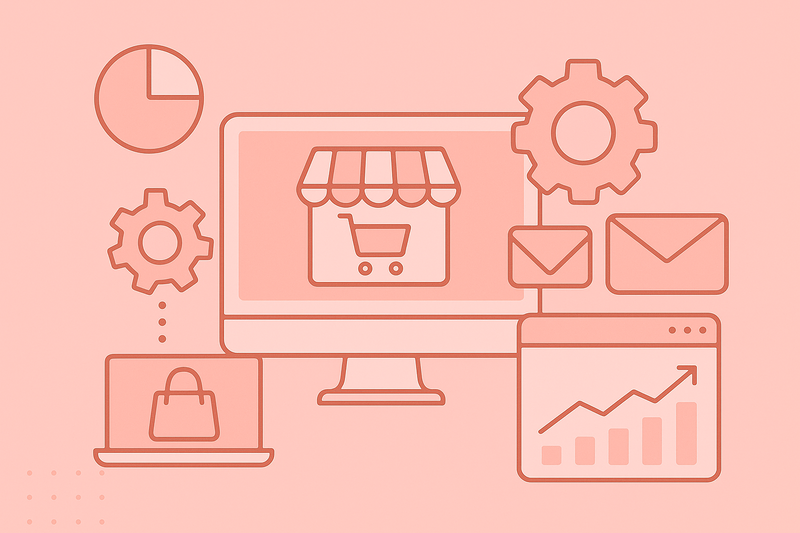
ECサイトとは?2つの代表的な形態
ECサイトは、インターネットを通じて商品やサービスを販売するWebサイトのことです。Amazonや楽天市場などの巨大なマーケットプレイス型プラットフォームもあれば、自社で運営するブランドECサイトも含まれます。
代表的なECサイトの形態は、以下の2つです。
モール型(マーケットプレイス型)
例:楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon
- プラットフォームが提供するモールに出店する形式
- 初期コストが低く、集客力が高い
- 一方で、販売手数料が発生し、デザインや機能の自由度は限定される
自社ECサイト型
例:Shopifyやecforce等を使った自社ドメインのブランドサイトなど
- 自社で構築・運営するスタイル
- デザインや機能のカスタマイズが可能で、顧客データの蓄積やCRMが行いやすい
- 集客は広告やSEOなどを自前で行う必要がある
多くの企業は、モール型で集客と売上のスピードを担保しつつ、自社ECで利益率とブランドを伸ばすというハイブリッド運用を行っています。
EC構築を始める前に押さえておきたい、7つの基本ステップ
EC構築は、ただシステムを選んでサイトを作るだけではありません。計画から設計・制作・運用まで、フェーズごとにしっかりとした準備が必要です。
以下では、構築前〜運用までの全体像を3つのフェーズに分けてご紹介します。
【フェーズ1】計画設計編:準備がすべての成功を決める
販売商品・ターゲットの明確化
何を・誰に・どのように売るのかを明確にしましょう。ペルソナを具体化することで、サイトの構成・デザイン・訴求文にも一貫性が生まれます。
ショップ形態の選定(モール型 or 自社EC)
目指す方向性によって、選ぶべき形態は変わります。短期の売上や集客重視ならモール型、長期的なブランド価値やCRMを重視するなら自社ECが有効です。
構築方式・サービスの選定(SaaS・クラウド・パッケージなど)
開発リソース、予算、拡張性などを軸に、自社に合ったサービスを選びましょう。初期費用と運用負荷のバランスも重要です。
【フェーズ2】構築・設計編:サイトの設計と制作を行う
デザイン・UI/UX設計
スマホファーストで設計し、スムーズな購入体験を意識します。ブランドの世界観やビジュアルトーンもここで定義します。
機能設定・コンテンツ登録
商品登録、決済方法、配送設定、カテゴリ分類など、運用に必要な情報を整理・実装していきます。
テスト公開・本番リリース
テスト注文やエラーチェック、通知メールの確認などを行い、万全の状態で公開を迎えましょう。
【フェーズ3】運用・改善編:売れる仕組みを育てていく
集客・販促・改善運用
SNS運用、広告配信、SEO対策、CRM施策などを継続的に展開し、ユーザー行動の分析をもとにUIや導線を改善していきます。
ECサイト構築の主な方式と特徴
ECサイトを構築する方法は、大きく5種類に分類されます。
それぞれに初期費用、運用コスト、拡張性、対象規模が異なるため、自社に合った方式を選ぶことが成功への鍵となります。
1. SaaS型(クラウド型)
クラウド上のECサービスを契約し、必要な機能を備えたECサイトを構築する方式です。
- メリット:初期費用が低く、スピーディに構築できる。テンプレートや管理機能が整っており、ノーコードでも運用可能。
- デメリット:自由度は限定的で、大規模カスタマイズや独自仕様には不向きな場合も。
2. オープンソース型
ソースコードが公開されているプラットフォームをベースに、自社で自由に開発・構築する形式です。
- メリット:自由なカスタマイズが可能で、独自の運用要件に柔軟に対応できる。
- デメリット:開発リソースが必要で、保守運用も自社(または外部開発会社)で行う必要がある。
3. パッケージ型
業務要件に合わせた高機能なパッケージを導入し、自社仕様にカスタマイズして使うタイプです。BtoBや大規模企業に向いています。
- メリット:EC運営に必要な機能が網羅されており、導入後のサポートやアップデート体制も整っている。
- デメリット:初期導入費用が高く、柔軟なカスタマイズには時間と費用がかかる。
4. クラウド型(PaaS型)
カスタマイズ性と拡張性を兼ね備えたクラウド型ECサービスです。自社要件に合わせて柔軟に構成でき、長期運用にも強いのが特徴です。
- メリット:スケーラビリティが高く、中〜大規模ECに向いている。SaaS型より自由度が高い。
- デメリット:一定の技術理解と導入・運用設計力が必要。費用はSaaS型よりやや高め。
5. フルスクラッチ開発
ゼロから独自に設計・開発する方式で、特定の業種・大企業・官公庁などが採用することが多いです。
- メリット:業務に完全に最適化されたECサイトが構築できる。競合にない独自性を発揮できる。
- デメリット:開発・運用コストが非常に高く、構築期間も長期化しやすい。継続運用にも高いスキルと体制が求められる。
EC構築方式別 比較表
※掲載している金額は目安です。実際の構築費用は規模や機能、運用体制によって変動する場合があります。
| 構築方式 | 初期費用 | 月額費用 | カスタマイズ性 | 対象規模 |
|---|---|---|---|---|
| SaaS型(クラウド型) | 0円〜10万円前後 | 3,000円〜数万円程度 | △ | 個人〜中規模 |
| オープンソース型 | 10万〜200万円程度 | 保守費別途 | ◎ | 中〜大規模 |
| パッケージ型 | 100万〜500万円以上 | 10万〜50万円/月 | ◎ | 中〜大企業 |
| クラウド型(PaaS型) | 50万〜200万円前後 | 5万〜20万円/月 | ◯ | 中堅〜成長企業 |
| フルスクラッチ型 | 500万円〜数千万円以上 | 要相談 | ◎ | 大規模・特化型 |
EC構築前にやるべき準備と戦略立案
EC構築を始める前には、サイト制作の前提となる「誰に・何を・どう売るのか」を明確にする必要があります。
これらの戦略的準備を丁寧に行うことで、後の構築や運用に一貫性と成果をもたらします。
ペルソナ・ターゲット設計
顧客像が曖昧なままサイトを構築すると、導線設計や訴求のズレが起きやすくなります。年齢・性別・悩み・購買行動・使用デバイス・SNS利用傾向など、具体的なペルソナを設定し、その人に最も響く構成を設計しましょう。
競合調査と差別化軸の明確化
自社ECの強みを明確にするためには、競合リサーチが欠かせません。
- 類似商材の価格帯・デザイン
- 商品説明の見せ方
- カート導線やレビュー機能
- リピート施策や送料設計
上記のような観点で競合を分析し、「自社ならではの価値(価格・利便性・世界観など)」を言語化しましょう。
KPI・KGIの設計
ECサイトは公開して終わりではありません。数字を軸に継続的な改善が求められます。月商やCVR、LTV、離脱率など、フェーズに応じて見るべき数値を明確にし、具体的なKPIを設定しましょう。
UI/UX設計とデザインの最適化
ユーザーに「買いやすい」「探しやすい」と感じてもらう体験設計(UX)は、ECサイトの成果に直結します。スマホユーザーが大半を占める今、特にスマホファーストの設計が重要です。
UIで意識すべきポイント
- 商品検索・カテゴリ導線の整理
- 商品画像のクオリティと枚数
- カートボタンの視認性
- ユーザーレビューやFAQの表示位置
- 会員登録・購入フローのシンプル化
上記のようにストレスなく買える体験が顧客のリピートにつながります。
デザインの注意点
- ブランドカラー・トーンの統一
- サイト内のビジュアルルール(写真、余白、フォントなど)
- 視認性と感情訴求のバランス
見た目のおしゃれさだけでなく、情報を瞬時に理解できるかも重視しましょう。
集客チャネルとCRM施策の展開
EC運用の中でも、集客とリピーター育成は成長に欠かせない2大テーマです。初動の流入を増やし、継続購入につなげる導線を整えていきましょう。
主な集客チャネル
- SEO/コンテンツマーケティング(記事・ブログ・Q&Aページ)
- SNS(Instagram、X、TikTokなど)
- リスティング広告・SNS広告
- LINE公式アカウント/メルマガ
- インフルエンサー・UGC活用
特にLINEやSNSはブランドとの距離感が近くなる接点として有効です。
LTVを高めるCRM施策
- 会員登録によるデータ収集
- 購入履歴に応じたリコメンド配信
- バースデークーポンや限定オファー
- セグメント別キャンペーンの自動化
顧客ごとのニーズやタイミングに応じた接点を増やすことで、LTVを最大化できます。
【2025年】EC構築で押さえるべきトレンド5選
テクノロジーの進化や消費者行動の変化により、EC構築のあり方も年々アップデートされています。2025年現在、注目すべきトレンドは以下の5つです。
1. 生成AIの業務活用
- 商品説明文の自動生成
- カスタマーサポートのチャットボット化
- バナーやSNS投稿素材の画像生成
工数削減とパーソナライズの両立が可能になります。
2. ノーコード構築の普及
開発知識がなくても、テンプレやアプリ拡張を使って本格的なECサイトを構築できる環境が整っています。これにより、担当者ベースでの素早い検証・改善が可能になります。
3. LINE連携によるCRM強化
LINE公式アカウントとECを連携し、セグメント配信やカゴ落ちリマインド、リピート訴求などを自動化する事例が増えています。
メールより開封率・反応率が高いため、販促チャネルとして重要性が増しています。
4. サードパーティCookie廃止と集客戦略の転換
Cookie規制により、従来のリターゲティング広告が機能しづらくなっています。
そのため、ファーストパーティデータの活用や、SNS・LINEなど自社管理できる接点での関係構築が求められます。
5. 実店舗とのOMO(Online Merges with Offline)連携
- 店舗で取得した会員情報をECへ活用
- 店舗受け取り(BOPIS)対応
- 店舗在庫連携による配送最適化
オンラインとオフラインを横断した購買体験がスタンダードになりつつあります。
ECサイト構築に関するよくある質問
Q1. ECサイト構築の初期費用はいくらくらいかかる?
構築方式によって大きく異なります。
SaaS型であれば無料〜数万円で始められるものもありますが、パッケージ型やフルスクラッチの場合は数百万円〜数千万円になることもあります。自社の事業フェーズや必要な機能に応じて、無理のない予算設計を行いましょう。
Q2. モール型と自社EC、どちらを選ぶべき?
短期的な集客力や市場のスピード感を重視するならモール型、長期的なLTVやブランディング、CRM活用を重視するなら自社ECがおすすめです。
最初はモールで実績を積み、自社ECに移行・併用するハイブリッド型も有効です。
Q3. サイト公開後は何から始めればいい?
まずは集客と改善のサイクルを回していくことが大切です。アクセス解析を行い、離脱率やカゴ落ちポイントを洗い出して改善を進めましょう。
並行してSNSや広告、LINE配信などで流入を強化していくのがセオリーです。
おすすめのEC構築サービスの選び方
ECサイト構築サービスは、提供形態や機能の柔軟性、サポート体制などによって大きく異なります。ここでは、それぞれのカテゴリごとの特徴を紹介します。
自社のフェーズや目的に合わせて、最適なタイプを選ぶ参考にしてください。
SaaS型(クラウド型)
- 初期費用を抑えて、スピーディにECを立ち上げたい企業向け
- テンプレートやアプリ連携などの拡張機能が豊富で、ノーコードでも運用が可能
- デザインや機能の自由度には一部制約があるが、運用のしやすさに優れる
パッケージ型
- 大規模ECやBtoB、独自業務に合わせたシステム構成を求める企業向け
- 導入時の要件整理〜開発〜運用まで、専任チームやパートナーと連携して進めるケースが多い
- 初期費用は高額になりやすいが、安定稼働・長期利用を前提とした設計に強みがある
クラウド型(PaaS型)
- 柔軟なカスタマイズと長期的なスケーラビリティを両立したい中堅〜成長フェーズの企業向け
- SaaSの手軽さと、パッケージに近い自由度を兼ね備えており、自社の要件に合わせたEC基盤を構築可能
- 月額費用はやや高めだが、事業拡大を見据えた選択肢として注目されている
オープンソース型
- 社内にエンジニアリソースがあり、独自開発や完全カスタムを前提とした構築を行いたい企業向け
- ソースコードが公開されているため、自由度が高く、外部開発会社と連携するケースも多い
- 保守・運用の負担や、セキュリティ対策も自社責任となる点には注意が必要
フルスクラッチ型
- 完全オリジナルな要件・ビジネスモデルに基づくECを構築したい大規模・特化型企業向け
- 要件定義からUI/UX、インフラ構成、運用フローまで全てを一から設計
- コスト・開発期間ともに大きくなるが、競合にない独自性や自社業務との完全連携が可能
選定時のチェックポイント
EC構築サービスを選ぶ際には、以下のような観点を総合的に考慮することが重要です。
単に「安い」「高機能」といった表面的な要素だけでなく、自社の戦略や運用体制とフィットするかどうかを見極めましょう。
- 事業規模と予算感のバランス
小規模事業であれば初期投資を抑えたSaaS型、大規模事業であれば長期視点の構築方式が選ばれやすくなります。 - 将来的な拡張性・柔軟性
今すぐ必要な機能だけでなく、今後の事業拡大に備えて柔軟に拡張できる構成かを確認しましょう。 - 社内の開発リソース・技術体制
自社で開発や保守ができるか、あるいはベンダーに依存する運用になるかによって、適切な方式は異なります。 - 既存システムとの連携可否
会計・在庫・CRM・POSなど、既存業務システムとの接続が必要な場合、柔軟な連携性が求められます。 - 顧客体験とブランディングの自由度
UI/UXやデザイン表現にこだわりたい場合は、自由度の高い構築方式を選ぶと理想に近づけやすくなります。 - 運用サポートや導入後の支援体制
専任担当による伴走支援、マニュアル整備、サポート窓口などの体制も、継続的な運用に大きく関わります。
ECサイト構築を成功させるために
ECサイト構築を成功に導くためには、単にシステムやサービスを選定するだけでなく、構築前の戦略設計から運用体制の構築、そして継続的な改善までを一貫して設計することが求められます。
特に重要なのは、自社の事業フェーズや商材特性、社内リソースとの整合性を踏まえて、最適な構築方式と運用体制を選択することです。初期投資の抑制にとらわれすぎると、拡張性や中長期的な収益性に課題が残るケースも見受けられます。
また、ECサイトは構築して終わりではありません。構築後の集客・CRM・UI改善といった運用フェーズにおいて、データドリブンな意思決定と継続的な改善サイクルを回せるかどうかが、成果を左右する大きな要素となります。
2025年現在、ノーコードツールや生成AI、LINE連携、クラウド型の柔軟なEC基盤など、選択肢は広がっています。しかしその一方で、ユーザーの期待値や市場の競争水準はこれまで以上に高まっているのが現実です。
変化の早いEC領域では、最初から完璧を目指すよりも、小さく始めてデータに基づいて改善を重ねる柔軟な姿勢が欠かせません。
自社のビジネスモデルに最適化された構築・運用体制を設計し、着実に成果へとつなげていきましょう。
※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比
※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月














