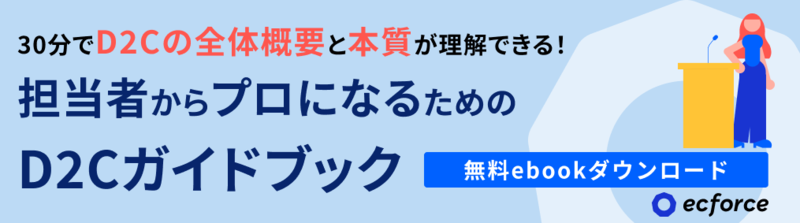この記事でわかること
※この記事は 時点の情報をもとに執筆しています。
越境ECは、国内市場が飽和する中で新たな販路として注目されているビジネスモデルです。
この記事では、越境ECの基本的な仕組みから、最新の市場動向、成功するための具体的なステップや成功事例をわかりやすく解説します。
「海外に商品を売ってみたいけれど、何から始めたらいいかわからない」──そんな悩みを持つ方に向けて、失敗しない始め方や、実際に成果を上げている事例もご紹介。
最後までお読みいただくことで、自社にとって最適な越境ECの取り組み方が明確になるはずです。
関連するテーマについては、下記の記事もぜひチェックしてみてください。
【2025年最新版】中国OEMとは?工場選び・始め方・リスク対策を完全ガイド
海外OEMを成功させるためには?手法や注意点を詳しく解説
越境ECとは?

越境ECとは、国境を越えて商品やサービスを売買する電子商取引のことです。たとえば、日本の企業がアメリカや中国など海外の消費者に商品を販売するケースなどがこれにあたります。
世界中の消費者をターゲットにできるため、国内市場の縮小に悩む企業にとっては大きなチャンスでもあります。
ここでは、越境ECの定義や特徴、主要なビジネスモデルについて詳しく見ていきましょう。
越境ECの定義
越境EC(Cross-Border E-Commerce)は、国境をまたいでオンライン上で商品やサービスを売買する取引全般を指します。
売り手と買い手が異なる国にいる場合に成立し、言語や通貨、法律、物流など多くの要素に対応する必要があります。
国内ECと比べて障壁が多い一方で、グローバルな需要を獲得できるポテンシャルを持つビジネスモデルです。
越境ECの特徴
越境ECには以下のような特徴があります。
- 世界中の消費者を相手にできるため、市場規模が圧倒的に広い
- 言語、決済方法、物流、法規制など、国ごとの対応が求められる
- ブランディングや文化的な違いへの配慮が必要
- 為替リスクや配送トラブルなど、特有のリスクも存在
このような特徴を理解し、適切に対処することが成功の鍵となります。
越境ECの代表的な5つのビジネスモデルと選び方
越境ECには、目的や体制に応じたさまざまな運営方法があります。
ここでは、特に導入事例が多く、実践的な5つのモデルについて詳しく解説します。それぞれの特徴を理解し、自社に合った運営スタイルを選びましょう。
自社ECサイト運営
自社で越境ECサイトを構築・運営する方法です。
自社ブランドの世界観を自由に表現でき、顧客データを直接収集・活用できるのが大きなメリットです。
一方で、多言語対応、海外決済の導入、物流オペレーションの構築など、全てを自社で整える必要があり、初期構築と運用に一定のリソースが求められます。
海外ECモール出店
Amazon、eBayなど、海外の大手ECモールに出店する方法です。
既に集客力があるプラットフォームを活用できるため、スタートしやすくスピーディーに販売を開始できます。
その反面、モール側のルールや手数料、同一カテゴリ内での競争が激しいため、価格・商品力・レビューなどの差別化が重要になります。
海外転送サービスの活用
転送サービスを活用することで、国内向けECサイトをそのまま使いながら、海外からの注文に対応できます。
購入者は転送会社の日本の住所を指定し、その後海外に商品が送られます。
初期構築の手間が少なく、導入しやすい方法ですが、送料や配送リスク、商品制限などの確認が必要です。
代行販売型(フルフィルメント型)
越境ECに必要な業務(商品登録、受注処理、カスタマー対応、配送など)を、すべて外部の代行業者に任せるスタイルです。
人的リソースが限られる企業にとっては効率的で、スピーディーな越境展開が可能です。
ただし、代行手数料やサービス範囲、ブランドコントロールの可否については事前の確認が必須です。
保税区の活用
中国などで多く利用されている「保税倉庫」を活用するモデルです。
保税区モデルでは、中国国内の保税区に商品を事前に輸送し、在庫として保管します。
消費者からの注文が確定した時点で、保税区から商品を出荷し、通関手続きを経て配送される仕組みです。
このモデルの最大の利点は、配送スピードの向上と物流コストの削減です。商品をあらかじめ中国国内に保管することで、注文から配送までのリードタイムを短縮でき、消費者満足度の向上につながります。
ただし、保税区モデルを採用するには、一定の販売量が見込まれることが前提となります。在庫リスクや保管コストを考慮し、慎重な計画が求められます。
詳細な情報や具体的な事例については、以下の参考記事をご覧ください。
出典:もう迷わない!!中国越境EC2つの物流モデルを徹底比較~保税区モデルと直送モデル~|ダイレクトチャイナ
越境ECのビジネスモデル比較表
| ビジネスモデル | メリット | デメリット | 向いている企業 |
|---|---|---|---|
| 自社ECサイト運営 | ブランド強化、顧客データ取得 | 初期費用・運用負担が大きい | ブランド重視の企業 |
| 海外ECモール出店 | 集客しやすく手軽に開始可能 | 手数料・競争が激しい | 低コストで始めたい企業 |
| 海外転送サービス活用 | 国内サイトを活用できる | 制限やトラブルのリスクあり | 手軽に試したい企業 |
| 代行販売型 | 全業務を外注できる | 手数料高め、自由度が低い | リソースが少ない企業 |
| 保税区活用型 | 通関が早く配送も迅速 | 在庫リスク・初期費用が必要 | 中国展開を目指す企業 |
越境ECと他の販売形態との違い
越境ECは海外市場へのアクセス手段として注目されていますが、実は他にも「海外店舗の出店」や「現地法人の設立」など複数の海外展開手法が存在します。
ここでは、越境ECと他の主要な形態を比較することで、それぞれの特性と導入のしやすさを明らかにし、自社にとって最適な選択肢を見極めるヒントを提供します。
国内ECとの比較
国内ECは、言語や通貨、法制度が統一された環境で運営できるため、越境ECに比べて構築・運営のハードルが低いというメリットがあります。
一方で、日本国内の市場は人口減少や競争激化により飽和状態にあることも事実です。
越境ECは、これに対して新しい市場を開拓できる手段となり、国内ではリーチできない層にアプローチできるのが大きな違いです。
実店舗の海外出店との比較
現地に実店舗を構える方法は、ブランド認知や体験価値の提供において非常に強力です。
ただし、物件取得、スタッフ採用、在庫管理、法務・税務手続きなど、多大なコストとリスクが伴います。
それに対し越境ECは、物理的な出店を必要とせず、比較的低リスク・低コストで始められるのが魅力です。
まずはECで市場反応を見た上で、実店舗展開に進むという段階的アプローチも有効です。
現地法人設立との比較
海外に法人を設立することは、本格的な海外事業展開の第一歩といえます。
現地での信用力向上や雇用、サプライチェーン構築など、多くの戦略的メリットがありますが、同時に高いコストと法的リスクを伴います。
越境ECは、こうした法人設立前のステップとして、事業検証や市場テストに適しています。
初期段階でのリスクを抑えつつ、現地ニーズを見極めるための手段として活用する企業も増えています。

越境ECのメリットとリスク
越境ECには、新たな市場への参入やブランドの国際化など多くの魅力がありますが、その一方で乗り越えるべきリスクも存在します。
このセクションでは、越境ECを導入することで得られる代表的なメリットと、企業が直面しやすいリスクの両面を整理し、事前に備えておくべきポイントを詳しく解説します。
越境ECのメリット
越境ECを導入することで、国内だけでは得られない多くの成長機会が広がります。
ここでは、企業にとって越境ECがどのような価値をもたらすのか、主なメリットを4つの観点から具体的に解説します。
世界中の顧客にアプローチできる
越境ECの最大の魅力は、国内市場に限らず、世界中の消費者へ商品を届けられる点です。
特に、日本製品は「高品質・信頼性の高さ」で評価されており、アジアを中心に根強い人気があります。
ニッチな商品でも、国外では大きな需要がある可能性があり、新たな収益源としての可能性が広がります。
低コストで海外展開が可能
実店舗や現地法人の設立と比較して、越境ECは遥かに少ない初期費用で始められます。
在庫管理や決済システムを工夫すれば、小規模からテスト運用を開始することも可能で、段階的な成長戦略にも適しています。
費用を抑えながらスピーディーに海外進出できる点は、特に中小企業にとって大きなメリットです。
ブランド価値の強化と認知拡大
日本製品への信頼感を活かし、海外市場で自社ブランドの認知を高めることができます。
レビューサイトやSNS、インフルエンサーマーケティングと連携することで、現地市場での影響力を高めやすく、ブランディング戦略の一環としても有効です。
日本製品への高い需要
日本製品は世界的に「品質が高く、信頼できる」という評価を得ており、越境ECにおいても強力なアドバンテージとなります。
特に化粧品、医薬品、家電、アニメ・ゲーム関連グッズ、ベビー用品、伝統工芸品など、ジャンルを問わず広く需要があります。
これらの製品カテゴリは既に「ジャパンブランド」として定着しており、海外市場での価格競争に巻き込まれにくい特徴もあります。
既存の商品やサービスがすでに高評価を得ている場合、越境ECはその魅力をより広範な市場に届けるための有効な手段となります。
越境ECのデメリットとリスク
越境ECは新たな市場を切り開く魅力的な手段である一方、国内ECにはないさまざまなハードルも存在します。
ここでは、運営上で特に注意すべき4つのリスクについて解説し、事前に備えておくべき課題を整理します。
高額になりがちな輸送コスト
越境ECで大きなネックとなるのが「国際配送費用」です。
配送距離が長くなるほど送料は高騰し、商品のサイズ・重量・緩衝材などによってコストに大きな差が出ます。
また、配送中の破損・紛失リスクを防ぐための保険料や再配送対応も含めると、利益を圧迫しかねません。
特に単価の低い商品を扱う場合は、送料が価格の大半を占めてしまうこともあるため、商品構成や価格設定の見直しが必要です。
「送料無料」の導入も、慎重な原価計算が求められます。
国や地域による対応の違い
販売対象国によって、関税、輸入制限、表示義務、返品ルール、消費税の仕組みなどが大きく異なります。
たとえば、ある国では食品や化粧品の成分表示が必須であったり、他国では医療機器の輸入が禁止されていたりと、対応の複雑さは想像以上です。
こうしたルール違反があると、商品が差し押さえられるリスクや罰金の対象になることもあります。
リスクを回避するには、各国の輸出入規制に関する事前調査や、通関業者・コンサルタントの活用が重要です。
顧客対応・セキュリティの課題
言語や文化の違いから生じるトラブルも多く、問い合わせ対応や返品処理は特に注意が必要です。
対応言語が限定されていると顧客満足度が低下し、クレームや悪評に繋がるリスクもあります。
また、クレジットカード不正利用や、虚偽の返金要求など、悪質な注文に対するセキュリティ対策も必要不可欠です。
こうしたトラブルを想定し、多言語カスタマーサポート体制やFAQ整備、不正注文検知ツールの導入など、地道な備えが信頼性を高めるカギとなります。
為替変動の影響
越境ECでは、現地通貨で売上を受け取るケースが多く、為替レートの変動によって利益額が変動します。
たとえば、円高が進行すると外貨で得た売上の円換算額が減少し、利益が目減りするリスクがあります。
逆に、円安であれば為替差益が得られる場合もありますが、それを前提とした経営は不安定です。
為替リスクを軽減するには、外貨建て口座を利用する、定期的に換金する、または収益の一部を為替ヘッジするなど、戦略的な資金管理が必要です。
越境EC市場の現状と予測
世界の越境EC市場は、ここ数年で急成長を遂げており、今後もその勢いは続くと見られています。
ここからは、越境ECの「市場規模」「地域別の動向」「日本製品の人気カテゴリ」に分けて、具体的なデータと傾向から今後のビジネスチャンスについて解説します。
世界の市場規模
世界全体の越境EC市場規模は、2024年に約3兆4,411億6,000万米ドルと評価されており、2033年には約20兆35億5,500万米ドルに達すると予測されています。
これは、2025年から2033年までの年平均成長率(CAGR)が21.6%であることを示しています。
出典:Market Data Forecast|「世界の越境電子商取引市場 」https://www.marketdataforecast.com/market-reports/cross-border-e-commerce-market
このような背景から、越境ECは今や一部の大手企業だけでなく、中小企業や個人ブランドにとっても参入しやすい成長分野となっています。
地域別の市場動向
越境EC市場の成長は地域によって傾向が異なり、それぞれの市場環境に応じた戦略が求められます。
ここでは、主要地域ごとの市場動向を紹介します。
アジア太平洋(APAC)
アジア太平洋地域は越境EC市場の中でも最も急速な成長を遂げているエリアであり、特に中国は世界最大級の市場を形成しています。
2024年には約3,969億米ドルの規模に達するとされ、今後も高い成長率が見込まれています。
また、インドネシアやタイ、ベトナムなど東南アジア諸国では、モバイルECの普及とともに海外製品への関心が急増しており、若年層を中心とした購買行動が活発化しています。
北米
北米地域は、購買力と物流インフラの充実を背景に、越境ECの受け入れが進んでいます。
特にアメリカでは、グローバルブランドの商品がオンラインで入手しやすくなっており、購買行動のボーダーレス化が顕著で、高い消費単価とリピート率の高さも特長です。
ヨーロッパ
ヨーロッパでは、ファッションやコスメなど感性商材における越境需要が大きく、越境ECがライフスタイルに定着しています。
EU加盟国間の規制統一や通貨統一(ユーロ)も、流通のしやすさを支える要因です。特にドイツ、フランス、イギリスなどは重点市場とされています。
中東・アフリカ(MEA)
中東・アフリカ地域は、今後の成長が期待される新興市場です。
都市部を中心にECインフラが整いつつあり、富裕層や若年層をターゲットとしたブランド戦略が奏功しています。
宗教や文化的な配慮を要する場面もありますが、参入企業は着実に増加しています。
本セクションのデータ出典
・Market.us|「世界の越境電子商取引市場の規模、シェア、統計分析レポート」
・Coherent Market Insights|「Cross Border E-Commerce Market」
日本製品の人気カテゴリ
越境ECにおいて、日本製品は数多くのカテゴリで高い人気を誇っています。
代表的なものを以下に紹介します。
- 化粧品・スキンケア用品:品質と安全性の評価が高く、アジア圏で特に支持されている
- アニメ・キャラクターグッズ:日本のポップカルチャーの代表格。熱心なファンが多く、リピーターも獲得しやすい
- 食品・お菓子・健康食品:日本食ブームやヘルス志向の流れから注目度が上昇中
- 電化製品・生活雑貨:技術力と使いやすさを重視する層に人気。レビューでの評価も影響大
- アパレル・ファッション雑貨:特に“クールジャパン”系のデザインや機能性が評価されやすい
これらのカテゴリは単価やリピート性も高いため、越境ECで扱う商品としての相性が非常に良いと言えます。
越境EC準備のための8ステップ
越境ECは魅力的な市場機会を提供しますが、成功の鍵は事前の準備にあります。
思いつきで始めてしまうと、法規制や言語・物流の壁に直面し、途中で挫折するケースも少なくありません。
ここでは、初めての越境ECでも確実に立ち上げられるよう、事前に押さえておくべき8つのステップを順に解説します。
取り扱い商品の適合性を確認
まず最初に確認すべきは、販売を検討している商品の「越境適性」です。
国によっては輸入が禁止されている商品や、成分表示・規格に厳しい条件があるカテゴリも存在します(例:化粧品、医薬品、食品、電化製品など)。
また、海外ユーザーが求める商品仕様やデザイン、使用言語なども考慮が必要です。関税負担や輸送効率も含め、「売れるか」だけでなく「売れる体制を整えられるか」を意識して商品を選びましょう。
ターゲット市場での需要を確認
商品が決まったら、どの国や地域に向けて販売するのかを検討します。
現地でのニーズや競合状況をリサーチすることで、実際に売れる見込みがあるのかを判断できます。
Google Trendsや海外のECモールでの検索傾向、現地SNSでの人気アイテムなどを調べるのも有効です。
また、言語・宗教・文化・季節性などによって需要が大きく異なるため、「どこに売るか」は「何を売るか」と同じくらい重要な判断軸です。
販売戦略の策定
ターゲット市場と商品が決まったら、具体的な販売戦略を立てます。価格設定、プロモーション方法(SNSマーケティングや広告出稿など)、ブランディング、カスタマーサポート体制など、どのように顧客にアプローチし、購入に繋げるかを具体的に計画します。現地の文化や商習慣に合わせた戦略が効果的です。
販売商品の準備
商品の在庫や梱包・ラベル表示など、物理的な販売準備も抜かりなく進めましょう。
多言語での商品情報(タイトル・説明文・注意書きなど)や、現地配送に対応した梱包サイズ・内容表示も必須です。
また、関税や関係書類の記載ミスなどがないよう、パッケージや帳票類にも注意を払いましょう。
法規制や商慣習のリサーチ
越境ECでは「知らなかった」では済まされない法的リスクが存在します。
各国の輸入規制、通関ルール、返品ポリシー、表示義務、消費者保護法などは事前に調査し、必要であれば専門家にも相談してください。
法律だけでなく、「送料無料が常識」「返品は無条件」など商慣習も要チェックです。
リソースの確保
越境ECは一人で完結する業務ではありません。
商品の翻訳、広告運用、顧客対応、物流対応など、国内ECよりも必要な作業領域が広がります。
社内リソースだけで回せない場合は、外部パートナー(通訳・物流代行・カスタマー代行など)を活用する準備を進めましょう。
最適な出店方法の選択
最後に、自社に最適な販売チャネルを選定します。
自社ECサイト、Amazonなどの海外モール、越境専門モール、海外転送サービス、代行販売型モデルなど、各手法には特性があります。
ブランド志向か、コスト重視か、販路拡大か、スモールスタートかなど、目的に応じて最適なモデルを選びましょう。

越境EC運営における注意点と対処
越境ECを立ち上げたあとも、継続的な運営には多くの障壁が存在します。
言語や文化の違い、決済手段、物流、返品対応など、国内ECにはない課題が山積しています。
ここでは、越境ECで「実際に起きやすい4つの課題」と「それに対する対処法」をセットで紹介します。
言語・文化の壁
多言語対応は、越境ECにおいて避けられない基本要件です。
商品ページやカスタマー対応で翻訳精度が低いと、信頼を損ねるだけでなく、購入にもつながりません。
また、文化的なタブーや価値観の違いにも配慮が必要です。
【対策】
機械翻訳に頼るのではなく、プロのネイティブ翻訳者や多言語対応のCS代行を導入するのが効果的です。
さらに、FAQを整備し自動応答を活用することで、対応コストを削減しつつユーザー体験を向上させることができます。
決済方法の違い
国ごとに利用される決済手段は異なります。
日本ではクレジットカードが主流でも、中国ではAlipay・WeChat Pay、東南アジアでは現地銀行決済や代引きが一般的です。
【対策】
ターゲット市場で普及している決済手段を事前に調査し、PayPal、Klarna、GrabPayなど地域ごとの決済に対応することが重要です。
複数決済に対応可能な決済代行サービスを導入することで、導入・管理コストの削減にもつながります。
国際物流の不安定さ
国際配送には、遅延、関税トラブル、破損、紛失などのリスクがつきものです。
また、気候や国際情勢によって物流が止まる可能性もあります。
【対策】
信頼できる国際配送会社(DHL、FedEx、ヤマトグローバルなど)を選定し、追跡・補償・保険付きの配送を基本にするのが安全です。
SLA(配達保証)を事前に確認し、トラブル発生時の対応範囲を明文化しておきましょう。
返品・交換対応の複雑さ
返品や交換のルールは国によって異なります。
「無条件返品」や「送料無料返品」が一般的な国もあり、対応を誤るとクレームや信頼低下につながります。
【対策】
各国の返品ルールを調査し、ポリシーを多言語で明記することが重要です。
返品送料の扱いや再販の可否なども含め、明確な条件を示すことでトラブル防止につながります。
可能であれば、海外倉庫を利用して返品対応のコスト・スピードも最適化しましょう。
越境ECの成功事例5選
越境ECは、単なる「海外通販」ではありません。
文化や商習慣の異なる海外市場において成果を上げるには、現地ニーズへの対応力、戦略的なチャネル選定、ブランド価値の伝え方など、多角的なアプローチが求められます。
このセクションでは、大手から中小企業まで実際に成果を上げた日本発ブランドの成功事例を紹介します。
それぞれの企業が、どのようにして海外市場と向き合い、どのような手法で成果を出したのか?今後の越境EC戦略のヒントとしてご活用ください。
ユニクロ
ユニクロ:自社ECとオムニチャネル戦略でグローバル展開
ユニクロは、自社ECサイトを多言語・多通貨対応に拡張し、グローバル展開を進めています。
オンライン注文と実店舗での受け取りを組み合わせたオムニチャネル戦略を採用し、現地消費者の利便性を向上。
また、現地のニーズに合わせた商品開発やマーケティングを行い、海外市場でのブランド力を強化しています。
特にコロナ禍においては、「エアリズムマスク」などの新商品投入により、中国市場を中心に売上を回復。製品の信頼性と品質の高さが海外で評価され、売上の安定につながっています。
出典: ユニクロ ヨーロッパ オンラインストア
BENTO&CO
BENTO&CO:ユニークな商品とコンテンツマーケティングで海外ファンを獲得
BENTO&COは、京都発祥のユニークな弁当箱やキッチン用品を越境ECで販売し、長期的なブログ運営とSNS・メルマガでの継続的な顧客エンゲージメントを通じて海外でのブランド認知と売上を確立しました。
他にはない珍しい高機能な弁当箱や、現代スタイルを取り入れた風呂敷など、独自性の高い商品を多く取り扱っています。
ShopifyなどのプラットフォームやShip&coのような配送ツールを活用し、効率的な運営を実現。
毎年開催する「国際弁当コンテスト」は、集客と日本の弁当文化のアピールに貢献しています。
出典: BENTO&CO 公式サイト
ヤーマン
ヤーマン:中国巨大ECプラットフォームでの戦略的展開と現地ニーズ対応
ヤーマンは、美容家電を中心に展開し、中国最大級のECモール「天猫国際(Tmall Global)」での積極的な出店と現地ニーズに合わせた製品訴求により、特に「独身の日」セールなどで高い販売実績を上げています。
中国の消費者が抱える「大気汚染による肌の汚れ」といった具体的な悩みに対応するため、美顔器の「イオンクレンジング機能」を重点的にプロモーション。
この戦略が奏功し、中国における美顔器を使ったスキンケア方法の浸透と市場拡大に貢献しました。
出典:ヤーマン 公式サイト(グローバル)
Fake Food Japan
Fake Food Japan:日本の精巧な食品サンプルでニッチな海外市場を開拓
Fake Food Japanは、日本独自の文化である精巧な食品サンプルを越境ECで世界に販売し、その驚くべきリアルさで海外のコレクターや観光客から高い評価を得ています。
単なる模倣品にとどまらない芸術性の高さが「本物としか思えない」と驚嘆され、ユニークな日本のお土産としても人気を集めています。
ニッチながらも世界中に存在する需要をオンラインで的確に捉え、特異な商材でグローバルな成功を収めています。
出典:Fake Food Japan 公式サイト
ダイアナ
ダイアナ:高品質な「メイドインジャパン」と顧客に寄り添った多言語サイト戦略
ダイアナは、高品質な「メイドインジャパン」の婦人靴を適正価格で提供することで海外市場での差別化を図り、特に中国語版と英語版のサイトで、きめ細やかな翻訳と顧客対応を通じて越境ECを成功させています。
商品の説明文や問い合わせ対応において、微妙なニュアンスの違いにも配慮し、顧客が正確な情報を得られるよう努めています。
海外でのブランド認知度向上のため、豊富な商品ラインナップを分かりやすく提示するデザインを採用し、SNS連携や動画配信による顧客体験向上にも取り組んでいます。
出典:ダイアナ オンラインストア
まとめ
越境ECは、文化や言語、物流、法規制といった多様な課題が絡むビジネス領域です。
一方で、これらの障壁を乗り越えることで、自社商品の新たな販路を開拓し、持続的な成長機会を得ることも可能です。
本記事では、越境ECの基本構造や主なビジネスモデル、国内ECとの違い、市場の成長性、メリット・リスク、運営に必要な準備、注意点、そして成功企業の事例まで、総合的な観点から解説してきました。
重要なのは、「越境ECを行うこと」自体が目的ではなく、自社の強みやリソースを踏まえたうえで、適切な市場と手法を選択することです。
初期から完璧な体制を整える必要はありませんが、必要な準備と検証を怠れば、想定外のコストやトラブルに直結するリスクもあります。
これから越境ECに取り組む企業にとって、まずは段階的に進められる体制を構築し、自社にとって実行可能かつ再現性のあるモデルを設計することが現実的な第一歩となります。
変化の早い市場環境において、柔軟に対応しながら事業の可能性を拡げていくためにも、本記事の内容がその一助となれば幸いです。
※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比
※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月