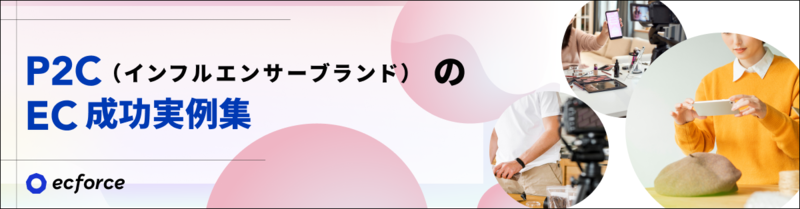この記事でわかること
※この記事は 時点の情報をもとに執筆しています。
SNSや口コミ、レビューで目にするUGC(ユーザー生成コンテンツ)は、現代のマーケティングに欠かせない存在です。
UGCは、一般ユーザーが自発的に投稿するコンテンツで、企業発信の情報よりも信頼されやすく、購買行動に大きな影響を与えます。
本記事では、「UGCとは何か?」という基本から、その効果や活用事例、注意点、さらにはUGCを効果的にマーケティングに取り入れる方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。自社のブランド力やCVR向上につなげたい方は必見です。
関連するテーマについては、下記の記事もぜひチェックしてみてください。
5つのステップで出来る!InstagramのUGCをECサイト/LPに効果的に活用する方法
インフルエンサーマーケティングとは?効果・手法・注意点と成功事例を紹介
UGC(ユーザー生成コンテンツ)とは?
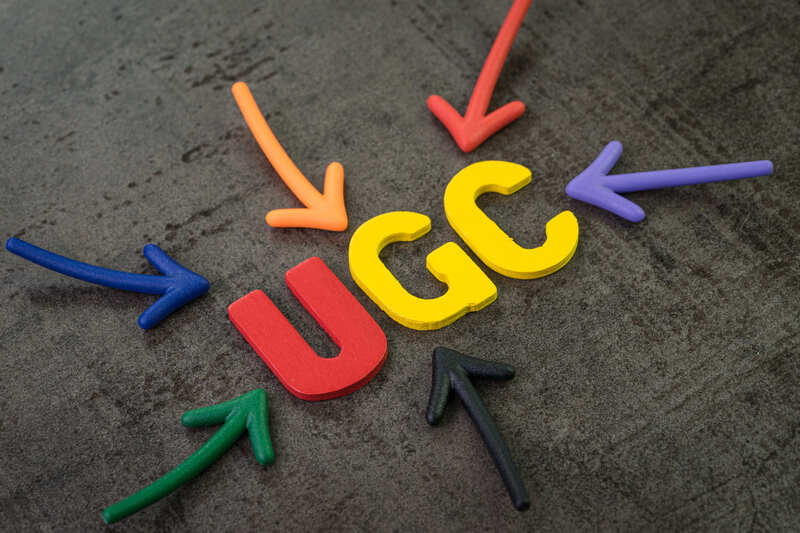
UGC(ユーザー生成コンテンツ)とは、「User Generated Content」の略で、企業ではなく一般のユーザーが自発的に制作・発信するコンテンツを指します。
たとえば、SNSの投稿や商品レビュー、ブログ記事、口コミサイトの評価、YouTubeやTikTokの動画など、ユーザー自身の体験や意見に基づいたコンテンツが該当します。
企業が制作する広告やオウンドメディアとは異なり、UGCはリアルで信頼感があり、共感を呼びやすいという特徴があります。
そのため、マーケティングにおける重要度が年々高まっています。
UGCと混同しやすい関連用語との違い
UGCと似た意味を持つ用語として、「IGC(インフルエンサー生成コンテンツ)」や「CGM(消費者生成メディア)」があります。
これらは混同されやすいものの、マーケティング戦略を立てる上では明確に区別して理解することが重要です。以下でそれぞれの違いを解説します。
IGC(インフルエンサー生成コンテンツ)との違い
IGCとは、「Influencer Generated Content」の略で、インフルエンサーによって制作・発信されるコンテンツを意味します。
一般ユーザーが自発的に投稿するUGCとは異なり、IGCは企業から依頼を受けて制作されるケースが多く、報酬が発生する商業的な性格を持つ点が大きな違いです。
インフルエンサーはすでに一定のフォロワーや影響力を持っているため、IGCは拡散力や波及効果が高いというメリットがあります。
一方で、UGCに比べて「広告的な要素」が強くなる傾向があり、信頼性や親近感の面ではUGCに軍配が上がる場面もあります。
CGM(消費者生成メディア)との関連性
CGMとは「Consumer Generated Media」の略で、消費者によるコンテンツ投稿によって成り立つWebメディア全般を指します。
具体的には、食べログ・価格.com・アットコスメ・Yahoo!知恵袋など、口コミやレビュー、Q&Aが投稿できるプラットフォームが該当します。
UGCが「1つ1つの投稿=コンテンツ」そのものを指すのに対し、CGMはそれらUGCを集約して情報提供メディアとして成立している場を意味します。
つまり、UGCはCGMの構成要素として存在しており、この違いを理解することで、UGCをどこで・どのように活かすかの視点が明確になります。
マーケティングでUGCが重要視される3つの理由
UGCは、なぜこれほどまでにマーケティングで注目されているのでしょうか。
それは、ユーザーのリアルな声を起点としたコンテンツが、企業の広告よりも信頼され、行動を促す力を持っているからです。ここでは、UGCがマーケティングにおいて重視される3つの主要な理由を紹介します。
消費者のリアルな声は信頼性が高い
UGCは、実際に商品やサービスを使ったユーザーによるリアルな体験や感想がベースになっているため、企業発信の広告よりも高い信頼性を持っています。
最近では、購入前に口コミやレビューを確認するのが当たり前になっており、「他のユーザーの評価が信用できる」と感じている消費者が増えています。
第三者の視点で語られるコンテンツだからこそ、説得力があり、ブランドへの好感や購入への安心感にもつながるのです。
購買意思決定に大きな影響を与える
UGC(ユーザー生成コンテンツ)は、消費者の購買意思決定において非常に強い影響力を持っています。
企業が発信する広告よりも、実際のユーザーによる使用体験やレビューといったUGCは、信頼性が高く、購入の後押しとなる重要な要素です。
ある調査では、生活者の64.6%が、購買行動においてUGCを信頼していると回答しており、信頼性の高さが数値としても裏付けられています。
また、ネット通販や定期購入を検討する際には、88.5%の人がUGCを参考にしているというデータもあり、多くの消費者が購入前にUGCに目を通していることが分かります。
さらに、ECサイト内に掲載された特集記事が購買行動に与える影響についての調査では、閲覧者の約半数が「その記事をきっかけに購入した」と回答しています。
SNSの投稿に関しても同様で、Twitterユーザーの約6割が、他人の口コミや投稿を見て商品を購入した経験があるとされています。
このように、UGCは購買を検討するユーザーにとって、信頼性・実用性・共感性の3つを満たす情報源となっており、広告よりもリアルで説得力のあるマーケティング手法として広く活用されています。
出典:
Letro「UGCが購買行動に与える影響調査」|株式会社アライドアーキテクツ
PR TIMES|株式会社アライドアーキテクツ
【UGC調査】ユーザーの6割が購買行動でUGCを信頼、購入の意思決定に影響が最も高いのは「テキスト」|ネットショップ担当者フォーラム
SNSの普及により情報が拡散しやすくなった
X(旧Twitter)やInstagram、TikTokなどのSNSが普及したことで、一般ユーザーの投稿が爆発的に拡散される機会が増えました。
特にSNSでは、ユーザー同士が共感やいいね、リポストを通じて体験談が短時間で拡散されるという特性があります。
これにより、ひとつの投稿が一気にバズり、商品の話題性やブランド認知を一気に広げる力を持つようになっています。
この拡散性の高さが、UGCの価値をさらに高め、企業がUGCを積極的に活用する大きな要因となっています。
UGCマーケティングを始めるための具体的な4ステップ
UGCマーケティングを成功させるためには、単に「投稿を待つ」のではなく、ユーザーが自然と参加したくなるような仕掛けと、それを効果的に収集・活用する体制を整えることが不可欠です。
本章では、初めてUGCマーケティングに取り組む企業に向けて、準備から実行、運用、成果活用までの4ステップを詳しく解説します。
Step1: UGCが自然に発生しやすい環境を整える
UGCは、企業が制作・管理するコンテンツとは異なり、ユーザーの自発的な行動によって生まれるものです。
そのため、「投稿してください」といった企業側からの一方的な働きかけだけでは、継続的なUGCの創出にはつながりません。
大切なのは、ユーザーが自然と投稿したくなるような環境や体験を、あらかじめ設計しておくことです。たとえば、以下のような工夫が有効です。
- ECサイトや商品パッケージにハッシュタグを明記する
- 店舗内の什器やPOPをSNSでシェアされやすいデザインにする
- レビューを書きたくなるような丁寧で印象的なカスタマーサポートを提供する
ユーザーの感情が動いた瞬間に、発信したくなるきっかけがそばにあることで、UGCの自然発生を促しやすくなります。
企業はこうした「仕掛け」を戦略的に組み込むことで、投稿のハードルを下げ、投稿そのものを体験の一部にすることが求められます。
Step2: ユーザーが投稿したくなる仕掛けを作る
UGCをさらに増やすには、ユーザーの投稿する理由を明確にすることが不可欠です。
多くの人にとって、発信のきっかけがなければわざわざ投稿する動機にはなりにくいため、企業は行動の後押しとなるような仕掛けを用意する必要があります。
たとえば、「レビュー投稿でクーポンをプレゼント」といったインセンティブ型のキャンペーンは非常に効果的です。
また、「#わたしの朝の一杯」や「#週末のご褒美ごはん」など、日常と結びつけたハッシュタグを使った投稿企画は、ユーザーの共感を呼びやすく、自然なUGCを生み出しやすくなります。
さらに重要なのは、ユーザーにとっての心理的なハードルを下げることです。
たとえば、「顔を出す必要がない」「文字だけでも参加できる」「スマホで撮影した簡単な写真でもOK」といったガイドラインがあるだけで、投稿への参加意欲は大きく変わります。投稿例をあらかじめ提示しておくことも有効です。
特に初めて投稿するユーザーは、「どういう風に投稿すればいいのか」「評価されるのか」などを不安に感じやすいため、参加しやすい空気感や導線の設計が、投稿数の底上げにつながります。
Step3: 集まったUGCを収集・分析する
UGCが集まり始めたら、それらの投稿を継続的に収集し、内容を分析する体制を整えることが重要です。
SNSやレビュー、ブログなど複数のチャネルに投稿されるUGCを把握するには、情報を一元的に管理できる仕組みを用意すると効率的です。
また、ただ数を集めるのではなく、どのような投稿がユーザーの共感や反応を得ているのかを確認することも大切です。
投稿の形式や内容、タイミング、反応数などをもとに傾向を読み取れば、UGCを今後どのように活用すべきかが見えてきます。
収集と分析を繰り返しながら、より効果的なUGCの創出と活用につなげていくことが、マーケティング成果の最大化につながります。
Step4: 収集したUGCを多角的に活用する
収集したUGCは、複数のチャネルで戦略的に活用することで、その価値を最大化することができます。
たとえば、ECサイトの商品ページに掲載する場合、単にレビュー欄にコメントを表示するだけでなく、以下のような見せ方の工夫が効果を高めます。
- 商品画像のすぐ下に「実際の購入者の写真」としてスライダー形式で掲載する
- レビューの中でも評価が高く、写真付きの投稿を優先的に上位表示する
- 「この商品を使っている人の投稿を見る」といったボタンを設け、InstagramやXの投稿一覧に遷移できるようにする
ユーザーの目線に立ち、「信頼感」「使用イメージ」「共感」の3点を満たす見せ方を意識すると、UGCの効果はより強く発揮されます。
また、UGCを広告素材として活用する際にも、商品ページとデザイントーンを合わせることで、ブランドの一貫性を保ちながら訴求力を高めることができます。

UGCの代表的な活用方法と成功事例
UGCは、企業のマーケティング施策に多角的に活用できる強力なコンテンツ資源です。
活用する目的やチャネルによって、その効果は大きく変わります。
この章では、UGCの代表的な活用方法と、実際の企業による成功事例を紹介します。
ECサイトやLPでCV率を高める
UGCは、商品を検討しているユーザーに対してリアルな使用感や体験を伝える力があります。
特にECサイトやランディングページでの活用は、購入を後押しする効果が高く、CV(コンバージョン)率の向上が期待できます。
たとえば、給水型浄水ウォーターサーバーを展開する株式会社TOKAIは、実際の利用者による口コミや写真を商品紹介ページに掲載することで、商品理解と購入意欲の向上を図っています。
生活者目線のリアルな声が伝わることで、ユーザーにとって安心感のある購買体験を提供しています。
出典:TOKAIウォーターサーバー公式サイト|株式会社TOKAI
SNSでエンゲージメントを高める
UGCは、SNSとの相性も非常に高いコンテンツです。
ユーザーの投稿を企業の公式アカウントで紹介することで、投稿者との関係性が深まり、他のユーザーからの参加も促進されます。
また、企業視点ではなくユーザー視点のコンテンツを発信することで、ブランドへの親近感や信頼性も高まります。
食品メーカーの永谷園は、X(旧Twitter)で「#永谷園」とタグ付けされた投稿の一部を公式アカウントで紹介し、ユーザー参加型のコミュニケーションを展開しています。
投稿されたレシピやアレンジ方法をシェアすることで、商品の多様な使い方が可視化され、購買意欲の喚起にもつながっています。
広告に活用してクリック率を上げる
UGCは、広告クリエイティブとして活用することでも大きな効果を発揮します。
ユーザーが自発的に投稿した写真や動画は、プロが制作した広告とは異なり、親しみやリアリティがあるため、広告感を抑えつつ高い訴求力を持たせることができます。
特にSNS広告においては、生活者視点のコンテンツが自然にフィードに溶け込み、ユーザーのクリック率やコンバージョン率を高める傾向があります。
D2Cブランドの「FABRIC TOKYO」では、顧客による着用写真やレビューコンテンツを広告や公式サイト上で活用しています。
ユーザーのリアルな声を反映させることで、ブランドの世界観と親和性を保ちながら、自然な訴求や共感を生む広告クリエイティブの構築につなげています。
UGCの活用により、ユーザー目線の情報発信を強化し、ブランドへの信頼感を醸成する取り組みが進められています。
UGCを活用したクリエイティブは、ブランドからの一方的なメッセージではなく、顧客の声を代弁する形で商品価値を伝えるため、初めてブランドに触れるユーザーにも受け入れられやすい特徴があります。
出典:FABRIC TOKYO公式サイト|株式会社FABRIC TOKYO
顧客の声を商品開発や改善に活かす
UGCは、マーケティング素材にとどまらず、商品やサービスの改善に役立つ「生活者からのリアルな声」としても活用できます。
レビューや投稿内容を分析することで、ユーザーがどのような価値を重視しているか、どのような不満や期待を持っているかを把握することが可能です。
スターバックス コーヒー ジャパンでは、SNSやアンケートを通じて寄せられた意見を新商品の開発や販売戦略に活かす事例があり、季節限定商品などではユーザーの反応をきっかけに定番化されるケースもあります。
このように、UGCは顧客との共創によるブランド価値向上にも貢献しています。
出典:スターバックス 公式サイト|スターバックス コーヒー ジャパン株式会社
ECサイトの購買率を高めるUGC活用法
ECサイトを運営する企業にとって、UGCはコンバージョン率(CVR)を高める上で非常に有効な要素となります。
実際に商品を使用したユーザーのリアルな声や写真は、商品説明以上に購買意欲に働きかける力を持っています。
UGCをECサイトで効果的に活用する方法については以下の記事でも詳しく解説しています。
5つのステップで出来る!InstagramのUGCをECサイト/LPに効果的に活用する方法|ecforce blog
UGCが購入率に与える影響
複数の調査結果から、UGCの有無によってECサイトの成果には明確な差が生まれることがわかっています。
たとえば、YOTPOの公式ブログ記事「Show Star Ratings In Your Product Preview」では、UGC(星評価など)を見たユーザーのコンバージョン率が5.6%であるのに対し、UGCを見ていないユーザーは2.1%にとどまるとの記述が確認できます。
これは、購買行動の過程でUGCに触れることが、購入確率を約2.7倍にまで高める効果があることを示しています。
さらに、YOTPOとZendeskによる共同レポートでも、UGCに触れたユーザーのCVRは5.6%で、UGC未接触ユーザーの2.1%と比較して大幅に高いことが明記されています。
この傾向は、ファッション・美容・日用品など、使用感やビジュアルが購買判断に影響する商材で特に顕著であり、UGCの採用がECサイトの購入率向上に寄与する強力な証拠となっています。
出典:
YOTPO公式ブログ|Yotpo Ltd.
YOTPO × Zendesk 共同レポート|Yotpo Ltd.
効果的なUGCの形式
UGCにはテキスト、写真、動画などさまざまな形式がありますが、特に視覚的なUGC(画像や動画)は購買意欲を高める効果が高いとされています。
YOTPOが発表したデータによると、視覚的なUGC(Instagram投稿や写真付きレビューなど)を閲覧したユーザーは、閲覧していないユーザーに比べてコンバージョン率が161%高いという結果が示されています。
これは、商品購入の意思決定において、写真や動画といったビジュアルコンテンツが大きな影響力を持っていることを示しています。
このことから、レビュー欄を設けるだけでなく、ユーザーが投稿した画像や動画を併せて掲載することで、購入検討中のユーザーの不安を和らげ、意思決定を後押しする効果が期待できます。
UGCを導線に活かすポイント
UGCの効果を最大限に発揮するには、ただ集めて掲載するだけでは不十分です。
ユーザーが購入を検討するタイミングに合わせて、適切な場所でUGCを見せることが重要です。
たとえば、次のような導線設計が考えられます。
- 商品詳細ページの下部やレビューセクションに、ユーザーによる写真付きの投稿を表示する
- 商品一覧ページに星評価や投稿件数を表示して、他ユーザーの評価をひと目で確認できるようにする
- カートボタンの近くに、実際の使用写真や「愛用者の声」を添えることで、不安を軽減する
これらの工夫によって、UGCが「検討」から「購入」へ踏み切る後押しとなり、CVR(コンバージョン率)の改善につながります。
UGCをただの賑やかしとしてではなく、購買導線の一部として戦略的に配置することが成果を生み出す鍵です。
ECサイトにおける購入率の向上には、信頼感と実感の提供が欠かせません。
企業目線ではなく、ユーザー目線のリアルな情報を取り入れることで、商品への理解と納得感が深まり、購入行動にポジティブな影響を与えることができます。
UGCはその役割を担う強力なコンテンツであり、正しく設計・活用することで、EC運営の成果を大きく左右する要素となります。
UGC活用でよくある失敗とその対処法
UGCを活用したマーケティングには多くのメリットがありますが、やみくもに始めてしまうと効果が出なかったり、かえってユーザーとの信頼関係を損ねてしまったりすることもあります。
ここでは、企業が陥りやすい失敗例と、その対処法を整理して解説します。
ハッシュタグだけ用意して投稿を待ってしまう
よくある失敗の一つが、「ハッシュタグを設定しただけで、あとは自然に投稿が集まるのを待つ」というスタンスです。
UGCはあくまでもユーザーの自発的な行動によって生まれるものですが、企業側が何の仕掛けも設けない状態では、なかなか投稿は生まれません。
対処法としては、投稿を促すための具体的なキャンペーンや、参加しやすい投稿テーマの設定が効果的です。
たとえば、「#〇〇と過ごす週末」など、日常に結びついたタグや、簡単なプレゼント企画と組み合わせることで、投稿数を増やすことができます。
投稿されていても収集・活用できていない
ユーザーが投稿しているにもかかわらず、企業側がUGCを把握できておらず、活用の第一歩を踏み出せていないというケースもよく見られます。
たとえば、「#商品名」やブランド名の表記揺れによって、検索で投稿を見逃していたり、UGCの収集・管理が手作業になっていて対応しきれていなかったりといった課題が背景にあります。
この場合は、まず「どこで」「どのような形で」UGCが生まれているかを整理し、UGCを一元管理できる仕組みや体制を整えることが重要です。
社内にUGC管理担当を設ける、または管理ツールを導入することで、見落としや活用漏れを防ぐことができます。
投稿の見せ方が悪くCVにつながらない
UGCをECサイトやLPに掲載しているのに、思ったように購入につながらないという場合は、コンテンツの見せ方や配置に問題があるケースが考えられます。
たとえば、レビュー欄の下部にテキストだけが並んでいて、ビジュアルがない、あるいは写真があってもスマホで表示しにくい設計になっているなど、UXの観点で不十分な状態ではUGCの効果を十分に引き出せません。
UGCを活かすには、ユーザーが自然に目にし、信頼感を得られる導線設計が必要です。
たとえば、商品写真のすぐ下にスライダー形式でUGCを配置する、写真付き投稿を目立つ位置に表示するといった工夫が、購入率の向上につながります。
投稿の許諾や法的リスクへの配慮が不十分
著作権の許諾を得ないままUGCを引用したり、薬機法や景品表示法に違反するような内容をそのまま掲載したりするなど、法的リスクに対する意識が不十分なまま運用してしまうことも、トラブルの原因になります。
この対処法としては、事前に投稿者から明確な許諾を得る仕組みを整えるとともに、掲載前に法務チェックを行う体制をつくることが基本です。
また、ガイドラインを整備し、「どのような投稿を紹介対象とするか」「NGとなる表現は何か」を社内で共有しておくことも、リスク回避につながります。
UGCの活用には多くのメリットがある一方で、適切な準備と運用体制がなければ、思うような成果を得ることはできません。
よくある失敗をあらかじめ把握し、仕組みづくりとルール設計を整えたうえで、戦略的にUGCマーケティングを展開することが、成功への第一歩となります。
UGCを活用する前に知っておきたい3つの注意点
UGCは企業にとって強力なマーケティング資産となり得ますが、適切に運用しなければ思わぬトラブルやリスクにつながる可能性もあります。
実際に活用する前に、必ず確認しておきたい注意点を3つの観点から解説します。
投稿者の許諾を得る
UGCはユーザーが自発的に作成・投稿したコンテンツであり、その著作権は原則として投稿者本人にあります。
企業がその内容を広告やサイト上で二次利用する場合、事前に明確な許諾を得ることが必要不可欠です。
無断でUGCを使用すると、著作権侵害とみなされる恐れがあり、法的トラブルや企業イメージの悪化につながる可能性もあります。
投稿を活用する際は、SNSのダイレクトメッセージで使用許可を確認する、あるいはキャンペーン規約にあらかじめ二次利用に関する条件を明記するなど、ルールに基づいた対応が重要です。
法令に抵触する表現が含まれていないかを確認する
UGCは投稿者による自由な表現である一方で、企業がマーケティング目的で掲載・使用する場合には、その内容が各種法令に抵触していないかを事前にチェックする必要があります。
特に注意が必要なのは、薬機法や景品表示法への違反リスクです。
たとえユーザーの感想であっても、「短期間で効果が出た」「他の商品よりも優れている」といった表現をそのまま掲載すると、法律上の問題を引き起こす可能性があります。
UGCを活用する際は、社内の法務担当や専門家のチェックを受ける体制を整え、広告表現として適切かどうかを判断した上で掲載することが求められます。
ネガティブな投稿への対応方針を決めておく
UGCはポジティブな内容ばかりとは限らず、時には商品やサービスへの不満、クレームなどが含まれることもあります。
こうした投稿にどう向き合うかは、企業の信頼性やユーザーとの関係構築に大きな影響を与えるポイントです。
ネガティブな内容を一方的に削除したり、反応せずに放置したりするのではなく、冷静かつ誠実に対応する姿勢が重要です。
たとえば、事実確認の上で丁寧にコメントを返す、必要に応じて個別に連絡を取るなど、状況に応じた判断が求められます。
また、あらかじめどのような投稿を活用対象とするか、炎上やクレーム投稿があった場合の対応手順を社内で共有しておくことで、トラブル発生時の対応スピードと一貫性が確保できます。
UGCがなかなか集まらないときの対処法
UGCの重要性を理解し、環境や仕組みを整えたつもりでも、なかなかユーザーから投稿が集まらないというケースは少なくありません。
そうした状況に直面したときは、ユーザー視点に立ち返り、「投稿したくなるきっかけ」が設計されているかどうかを見直すことが大切です。
ここでは、UGC創出に課題を感じたときに実践できる対処法を紹介します。
ユーザーがシェアしたくなる体験を提供する
UGCは、ユーザーが「誰かに伝えたくなる体験」に出会ったときに生まれやすくなります。
商品やサービスの品質だけでなく、開封時の驚き、店舗での接客、使ってみたときの満足感など、感情が動く瞬間を設計できているかを確認しましょう。
たとえば、SNS映えするパッケージデザイン、開封時に気持ちを伝えるメッセージカード、ユニークな同梱物なども、投稿のきっかけになる要素です。
ユーザーの記憶に残る体験が、自然なUGCの創出につながります。
ハッシュタグを活用したキャンペーンを実施する
UGCを促す手段として、SNSでのハッシュタグキャンペーンは特に有効です。
ブランド独自のハッシュタグを設け、投稿テーマを明確にすることで、参加のハードルを下げることができます。
投稿に対して抽選でプレゼントを贈る、投稿を公式アカウントで紹介するといったインセンティブを組み合わせると、さらに参加率が高まります。
重要なのは、ユーザーに「投稿しても良い理由」を与えることです。
ルールはできるだけシンプルにし、誰でも気軽に参加できるよう設計することがポイントです。
インフルエンサーを起点に投稿の流れを作る
UGCが自然発生しにくい初期段階では、インフルエンサーによる発信をきっかけに、一般ユーザーの投稿が増える流れをつくるのも効果的です。
フォロワーとの信頼関係を築いているインフルエンサーによる投稿は、共感を得やすく、二次的なUGCを生み出す起点になります。
この場合、投稿がPRであることを明記し、透明性のある形で協力を依頼することが重要です。
ステルスマーケティングと受け取られないよう、企業側の意図を明確にしたうえで展開しましょう。
UGCが思うように集まらないときは、ユーザーにとっての「投稿する理由」が設計できているかを見直すことが重要です。
感情が動く体験、参加しやすい仕掛け、共感を広げる起点のいずれか、または複数を組み合わせることで、UGCが自然と広がる環境を作ることができます。
まとめ
UGC(ユーザー生成コンテンツ)は、企業にとって非常に価値の高いマーケティング資産です。
広告や企業発信の情報に対する信頼が薄れつつある中、ユーザー自身の声や体験に基づいたコンテンツは、消費者の共感を呼び、購買行動に強く影響を与えるようになっています。
UGCの活用によって得られる効果は多岐にわたります。
ECサイトにおける購入率の向上、SNSでのエンゲージメント拡大、広告クリエイティブとしての転用、さらに商品開発やサービス改善へのフィードバックなど、企業活動全体に対して広く波及する可能性を持っています。
一方で、UGCを活用する際には、著作権の扱いや法令遵守、ネガティブな投稿への対応など、適切な運用ルールを整えておくことが不可欠です。
ただ集めて使うのではなく、「どう扱い、どう信頼を築くか」が成果に直結します。
まずは、ユーザーが思わず発信したくなる体験を提供することから始めてみましょう。
小さな仕掛けや一つの投稿が、やがてブランドの信頼や認知、売上を支える力になることもあります。
UGCを「単なる投稿」としてではなく、顧客との継続的な関係づくりのきっかけとして捉えることが、これからのマーケティングにおいてますます重要になっていくでしょう。
※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比
※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月