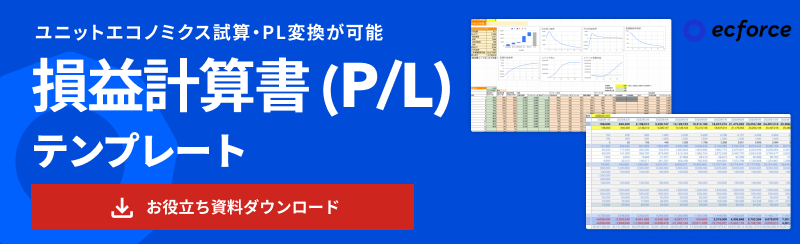この記事でわかること
※この記事は 時点の情報をもとに執筆しています。
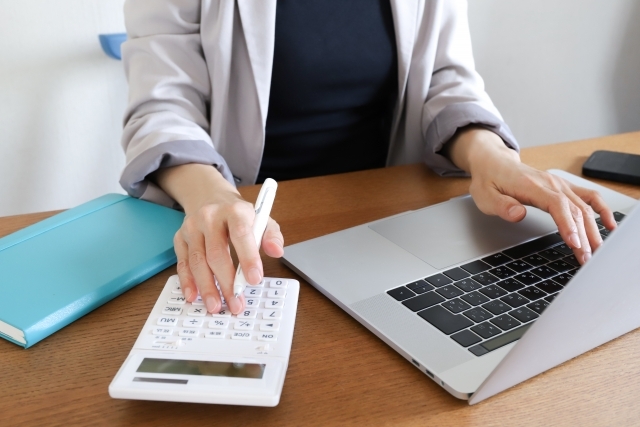
ネットショップにおける販売価格の決め方には、原価率・利益率から逆算する方法や、競合商品を参考に決定する方法などがあります。原価を計算する際は、自分の人件費や配送料など、見落としやすいコストも忘れずに含めることが重要です。価格設定の土台となる基礎知識や販売価格の決め方、原価率を抑えるコツを解説します。
販売価格を決める前に知っておきたい基礎知識

ネットショップ運営において適正な販売価格を決めるには、原価の計算方法や原価率、利益率などを把握しておくことが重要です。販売価格の決め方を紹介する前に、価格設定の土台となる基礎知識を解説します。
原価とは
原価とは、商品やサービスを提供するために直接かかった費用のことです。仕入れ費用や材料費、人件費、配送料、梱包材代などが含まれます。ネットショップで商品を販売する場合、原価に利益を上乗せして販売価格が決定されます。適切な販売価格を決めるためには、まず正確な原価を把握することが重要です。
原価の計算方法
■ハンドメイドのブローチ10個を制作・販売する場合
材料費:10個分のブローチ用の刺繍糸、フェルト、金具 3,000円
制作にかかった時間:5時間(1,000円/時)5,000円
材料の仕入れ送料:500円
梱包材代(台紙、OPP袋など):10個分200円
合計(10個分の総費用)8,700円
1個あたりの原価8,700円 ÷ 10個 = 870円
※計算式をわかりやすくするため、光熱費や家賃などの費用は省いています。
注意点は、原価 = 材料費という認識で計算しないことです。人件費や送料、梱包材代を考慮しないで計算すると、材料費の3,000円 ÷ 10個で1個あたりの原価が300円となり、仮に800円で販売しても、1個70円の赤字となってしまいます。
原価を計算する際は、必ず人件費や送料など、仕入れ・制作にかかった費用を含めるようにしましょう。
原価率とは
原価率とは、売上高に対して原価が占める割合です。原価率が低いほど、商品の提供にかかるコストが抑えられており、利益を生み出しやすい構造だと言えます。
■原価率の計算式
原価率(%) = (原価 ÷ 売上)× 100
<計算例>
1,000円で販売した商品の原価が300円だった場合:原価率 = (300円 ÷ 1,000円)× 100 = 30%
利益率とは
利益率とは、売上高に対してどれだけ利益を上げているかを示す割合です。利益率が高いほど、効率よく収益を上げていると言えます。
■利益率の計算式
利益率(%) = (利益 ÷ 売上高) × 100
利益にはさまざまな種類がありますが、販売価格を決める上で基本となるのが、売上から原価を引いた「売上総利益」を用いた利益率です。他に、売上から原価に加えて販売費・一般管理費を差し引いた「営業利益」などがあります。
上代・下代とは
「上代(じょうだい)」「下代(げだい)」とは、主に卸売業や小売業で使われる、商品の価格に関する専門用語です。上代とは、「定価」や「メーカー希望小売価格」のことで、商品が一般の消費者に販売される際の最終的な価格を指します。ネットショップや店舗で目にする価格が「上代」に相当します。
下代とは、小売店やネットショップが商品を仕入れる際の価格のことです。「卸売価格」とも呼び、上代(定価)から利益や手数料を引いたもので、メーカーや卸売業者から小売業者への販売価格を指します。
販売価格の決め方が売上を左右する

販売価格はネットショップの売上を左右する重要な要素です。価格を少し変更するだけでも、顧客の購買行動を促す効果が期待できます。特に、期間限定セールなどのイベントは、売上を一時的に伸ばす戦略として有効です。
|
プロモーション価格設定 |
期間限定で価格を引き下げることで、顧客の購買意欲を高めます。季節の変わり目やイベントに合わせて戦略的に行うことで、売上増や在庫処分を狙えます。 |
|
ダイナミック価格設定 |
需要の変動や在庫状況、競合の価格に応じてリアルタイムで価格を変更する手法です。需要が高い時には高く、低い時には安く設定することで、販売機会の最大化を目指します。 |
こうした価格設定の方法は売上増に有効ですが、頻繁に価格を変更すると顧客の信頼を損ない、購買意欲を下げてしまう可能性もあります。
また、販売価格は売上に加えて、顧客がブランドに対して抱くイメージも決定づけます。高価格帯のブランドは、高品質なプレミアムブランドとして認知されやすく、低〜中価格帯のブランドは、手頃でコストパフォーマンスがよいイメージで、幅広い顧客層に受け入れられやすい傾向です。
どの価格帯でも、価格に見合った、あるいは価格以上の品質を提供することで、顧客は「よい買い物をした」と感じ、顧客満足度が高まりやすくなります。販売価格の設定には原価計算だけでなく、競合分析、顧客の購買意欲、目指すブランドイメージなども考慮するとよいでしょう。
ECマーケティングとは?売上アップにつながる施策と今後の展望まで解説
販売価格の基本の決め方

販売価格の基本の決め方には、原価率から決める、利益率から決める、競合商品を参考に決める方法があります。
原価率から決める
原価を基準に、必要な利益を確保できる価格を設定する方法です。
■計算方法
確保したい原価率を先に設定し、そこから販売価格を逆算します。
例: 原価300円の商品で、原価率を30%に抑えたい場合
原価300円 ÷ 0.3(30%) = 販売価格1,000円
参考までに、ネットショップにおける原価率の平均は30%前後と言われています。ハンドメイド品であれば、材料費に加えて人件費がかかるため、原価率15〜20%程度と低くなることもあります。
利益率から決める
確保したい利益率を先に設定し、販売価格を逆算する方法です。
例: 原価300円の商品で、利益率を70%確保したい場合
原価300円 ÷ 0.3(1 - 利益率) = 販売価格1,000円
なお、原価率と利益率は表裏一体の関係にあるため(原価率が30%なら利益率は70%)、どちらを基準に逆算しても、販売価格は同じになります。
利益目標が明確な場合は、「30%の利益が欲しいからこの価格にする」といったように、利益率から逆算するほうが分かりやすいでしょう。一方、仕入れ値が変動しやすい場合は、原価率から逆算するほうがコスト感覚を維持しやすくなります。
競合商品を参考に決める
競合他社が提供している類似商品の価格を基準に、自社の価格を調整する方法もあります。競合の商品がいくらで販売しているのか、どういったラインナップがあるのかリサーチすることは非常に重要です。市場調査を怠ると、他社と価格を比較されて商品が売れなくなる可能性もあります。
市場調査をした上で、競合と比べて差別化要素が少ない場合や、市場シェアを維持したい場合には、競合と同水準の価格を採用します。価格優位性で顧客を惹きつけたい場合には、競合より少し安い価格に。品質や機能、ブランド力に明確な優位性がある場合には、競合より高い価格にしても問題ありません。
注意点として、競合よりも安く設定しすぎると価格競争に巻き込まれたり、「価格が安いから品質も低いかもしれない」と思われたりするリスクがあります。
競合よりも高い価格で販売したい場合は、SNSなどを利用してブランドのファンをつける、お店独自の特典をつける、希少性の高いアイテムを取り扱うなどして、差別化を図る必要があります。
その他の決め方
上記以外にも、売上目標やブランドイメージ、商品の特性に応じて戦略的に価格を設定する方法があります。
|
コストに利益を乗せる |
原価(コスト)に得たい利益をプラスして価格を決める方法です。 |
|
需要で決める |
顧客の需要や人気に応じて価格を変動させる方法です。季節ものの商品など、需要が高い時は価格を上げ、シーズン外れの商品など、需要が低い時は価格を下げます。 |
|
名声価格法 |
ブランドイメージを意図的に高めるために、原価や競合価格に比べて高めの価格を設定する方法です。「高価格=高品質」というイメージを顧客に持たせ、ブランド価値を高めることを目的とします(例:高級ブランド品、限定生産品、化粧品、高級商材)。 |
|
商品のライフサイクルに合わせて変動させる |
商品の市場投入から衰退までのサイクルに合わせて価格を変動させます。新発売の時は高価格で少量を販売させ、時間とともに価格を調整するなどの手法があります。 |
|
他の自社商品との兼ね合いで決める |
複数の商品をラインナップしている場合に、それぞれの価格に階層や役割を持たせる方法です。主力の収益商品は適正利益を確保する価格設定をして、集客商品は原価ギリギリまたはそれ以下の価格で販売し、他の商品の購入を促します。 |
販売価格の決め方ごとのメリット・デメリット

販売価格の決め方ごとに、メリットとデメリットを理解しておくことは売上を伸ばす上で重要です。
|
決定方法 |
アプローチの基本 | メリット |
デメリット |
|---|---|---|---|
|
原価率から決める |
コストに焦点 | 計算が簡単で迅速に価格設定できる |
市場価格と乖離し、売れない価格になる恐れがある |
|
利益率から決める |
利益目標に焦点 | 必要な利益を確保しやすい |
顧客目線がないため、価格に納得感がない場合がある |
|
競合商品を参考に決める |
市場に焦点 | 市場価格と乖離しないため購入されやすい |
利益率が低くなる場合がある |
原価率から決める方法は、迅速に価格設定でき、赤字を回避して最低限の収益性を確保できます。デメリットは、原価に基づいて決めた価格が競合商品より高すぎる、または安すぎる場合があることです。顧客が感じる商品の価値が考慮されないため、高すぎると売れず、安すぎると利益を逃す可能性があります。
利益率から決める方法は、確保したい利益を反映した価格設定ができる一方で、設定した価格が市場の相場から外れている可能性があり、売上不振につながることがあります。
また、競合商品を参考に決めると、市場価格と乖離せず、顧客が納得しやすい価格帯で販売しやすくなります。競合を意識してポジショニングや差別化を打ち出しやすくなりますが、自社の原価が高くても、競合の価格に合わせる必要がある場合、目標とする利益率を確保できない恐れがあります。
これらのメリットとデメリットを踏まえ、ネットショップの販売価格は、「原価・利益」の視点と「市場・顧客」の視点を組み合わせた、総合的なアプローチで決定するのが理想的です。
実際に販売価格を決める際の流れ

実際にネットショップで販売価格を決定する際の流れを、4つのステップで解説します。販売価格の決め方にはさまざまな方法がありますが、ここでは最初に原価率を求め、その数値を競合商品の価格と比べた上で価格を調整する方法を採用しています。
①原価率を3割として計算する
まず、必要な利益を確保できる最低ラインを見極めるために、目標とする原価率を設定し、仮の販売価格(ベース価格)を算出します。
例:原価が500円、目標とする原価率が30%の場合
仮の販売価格 = 500円 ÷ 0.3 = 約1,667円
この価格(1,667円)を下回ると、目標とする利益率(70%)を確保できないという、価格の下限ラインがわかります。
※ここでは省略していますが、実際には利用しているサービスの手数料や、人件費・販売費も考慮して計算します。
②競合商品の価格と比べる
ステップ①で算出した仮の価格が、市場で受け入れられる水準かを確認します。競合商品の平均価格に対して、とるべき戦略の一例は以下の通りです。
| 仮の販売価格(例:1,667円) | 競合商品の平均価格 | とるべき戦略 |
|---|---|---|
| 高い | 1,200円 | ステップ③で差別化要因による値上げができるか検討するか、原価率の見直しが必要 |
| 同程度 | 1,700円 | 競合と同等の価格で市場に投入することを検討 |
| 安い | 2,500円 | ステップ③で付加価値を加算し、価格を引き上げることを検討(利益を最大化) |
③商品の特徴に合わせて価格を変更する
仮の価格と競合価格の比較に基づき、自社商品の強みや付加価値を反映させて価格を調整します。
| 自社商品の特徴 | 価格の方向性 | 理由・効果 |
|---|---|---|
| 独自性・高品質 | 価格を上げる(プレミアム価格) | 「高価格=高品質」のイメージを顧客に与え、ブランド価値を高める |
| 機能がシンプル | 価格を下げる(低価格戦略) | 価格競争力を持たせ、競合よりも買いやすい選択肢として訴求する |
| ブランド力 | 価格を上げる | 既存顧客やファンに対し、適正なブランド料を請求し、利益を確保する |
④価格を調整して購入のハードルを下げる
最後に、決定した販売価格に対し、顧客が購入しやすくなるよう調整を行います。
端数価格設定: 価格を1,980円や4,990円などの端数に設定することで、顧客に「2,000円」「5,000円」よりも安く感じる効果を与えます。
松竹梅の法則: 商品ラインナップに、高価格帯(松)、中価格帯(竹)、低価格帯(梅)の3つを用意することで、顧客が真ん中の中価格帯の商品を選びやすくなるように誘導します。
一例として、2,000円の商品を1,980円に設定すると、実際の価格は20円しか違いませんが、顧客は割安感を覚え、購入のハードルを下げる効果があります。こういった工夫はさまざまな店舗で採用されているので、他のネットショップの販売方法を学んでみるのもおすすめです。
販売価格の決め方の注意点

販売価格を決める際は、市場価格を考慮しないと売上が伸び悩む原因になります。必要以上に高すぎる・安すぎる価格設定は避け、隠れたコストも踏まえて適切な原価を計算しましょう。
競合商品の価格相場と大きく離れないようにする
価格を設定する際は、市場価格を無視してはいけません。自社の価格が相場の価格帯から大きく外れると、販売機会を逃す可能性が高くなります。
- 相場より高すぎる場合
特別な付加価値(高品質、独自のデザイン、強力なブランドなど)がないにも関わらず相場より高すぎると、顧客は割高だと感じ、購入をためらいます。
- 相場より安すぎる場合
相場を大きく下回ると、「品質が悪いのではないか?」という不信感を顧客に抱かせることがあります。
対策として、定期的に競合価格の調査を行い、自社商品のポジショニング(品質、機能、ブランド力)を踏まえた上で、相場価格帯の中で適切な価格を決定するとよいでしょう。
安すぎる価格設定は避ける
「安ければ売れる」と考え、必要以上に価格を引き下げてしまうことも問題です。原価ギリギリや原価割れの価格設定では、どれだけ売上を伸ばしても、広告費や人件費、運営費などの経費を賄えず赤字に陥ります。
また、価格を下げる競争は自社だけでなく、市場全体の利益を圧迫します。売上に伸び悩む場合は、迅速な配送、丁寧な梱包、手厚いアフターサービスなど、価格以外の価値を高めて差別化を図ることが重要です。
見落としやすいコストに注意する
原価計算で必要なコストを見落としている場合、気づかないうちに赤字になっている可能性があります。
■見落としやすいコストの一例
| 項目 | 内容 | ネットショップでの注意点 |
|---|---|---|
| 販売手数料 | モール(楽天市場、Amazonなど)や決済代行サービスに支払う手数料 | 売上高の5%〜10%以上かかることが多く、利益から差し引く必要がある |
| 配送料(顧客負担外) | 顧客の購入額が送料無料ラインに満たない場合の不足分の送料 | 販管費として計上すべき隠れたコスト |
| 人件費 | 商品の梱包、発送作業、顧客対応、サイト更新にかかる労働時間 | ハンドメイドや個人事業主は特に、自分の時給を原価や販管費として計上し、価格に含めることが重要 |
| 広告宣伝費 | Google、SNS、モール内広告などに費やした費用 | 利益目標を立てる際に、利益から差し引くべき経費 |
これらのコストを正確に把握しないと、最終的な営業利益がゼロ、またはマイナスになる恐れがあります。販売価格はこれらの費用をすべて賄った上で、最終的に利益が残るように設定するのがコツです。
原価率を抑える5つのコツ

原価率を抑えると、商品の利益率も高まるため、結果的に売上を向上させます。原価率を抑えるには、仕入れコストやロス率を下げる、販売価格を上げる、人件費を減らすなどの方法があります。
①仕入れコストを下げる
| 大量仕入れの交渉 | 仕入れ量を増やすことで、業者に対して単価の引き下げや特別割引を交渉します。ただし、在庫リスクも増えるため、販売見込みを正確に立てることが前提です。 |
| 仕入れ先の見直し | 現在の仕入れ先だけでなく、国内外の製造元を比較し、より安価な仕入れルートを開拓する方法です。 |
| 素材の代替検討 | 商品の品質を大きく損なわない範囲で、より安価な素材や部品に切り替えることを検討します。 |
②ロス率を下げる
| 不良品の削減 | 製造工程や検品体制を見直し、初期不良の発生を最小限に抑えます。不良品は、その分の材料費、労務費がすべて損失(ロス)となります。 |
| 廃棄を減らす | 在庫管理を徹底し、販売期限が近い商品を把握し、期限前にセールなどで売り切るための対策を講じます。 |
| 破損対策 | 梱包や保管方法を改善し、配送中や保管中の破損による販売不可商品を減らします。 |
③販売価格を高くする
| 付加価値による値上げ | 単なる値上げではなく、商品のデザイン改良、保証期間の延長、オリジナルのギフトラッピングなどの付加価値を加え、顧客が価格上昇を納得できるようにします。 |
| ターゲット層の見直し | より高価格帯の商品を購買できる顧客層にターゲットを変更し、ブランディングを強化することで、価格の正当化を図ります。 |
④人件費を減らす
| 作業効率の改善 | 製造や梱包のプロセスを見直し、無駄な工程を削減したり、効率的なツールを導入したりして、1個あたりの制作にかかる時間を短縮します。 |
| 自動化・デジタル化 | 事務作業や在庫登録などの作業を自動化ツールやAIで代行し、労務コストを削減します。 |
➄在庫管理方法を調整する
在庫管理を調整することも、原価率に影響を与えます。過剰な在庫は保管コストを増加させるだけでなく、将来的にロスになるリスクを高めます。売れ筋商品を正確に予測し、欠品しないギリギリの量を維持することで、在庫リスクを最小限に抑えます。
販売価格の決め方を参考に売上アップを目指そう

販売価格の決め方には、原価率や利益率から計算する方法や、競合商品と比べる方法などがあります。実際に販売価格を決める際は、複数の方法を併用すると、市場価格や顧客目線も踏まえた価格設定がしやすくなります。注意点や原価率を抑えるコツも参考に、最適な価格を設定し売上アップを目指しましょう。
※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比
※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月