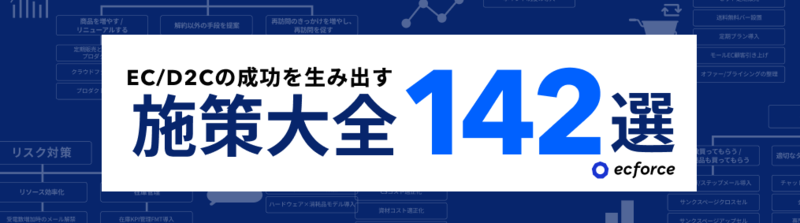この記事でわかること
※この記事は 時点の情報をもとに執筆しています。
通販サイトを始める際、どうしても注目されやすいのは「初期費用」ですが、実は継続的にかかるランニングコストこそが、利益を大きく左右する要素です。
サーバー代、決済手数料、広告費、配送費、人件費。通販サイトの運営にはさまざまな費用がかかり、それらを正確に把握できていないと、「商品は売れているのに利益が出ない」という事態にもなりかねません。
本記事では、通販サイト運営に必要なランニングコストを体系的に整理し、構築方法ごとの費用の違いや、コストを抑えるための具体策までわかりやすく解説します。
初心者の方はもちろん、すでに通販ビジネスを展開している方の見直しにも役立つ内容です。
関連するテーマについては、下記の記事もぜひチェックしてみてください。
ECサイトとは?種類や仕組み・メリットと主要なECサービス一覧
【5ステップ】ネットショップを立ち上げよう!おすすめのツールや開業を成功させるためのポイント
通販サイトのランニングコストとは?初期費用との違いも解説

通販サイトを立ち上げる際、多くの方が初期費用に注目しがちですが、実際に運営を始めると毎月継続して発生するランニングコストの存在がより重要になります。
このパートでは、ランニングコストの基本的な定義から、初期費用との違い、そしてなぜその把握が通販ビジネスにおいて欠かせないのかについて解説します。
ランニングコストとは?
ランニングコストとは、通販サイトの運営にあたって毎月または定期的に発生する継続的な費用のことです。
主な項目には以下のようなものが挙げられます。
- サーバー・ドメイン代
- カートシステム利用料
- 決済手数料
- 配送費・梱包材費
- 広告費
- コンテンツ制作費
- 外注費・人件費
これらはサイトを動かし続けるために不可欠であり、売上に関係なく発生する費用も多いため、適切な管理が必要です。。
ランニングコストと初期費用の違い
ランニングコストと対になるのが初期費用(イニシャルコスト)です。
初期費用はサイトを立ち上げる段階で一度だけ発生するもので、たとえば以下のような項目があります。
- サイト制作費(デザイン、構築)
- システム初期導入費
- 商品撮影・登録代行費
- 初回在庫の仕入れ
対してランニングコストは、サイト公開後に継続して発生する費用です。
金額が比較的小さくても、月単位・年単位で見れば初期費用を上回るケースも珍しくありません。
なぜランニングコストの把握が重要なのか?
通販サイトで安定した利益を上げるためには、「売上を伸ばす」だけでなく、「コストを抑える」視点が欠かせません。
とくにランニングコストは気づかないうちにじわじわと利益を圧迫していく性質を持っています。
たとえば次のようなケースがよくあります。
- 決済手数料だけで毎月売上の5%が消える
- 配送費や梱包費が原価を超えている
- 利用していない機能のために高額なカートシステム費を払い続けている
これらは全体像を見てはじめて発見できるムダです。
だからこそ、ランニングコストの内訳を正しく把握し、戦略的に見直すことで、通販ビジネス全体の利益体質を改善することが可能になります。
通販サイトで発生する主なランニングコスト一覧

通販サイトの運営では、どの事業者にも共通して発生する基本的なランニングコストがいくつか存在します。
こうした費用は固定的に発生するものが多いため、見落としたまま運営を続けると、利益を圧迫しやすくなります。
このセクションでは、通販サイトにおいて代表的なランニングコストの内訳を整理し、それぞれの役割と注意点を解説します。
サイトインフラに関わるコスト(ドメイン・サーバー・SSL)
通販サイトの運営には、最低限のインフラとしてドメイン・サーバー・SSL証明書が必要です。
これらは毎年または毎月発生する基本的な固定費で、特別な機能がなくても必ず発生する支出です。
特にSSL証明書は、個人情報やクレジットカード情報を扱う通販サイトでは導入が必須です。
無料SSLもありますが、企業サイトとしての信頼性やサポート面を考慮すると、有料プランを選択する事業者も多く見られます。
販売処理・決済関連のコスト(決済手数料・カート利用料)
商品の受注から決済までを処理するには、ECカートと決済サービスの導入が必要です。
カートシステムは、月額利用料を支払うことで、商品管理・注文管理・在庫連携などの機能が提供されます。無料プランもありますが、機能制限や手数料が高くなる場合があります。
決済手数料は売上に応じて発生する変動費で、主要な決済手段を導入するたびに発生します。
売上が伸びるほどコストが増加するため、将来的な利益率への影響も踏まえて契約内容を選ぶ必要があります。
物流・商品提供にかかるコスト(配送・梱包・撮影費)
商品を顧客へ届けるためには、梱包資材・発送作業・配送業者との契約といった物流関連の費用が発生します。
商品のサイズや出荷量によっても費用は変動し、送料をすべて事業者側で負担する場合は利益圧迫につながるため注意が必要です。
あわせて、通販サイトでは商品画像が購入判断に大きな影響を与えるため、高品質な商品写真を外注で制作する場合は、撮影・編集にかかる費用も見込む必要があります。
運営体制に関するコスト(人件費・外注費)
サイト運営では、受注確認、顧客対応、商品登録、コンテンツ更新など、日常的な業務が多数発生します。
これらを社内で行う場合は人件費が、外注する場合は業務委託費がランニングコストとして発生します。
とくにカスタマーサポートやコールセンター業務は、繁忙期に対応件数が急増することもあるため、あらかじめ業務量の見積もりと費用の上限設定を行っておくと安心です。
外注と内製のバランスを取りながら、コスト効率を最適化していく視点が欠かせません。
このように、通販サイトのランニングコストは、サイトの公開と同時に自動的に発生し続けるものばかりです。
事前に内訳と金額感を把握しておくことで、利益率の確保や無駄な支出の防止につながります。
通販サイトで発生する主なランニングコスト一覧表
| 費用項目 | 年間目安 | 説明 |
|---|---|---|
| ドメイン代 | 500〜6,000円 | サイトのアドレス取得・維持にかかる費用。 |
| サーバー費用 | 500〜10,000円 | サイト公開に必要なインフラ。プランにより変動。 |
| SSL証明書 | 10,000〜90,000円 | 顧客情報を守るための通信暗号化。 |
| 決済手数料 | 売上の3〜5% | クレジットカード・コンビニ決済等で発生。 |
| カートシステム利用料 | 月額3,000〜100,000円 | EC機能を提供するシステムの使用料。 |
| 配送・梱包費 | 商品1件あたり400〜2,500円程度 | 商品の発送・資材・保管にかかる費用。 |
| 商品画像撮影費 | 案件ごとに変動(10万円〜) | 高品質な商品画像作成を外注する場合の費用。 |
| 人件費・外注費 | 月数万円〜数十万円 | 運営作業や問い合わせ対応などにかかる人的コスト。 |
構築方法別に見る通販サイトのランニングコスト比較
通販サイトを構築する方法によって、かかるランニングコストは大きく異なります。
システム選定は初期費用だけでなく、運用フェーズにおけるコストや業務負担にも直結するため、長期視点での比較が欠かせません。
このセクションでは、代表的な構築方法5種を取り上げ、それぞれの特徴とランニングコストの目安を整理します。
ECモール型
ECモール型は、楽天市場やAmazonのような既存の大規模ショッピングモールに出店するスタイルです。
初期費用がほとんどかからず、すぐに商品販売を始められる手軽さがある一方、月額利用料や売上に応じた販売手数料が継続的に発生します。
とくに手数料は売上の数%から最大15%前後になることもあり、想定より利益が残らないケースも少なくありません。
また、モール側が定める仕様に沿って運営する必要があるため、カスタマイズの自由度が低く、独自性のあるブランディングやサイト設計には限界があります。
ASP型
ASP型は、クラウド上で提供されるECサイト構築サービスを利用する方法で、比較的低コストでスピーディにサイトを立ち上げられます。
月額費用はプランによって異なりますが、機能が豊富なプランになると1万円以上かかる場合もあります。
無料プランが用意されていることもありますが、商品登録数や決済機能に制限があることが多いため、成長フェーズに合わせて有料プランへの移行が前提となります。
カスタマイズの自由度はやや制限されますが、テンプレートや外部アプリを活用することで一定の柔軟性は確保できます。
小規模事業者や個人ECの立ち上げに適した選択肢です。
パッケージ型
パッケージ型は、業務用に設計されたEC構築ツールをベースに、個別カスタマイズを加えてサイトを構築する方式です。
初期費用は50万円以上が一般的で、機能追加や外部連携の柔軟性が高く、中〜大規模事業者に多く採用されています。
ランニングコストは、月額利用料に加えて保守費用やシステム改修費が発生しやすく、継続的な投資が前提となります。
ただし、業務効率化や顧客管理、マーケティング機能まで含めて一元化できることから、安定した運用とスケーラビリティを重視する企業に適した選択肢です。
オープンソース型
オープンソース型は、無料で公開されているECサイト構築ソフトウェアをベースに、独自カスタマイズを加えて運用する方法です。
初期費用は抑えられる反面、自社内での開発・保守が必要になるため、技術力や運用体制が求められます。
ランニングコストとしては、ホスティング費用、セキュリティ対策、システムアップデートなどがあり、内製か外注かによって費用の振れ幅も大きくなります。
柔軟な構成を目指す中小企業や、技術力をもつチームに向いている方法です。
フルスクラッチ型
フルスクラッチ型は、ゼロからすべてを自社開発する方式で、業務フローや顧客体験などあらゆる部分を完全に最適化できます。
ただし開発期間は長期にわたり、初期費用は数百万円〜、ランニングコストも人件費や運用体制によって高額になります。
この構築方法は、独自性の高いサービス展開や大規模なトラフィック処理が求められる企業でのみ現実的な選択肢となります。
長期的視点での投資対効果と、内製体制の有無を慎重に検討する必要があります。
構築方法別に見る通販サイトのランニングコスト比較表
| 構築方法 | 初期費用の目安 | 月額費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ECモール型 | 無料〜10万円 | 数千円〜10万円 | モールの集客力を活用。販売手数料が高め。 |
| ASP型 | 無料〜数十万円 | 数千円〜10万円 | 導入しやすく、機能は限定的。 |
| パッケージ型 | 50万円〜 | 月額5万〜100万円 | 拡張性と保守性が高い。中〜大規模向け。 |
| オープンソース型 | 数十万〜数百万円 | 月額数万円〜 | 自由度が高く、技術リソースが必要。 |
| フルスクラッチ型 | 500万円〜 | 月額50万〜100万円 | 完全自社仕様。開発・運用負荷が大きい。 |
必要に応じて発生するランニングコスト
通販サイトの運営にかかるコストは、基本的な固定費だけではありません。
事業のフェーズや戦略によっては、必要に応じて追加で発生する費用もあります。
こうしたコストは見落とされやすいものの、売上拡大やブランド価値向上に直結する重要な投資でもあります。
このセクションでは、運営状況に応じて発生する代表的なコスト項目とその考え方について整理します。
デザイン費用
ECサイトの印象やユーザー体験を大きく左右するのがサイトデザインです。
テンプレートでは表現しきれないブランドの世界観や独自性を打ち出したい場合、外部デザイナーや制作会社に依頼することで、トップページや商品詳細ページ、バナー、LPなどをカスタマイズする費用が発生します。
デザイン費は一度きりで済む場合もありますが、定期的なキャンペーン更新やUI改善を行う場合には、ランニングコストとして年間数十万円単位の予算が必要となるケースもあります。
特に競争の激しい市場では、UI/UXに対する投資がコンバージョンに直結することもあり、効果的なデザインへの継続的な支出はコストというより「売上アップのための投資」と捉えるべきです。
広告費
短期間で集客を増やしたいとき、最も即効性があるのが広告出稿です。
リスティング広告、SNS広告、アフィリエイト広告など様々な媒体がある中で、どの施策にいくら投資するかは自社の目標に応じて調整が必要です。
広告費は変動費であり、月数万円から数百万円まで規模感は大きく異なります。
ただし、CPA(顧客獲得単価)やROAS(広告費用対効果)といった指標を明確に持ち、施策ごとのパフォーマンスをモニタリングすることで、無駄な広告出稿を避けることが可能です。
競争が激化している現在のEC市場では、広告費ゼロで売上を作るのは難しいのが実情です。
継続的に売上を伸ばしていくには、広告費の最適化と成果測定をセットで行うことが求められます。
外注費
社内リソースが限られている場合や、専門性の高い業務に対応するために、運営の一部を外部に委託するケースも少なくありません。
たとえば、カスタマーサポート、受注処理、商品登録、メルマガ配信、広告運用などが該当します。
外注費は、委託する業務の内容や作業量によって大きく変動します。
月に数万円〜数十万円で収まる場合もあれば、業務範囲が広い場合には数百万円を超えるケースも少なくありません。
たとえば、ECサイトの制作代行では3万円〜150万円程度が相場となっており、Webデザイン会社に対してマーケティング戦略の立案からページ更新、受注処理まで一括で依頼する場合は、100万円を超えることも十分にあり得ます。
また、料金体系もさまざまで、月額固定型なら数万円〜30万円程度が目安です。
成果報酬型であれば売上の5〜10%前後が課金対象となり、複合型の場合は「月額固定費+売上の5〜10%」といった形式になることもあります。
そのため、外注費は一律で見積もることが難しく、自社の規模や委託範囲に合わせて都度確認・調整していくことが重要です。
人件費を抑えたい場合や、短期間で業務を立ち上げたいときに有効な手段ですが、委託先のクオリティや契約内容の見直しを怠ると、成果が出ないまま費用だけが発生してしまうリスクもあります。
必要に応じて相見積もりを取りながら、外注コストの妥当性や内製化とのバランスを定期的に検討することが重要です。
このように、通販サイト運営においては、事業フェーズや戦略によって追加的に発生するコストも少なくありません。
重要なのは、これらのコストを目的別に分類し、費用対効果を見ながら投資判断を行う視点です。
ランニングコストを最適化する方法
通販サイトの利益率を高めるためには、ランニングコストの最適化が欠かせません。
単に費用を削るのではなく、自社にとって本当に必要な支出とそうでないものを見極め、無駄なく効率的な運営体制をつくることが重要です。
このセクションでは、コスト最適化に有効な5つの視点を紹介します。
ECプラットフォームの見直し
現在使っているECプラットフォームが、自社の規模や売上に見合っているかを定期的に見直すことが大切です。
例えば、高機能なパッケージ型サービスを契約しているにも関わらず、その機能の多くが未使用である場合、過剰なランニングコストが発生している可能性があります。
一方で、低価格のASP型を使いながらも複数の外部サービスを併用している場合は、結果的にコストが割高になっているケースも見られます。
プランのグレード変更や、別サービスへの移行も視野に入れ、自社にとって最適なプラットフォームを選び直すことで、無駄な支出を削減できます。
決済手数料の最適化
決済手数料は売上に対して必ず発生するため、累積すると大きなコストになります。
まずは現在契約している決済代行会社の手数料率を確認し、他社と比較することで交渉の材料を持ちましょう。
取扱高が増えてきた段階であれば、ボリュームディスカウントの対象となる場合もあり、条件を見直す余地があります。
また、手数料の高い決済手段に偏らないよう、銀行振込やコンビニ払いなど手数料が比較的低い手段の導入・促進も有効です。
利用率の低い決済手段を絞り込むことで、運用コストの削減にもつながります。
広告費の効率化
広告費は通販ビジネスにおいて重要な集客手段ですが、管理を怠るとすぐに利益を圧迫します。
大切なのは、費用をかけることではなく「どの広告が、どれだけ売上につながっているか」を把握することです。
ROAS(広告費用対効果)やCPA(1件あたりの顧客獲得単価)といった指標を活用し、効果の高いチャネルに絞って予算を集中させることが、最も効率的な方法です。
リスティング広告・SNS広告・ディスプレイ広告など、それぞれの特性に応じて使い分けることで、同じ予算でもより多くの成果を得ることができます。
また、中長期的にはSEOやSNS運用など、オーガニック流入を強化する施策にシフトしていくことも広告費依存の脱却に有効です。
物流コストの削減
商品の発送や梱包、保管にかかるコストも、事業規模が大きくなるほど無視できない負担になります。
まずは、商品のサイズや重量を見直し、無駄な梱包資材やスペースを減らす工夫をしましょう。標準化されたサイズの箱を使うことで、資材費・作業効率の両面でコストダウンが可能です。
次に、配送業者との契約条件を定期的に見直すことも重要です。発送件数が増えていれば、送料の単価交渉が可能になる場合があります。
地域別の業者使い分けや営業所持ち込み割引なども、条件次第で活用できます。
さらに、過剰在庫による保管費用や廃棄ロスも含めて見直し、在庫回転率を高めることでトータルの物流コストを圧縮できます。
外注費の見直し
業務委託や外注サービスを利用している場合は、そのコストが実際の効果に見合っているかを定期的に精査する必要があります。
契約が長期間固定化していたり、業務範囲が変わっているのに費用が変わっていないような場合には、無駄な支出が含まれている可能性があります。
外注先を変更する、相見積もりをとる、または一部業務を内製化するなど、業務の再設計を含めた見直しを行うことで、コスト最適化を実現できます。
ただし、安易な内製化は人的コストや教育負担を生むため、シミュレーションを行ったうえで判断することが重要です。
売上に対する適正なコスト割合とKPI設定
ランニングコストの削減や最適化に取り組むうえで、「どの程度の費用をかけるのが適切か」「そのコストが妥当かどうかをどう判断するか」といった基準を持っておくことが重要です。
単に費用を減らすだけでは、サービス品質や売上を損ねるリスクもあるため、売上とのバランスをもとに判断基準や評価指標(KPI)を設けておくことが長期的なEC運営の鍵となります。
このセクションでは、コスト割合の考え方と、KPIを使った管理手法について具体的に解説します。
適正なコスト割合(経費率)とは?
ECサイトにおけるコスト管理の出発点は、「売上に対してどれだけコストをかけてよいのか」という基準づくりです。
一般的に、物販ECにおける営業利益率の目安は10〜20%前後とされており、売上に対する総コスト(原価+販管費+ランニングコスト)の割合を80〜90%以内に収めることが理想とされています。
よく使われる指標として「3:3:4の法則」があります。
これは、売上のうち「30%を原価」「30%を広告費・販売促進費」「40%をその他経費+利益」に収めるという考え方で、通販ビジネスの粗利構造をわかりやすくモデル化したものです。
この40%の中には、サーバー費用や人件費、システム利用料、物流費などのランニングコストが含まれます。
商材によっては「1:5:4」など販促費を厚く取る戦略もありますが、どのようなモデルでも利益が残る構造を維持できているかどうかが重要です。
各コスト項目の比率をチェックする
経費の総額だけでなく、「どの項目に、どれだけ使っているか」を把握することが重要です。
具体的には以下のような項目について、売上に対する比率を計算し、過去実績や業界平均と比較します。
- 決済手数料(3〜5%が目安)
- サーバー・ドメイン費用(1%未満)
- カートシステム利用料(1〜3%)
- 広告費(15〜30%、商材によって変動)
- 物流費(商品価格の5〜15%)
- 人件費・外注費(5〜10%)
これらの比率が極端に高い項目がある場合、改善余地がある可能性があります。
例えば、広告費が売上の40%を超えているのにリピート率が低い場合は、LTVが見合っていない可能性があります。
長期的なコスト計画の立て方
KPI(重要業績評価指標)を活用することで、ランニングコストを定量的に管理することができます。
単に高い or 安いではなく、「目標に対してどうか」「改善できているか」といったPDCAを回せるようになります。
主なKPIの例は以下の通りです。
- 経費率(販管費 ÷ 売上高):◯%以内に抑える
- ROAS(広告費用対効果):300%以上を目標に
- CPA(顧客獲得単価):◯円以内
- 出荷1件あたりの物流費:◯円以下
- 問い合わせ1件あたりの人件費:◯円以内
- 在庫回転率:◯回以上をキープ
こうしたKPIを部門や施策ごとに設定し、月次・四半期ごとに進捗を確認することで、過剰支出や無駄な投資を未然に防ぐことができます。
コスト評価にLTVの視点を取り入れる
単発のコスト評価ではなく、顧客のLTV(顧客生涯価値)を軸にした判断も重要です。
たとえば、初回購入で利益が出なくても、その後のリピート購入や定期購入によって回収できるモデルであれば、広告費や外注費を高めに設定しても問題ありません。
LTVとCPAのバランスを見ながら、最終的に利益が残るかどうかを中長期視点で判断することが、ECのスケーラブルな運用には不可欠です。
年間予算と実績のギャップ管理
毎月のコスト管理に加え、年間予算との整合性を取ることも重要です。
特に広告や在庫仕入れなどは月によって偏りが出やすいため、年間で利益を確保するには、月次予算と実績のブレを把握して補正していく必要があります。
売上の見込みと費用のバランスが崩れてきたら、すぐに軌道修正するための体制づくりもコスト管理の一部と考えましょう。
まとめ
通販サイトを運営する上で、初期費用だけに注目してしまうと、継続的に発生するランニングコストの存在を見落としがちです。
しかし、実際にはサーバーや決済、物流、広告、人件費など、日々積み重なっていく費用こそが利益を左右する大きな要因となります。
ランニングコストを適切に管理するには、まず各費用項目の内訳と相場感を把握することが第一歩です。
さらに、構築方法による費用の違いや、売上に対する経費率の目安、KPIに基づいた評価と改善を継続することで、健全なコスト構造を維持できます。
必要な投資と不要な支出を見極めながら、効果的にコストを最適化していくことが、利益を生み続ける通販サイト運営の鍵です。
もし現在のコスト構造に課題を感じているなら、システムや物流、広告運用の見直しから始めるだけでも、大きな改善効果が期待できます。
法人向け通販プラットフォームをご検討の方へ
運営効率と利益率の両立を図りたい方には、EC特化型SaaS「ecforce」の導入もおすすめです。
構築から受注、マーケティング、顧客対応までを一元化できることで、多くの成長ブランドが利益体質への転換を実現しています。
※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比
※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月