この記事でわかること
※この記事は 時点の情報をもとに執筆しています。
ECとはどのような仕組みで、どのようなビジネスモデルが存在するのか。
この記事では、ECの定義や代表的な形態、サイト構築の方法、さらにEC事業を始める際のステップや成功のポイントまで、わかりやすく解説していきます。
ECの定義や種類に加えて、EC化を検討している事業者に役立つ実践的な情報を網羅的にご紹介します。
「EC」の定義とは
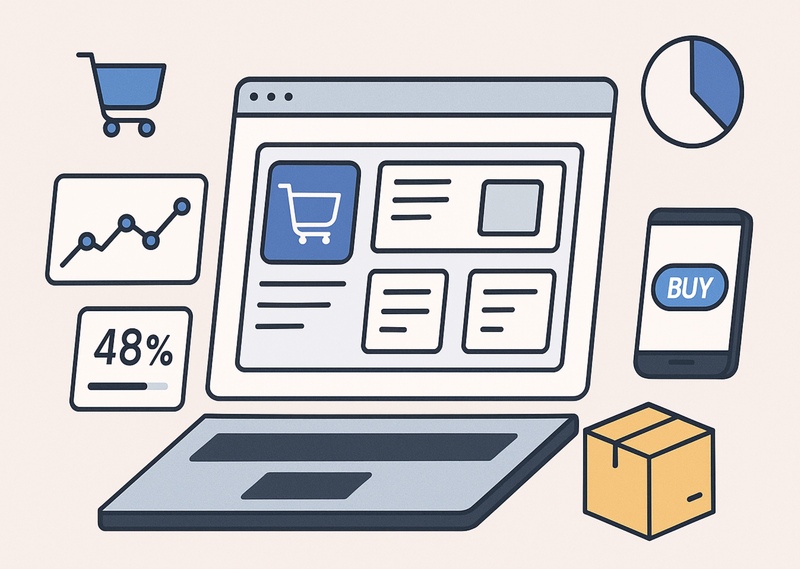
ECとは、「Electronic Commerce(エレクトロニックコマース)」の略で、日本語では「電子商取引」を意味します。
これは、インターネットなどの電子的な手段を通じて行われる、あらゆる商取引を指す広い概念です。
たとえば、オンライン上での商品やサービスの売買、契約、決済などが該当します。
ECはネットショッピングだけでなく、企業間の電子取引や個人同士の取引など、さまざまな取引形態を含んでいるのが特徴です。
ECの主な類型
ECには、取引の当事者や販売経路によってさまざまなビジネスモデルが存在します。それぞれの類型を理解することで、自社に適した展開方法を検討しやすくなります。
一般的にECは、取引を行う主体によって分類されます。たとえば、企業と消費者間の取引や、個人同士、企業同士など、関係性によってモデルが分かれているのが特徴です。
ここでは主要なECの類型について、それぞれの特徴や市場規模もあわせて解説していきます。
※本セクション内の市場規模データは、経済産業省「令和5年度 電子商取引に関する市場調査」(2024年9月25日発表)より引用しています。
BtoC型EC
BtoC型ECとは、「Business to Consumer」の略で、企業が一般消費者に向けて商品を販売する電子商取引の形態です。私たちが普段利用する多くのオンラインショップがこのBtoC型に該当します。たとえば、楽天市場やAmazonなどの大手モール型や、ブランドが展開する公式通販サイトなどが代表例です。
消費者は、時間や場所にとらわれずにインターネットで買い物ができるため、利便性の高い購買体験が可能になります。BtoC市場は年々拡大しており、2023年の日本国内におけるBtoC-EC市場規模は約24.8兆円に達しています。
BtoB型EC
BtoB型ECは「Business to Business」の略で、企業同士が行う電子商取引です。これまで企業間の取引は電話やFAXなどが主流でしたが、近年はインターネットを介したECの導入が進んでいます。
BtoB型ECの市場規模は大きく、2023年には日本国内で465.2兆円となりました。BtoC型ECと比較してもBtoB型ECがいかに企業活動に浸透しているかが分かります。
BtoB型ECの特徴として、企業間取引特有の商習慣に対応するため、取引先ごとの価格設定や承認フローなどの機能が必要になる点が挙げられます。
CtoC型EC
CtoC型ECとは、「Consumer to Consumer」の略称で、個人と個人の間で行われる電子商取引の形態です。
フリマアプリやネットオークションなどがこれに該当します。個人が不要になったモノを他の個人に販売したり、ハンドメイド作品などを個人間で取引したりすることが、CtoC型ECの主な利用方法です。
企業はこれらの個人間取引を仲介するプラットフォームを提供し、手数料などで収益を得ています。
CtoC型ECの市場規模も拡大傾向にあり、2023年には国内で約2.4兆円に達しています。
D2C型EC
D2C型ECとは、「DirecttoConsumer」の略称で、メーカーやブランドが仲介業者を通さず、自社のECサイトを通じて直接消費者に商品を販売するビジネスモデルです。
このecの形態では、間に小売店などを挟まないため、顧客との関係性を直接構築しやすいという特徴があります。
アパレルや化粧品、食品など様々な分野でD2C型ECを展開する企業が増えています。
自社で商品の企画・製造から販売までを一貫して行うため、ブランドの世界観を顧客に直接伝えやすく、熱心なファンを獲得しやすいといったメリットがあります。
越境型EC
越境型ECとは、国境を越えて行われる電子商取引のことです。
日本国内の事業者が海外の消費者向けに商品を販売したり、海外の事業者が日本の消費者向けに商品を販売したりするケースが該当します。
例としては、日本のファッションアイテムやアニメグッズを海外の消費者が購入したり、ヨーロッパの雑貨や中国の最新家電などを日本の消費者が購入したりすることが挙げられます。
越境EC市場は世界的に拡大しており、特に中国やアメリカとの間で取引が活発に行われています。
卸売型EC
卸売型ECは、主にメーカーや卸売業者が小売業者などの法人向けに商品を販売するECのことです。これはBtoB型ECの一種といえます。
多くの場合、卸売型ECサイトは一般消費者が利用できず、取引契約を結んでいる企業のみが閲覧・購入できる会員制サイトとして運営されています。
こうしたサイトでは、必要な商品を効率的に仕入れられるように、大量注文への対応や購入数に応じた価格設定機能などが備えられています。
自社で卸売型ECサイトを立ち上げることも可能で、既存のBtoC向けネットショップに卸販売機能を追加することで、一般顧客と法人顧客の双方に対応できる仕組みにすることもできます。
その他のEC形態
上記で紹介した主要なモデル以外にも、さまざまな形態の電子商取引が存在します。
たとえば、電子チケットの販売や、音楽・動画・電子書籍といったデジタルコンテンツのダウンロード販売などが該当します。
これらは物理的な「モノ」ではなく、サービスや情報といった無形の商品を取り扱うEC形態といえます。
オンライン学習プラットフォームや、月額制のコンテンツ配信サービスなども、広義のECに含まれるケースがあります。
ECの形態は今後も多様化が進んでおり、ビジネスの内容に応じて、最適な形式を選ぶことが重要です。
ECサイトの構築方法
ECサイトを構築・運営する方法には、主に「自社で構築する方法」と「ECモールを利用する方法」があります。
それぞれの手法には、コストや運用の自由度、初期投資、拡張性などの面で特徴や違いがあります。
ここでは、ECサイト構築の代表的な方法について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを比較しながら紹介します。
自社でECサイトを構築する
自社でECサイトを構築する方法とは、企業が独自のドメインを取得し、自社のブランドやビジネスモデルに合わせてゼロからサイトを設計・開発・運営する形態です。
デザインや機能を柔軟にカスタマイズできるため、オリジナルな顧客体験を提供しやすい点が大きなメリットです。
一方で、初期投資や運用コストが比較的高く、ある程度の技術的知識や専門スキルが求められる点には注意が必要です。この自社構築型には、さらにいくつかの手法があります。
ASPを利用する
ASP(Application Service Provider)を利用する方法は、サービス提供企業が用意したプラットフォーム上でECサイトを構築・運営する形態です。
カート機能や決済機能、受注・在庫管理機能などがあらかじめ揃っているため、専門知識がなくても短期間・低コストで導入できる点が大きな魅力です。
ただし、デザインや機能のカスタマイズ性は他の構築手法と比べて制限される場合があります。
パッケージを利用する
ECパッケージを利用する方法は、ECサイトの構築に必要な機能が組み込まれたソフトウェア(パッケージ)を導入し、自社サーバーなどにインストールしてサイトを構築・運営する形態です。
ASPと比較するとカスタマイズの自由度が高く、自社のビジネスモデルに合わせて機能を追加しやすいというメリットがあります。
一方で、ゼロから開発するよりはコストや時間を抑えられるものの、ASPよりは初期費用や運用コストがかかる傾向があります。
クラウドを利用する
クラウドを利用したECサイト構築は、クラウド上で提供されるサービスを活用してサイトを構築・運営する方法です。
自社でサーバーなどのインフラを用意する必要がないため、初期投資を抑えられる点が特徴です。
また、トラフィックの増減に応じて柔軟にサーバーリソースを調整できるため、急なアクセス増にも対応しやすいというメリットがあり、ASPと比較すると、より柔軟なカスタマイズが可能なサービスもあります。
一方で、サービスの仕様や運用ルールに制約があるため、要件によっては思い通りの設計が難しいケースもあります。
オープンソースを利用する
オープンソースを利用したECサイト構築は、無償で公開されているソフトウェアのソースコードを活用して構築する方法です。
ソフトウェアの利用料がかからないため、コストを抑えられる可能性があります。
また、ソースコードを自由に改変できるため、デザインや機能を柔軟にカスタマイズできる点も大きなメリットです。
一方で、システムに関する専門知識が必要であり、セキュリティ対策や機能追加などを自社で行う必要があるため、運用にはある程度の技術力が求められます。
ECモールに出店して販売する
ECモールを利用する方法は、複数のEC事業者が一つのプラットフォーム上に出店して商品を販売する形態です。代表的なECモールとしては、楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングなどがあります。
これらのモールは、既に多くの顧客が利用しており、高い集客力が魅力です。そのため、自社でゼロから顧客を集める手間を省くことができます。
また、モール側がサイト構築や運営に必要なシステムを提供しているため、オンライン販売を比較的容易に開始できます。
一方で、モールに出店する際には、出店料や売上に応じた販売手数料が発生します。さらに、モールの全体的なルールやデザインに制約があるため、自社のブランドイメージを自由に表現しにくいというデメリットもあります。
また、他の出店者との競争も激しくなりがちです。
ECを導入するメリット
EC(電子商取引)の導入は、単なる「商品販売のオンライン化」にとどまりません。
企業にとっては事業拡大やコスト最適化の手段となり、消費者にとっては利便性や選択肢の向上を意味します。
本セクションでは、ECがもたらす代表的なメリットを事業者と消費者、双方の視点から詳しく解説します。
事業者にとってのメリット
企業がECを導入する最大の目的は「売上拡大」ですが、それを支える複数のメリットが存在します。
ここでは、販路・費用・マーケティング・顧客接点といった観点から整理して紹介します。
販路の拡大
ECを導入する最大の利点の一つが、商圏の拡大です。
従来の店舗販売では限られていた地理的な制約を超えて、全国・全世界の消費者に商品を届けることが可能になります。
特に地方の企業や中小規模の事業者にとっては、実店舗を持たずに全国展開を実現できる手段として有効です。
コストの削減
ECでは、実店舗に比べて家賃・人件費・水道光熱費といった固定費を抑えることができます。
加えて、店舗運営に必要な備品や内装などの初期投資も不要となるため、スタートアップや小規模事業者にとって非常に導入しやすいのが特長です。
24時間営業が可能
ECサイトはインターネット上に存在するため、物理的な営業時間に縛られることがありません。24時間365日商品を販売でき、営業時間外の需要にも対応できるため、販売機会を逃しにくくなります。
また、キャンペーンやセールの自動化も行いやすく、業務の効率化にもつながります。
顧客データの活用
ECを通じて取得できる購買履歴やアクセスログは、マーケティング施策の最適化に非常に有効です。
たとえば、ユーザーごとの閲覧行動に基づいたレコメンド機能や、購入傾向を元にしたメルマガ配信など、パーソナライズドな施策を実施することで、顧客満足度の向上やLTV(顧客生涯価値)の最大化を狙うことができます。
顧客接点の増加と信頼構築
レビュー投稿、問い合わせフォーム、チャットサポートなど、ECサイト上には顧客と直接接点を持つ機能が多く備わっています。
こうしたフィードバックの蓄積は、商品の改善やサービス品質の向上に役立つだけでなく、企業と顧客の信頼関係を築く重要な要素となります。
消費者にとってのメリット
ECの普及は、消費者の購買体験にも大きな変化をもたらしています。
時間や場所にとらわれずに買い物ができるだけでなく、比較検討のしやすさや商品の選択肢の多さ、価格面でのメリットなど、実店舗にはない利便性が数多く存在します。
ここでは、ECがもたらす主な利点について、消費者視点で具体的にご紹介します。
時間と場所を選ばない利便性
ECの最大の魅力は、好きな時間に好きな場所から買い物ができることです。
特に忙しい社会人や子育て中の家庭では、営業時間や移動の制約を受けずにショッピングできる点が大きなメリットとなります。
また、スマートフォンひとつで完結できるため、通勤中や休憩時間などのスキマ時間も有効活用できます。
比較検討が容易
ECサイトでは、複数の商品や店舗の価格・機能・レビューを簡単に比較することができます。
その結果、自分に合った最適な商品を選びやすく、より納得感のある買い物が可能になります。
実店舗での購入に比べて「賢く買える」ことが、消費者の満足度を高める要因となっています。
実店舗では買えない商品も手に入る
ECでは、オンライン限定商品やコラボアイテム、海外ブランド、日本未発売の商品なども手軽に購入可能です。
実店舗ではなかなか手に入らない珍しい商品を探しやすいことから、コレクターやファン層にとっても魅力的なチャネルになっています。
お得な購入機会が多い
ポイント還元、セール、クーポンなど、ECならではの販促施策が頻繁に実施されており、消費者はお得に商品を購入できるチャンスが豊富です。
特にタイムセールや期間限定キャンペーンなどは、ECユーザーの購買意欲を高める有効な施策として機能しています。
失敗しないECサイト開設の7ステップ
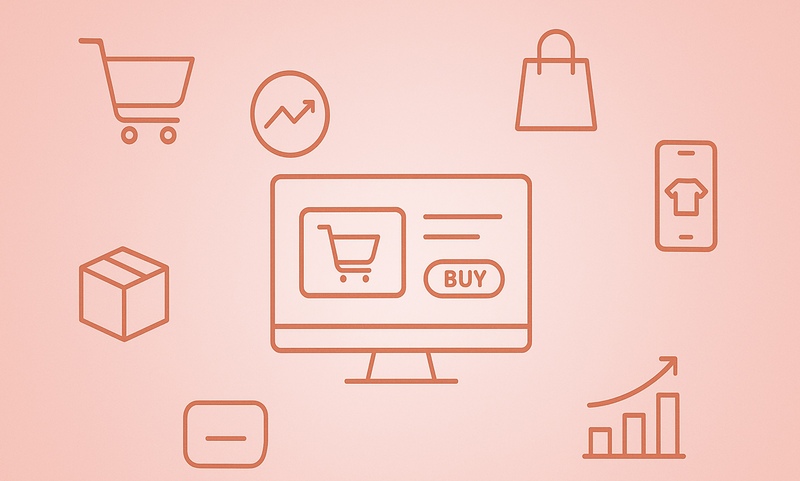
ECサイトを開設するには、いくつかのステップがあります。
場当たり的に進めるのではなく、順序立てて進行することで、スムーズな構築・運用が可能になります。以下では、ECサイト構築の7つの主要なステップについて解説します。
1. 計画を立てる
ECサイト開設の最初のステップは、事業計画をしっかりと立てることです。
どのような商品を誰に販売するのか、ターゲット顧客を明確に定義し、競合サイトの調査や市場分析を行います。
また、ECサイトのコンセプトやデザイン、必要な機能などを具体的に検討します。
事業の規模や予算、目標とする売上などを考慮し、実現可能な計画を策定することが重要です。どのようなサイト形態を選択するのかも、この段階で検討を始めます。
2. サイトの構築方法を選択する
計画に基づいて、ECサイトの具体的な構築方法を選択します。
自社で完全にオリジナルなサイトを構築するのか、ASPやECパッケージを利用するのか、あるいはECモールに出店するのかなど、それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、自社の状況に最も適した方法を選びます。
サイト構築にかかる費用や期間、技術的な要件などを考慮して決定します。
3. ドメインとサーバーを準備する
独自のECサイトを構築する場合は、ドメイン(URL)とサーバーの準備が必要です。
ドメインはブランドイメージやSEOにも影響するため、わかりやすく覚えやすいものを選ぶとよいでしょう。
サーバーは、アクセス数やサイトの規模に応じて適切なスペックを選定し、必要に応じてSSL証明書の取得やセキュリティ設定も行います。
ASPやECモール型ではこのステップが不要なこともあります。
4. 商品を登録して検証する
サイトの構築方法が決まったら、実際にECサイト上に販売する商品を登録していきます。
商品画像の撮影や、いわゆる「ささげ(撮影・採寸・原稿)」と呼ばれる作業(商品説明文の作成や価格設定など)を行います。
商品情報の正確性は売上に直結するため、丁寧に作業することが重要です。
商品登録が完了したら、実際に購入フローを通じてサイトが正しく表示されるか、購入手続きに支障がないかなどの検証も欠かせません。
5. 決済・配送方法を設定する
商品登録が完了したら、決済手段や配送方法の設定を行います。
どの決済サービスを導入するか(例:クレジットカード・コンビニ決済・後払い・キャリア決済など)は、ターゲット顧客のニーズに合わせて選定する必要があります。
また、配送業者や送料設定、納期なども事前に取り決め、システム上で反映させておくことで、ユーザーの購入体験をスムーズにします。
6. 運用体制を整える
ECサイトを安定して運用するには、受注管理・在庫管理・顧客対応など、日常的に発生する業務を滞りなく行える体制が必要です。
問い合わせ対応やクレーム処理、返品対応などに備えて、適切なカスタマーサポートの仕組みも整えておきましょう。
また、社内の担当分担や運用マニュアルの作成もこのタイミングで行うのが理想です。
7. 運用を開始する
ECサイトの準備が整ったら、いよいよ運営を開始します。
集客のためにWeb広告を出稿したり、SNSを活用したり、SEO対策を行ったりと、様々なマーケティング施策を実行します。
注文が入ったら、商品の梱包・発送、顧客への連絡、在庫管理などの業務を行います。
サイトを訪れた顧客の行動データを分析し、サイトの改善点を見つけ、継続的にサイトの改善を行うことが、売上を伸ばす上で重要です。
また、顧客からの問い合わせに対応するカスタマーサポート体制も整える必要があります。
EC事業における課題
EC事業は拡大傾向にありますが、同時にいくつかの課題も存在します。
これらの課題に適切に対応することが、EC化を成功させる鍵となります。
決済方法への対応
ECサイトでは、顧客が利用できる決済方法の多様性が重要です。
クレジットカード決済が最も一般的ですが、それ以外にもコンビニ決済、銀行振込、代金引換、キャリア決済、後払い決済、QRコード決済など、多様な決済方法があります。
顧客は自分の都合に合わせた支払い方法を求めるため、選択肢が限られていると購入を断念してしまう「カゴ落ち」の原因になることも少なくありません。
特に、若年層や高齢層といった特定の年齢層に対応するには、クレジットカードを持っていない層に向けたコンビニ決済や後払い決済の導入を検討することも、お客様目線での利便性向上に寄与します。
幅広い顧客層に対応できるよう、柔軟な決済手段の設計が不可欠です。
決済方法の種類や選び方については、以下の記事でも詳しく解説しています。
オンライン決済、どれを選ぶ?選び方と比較ポイントを徹底解説【導入時のチェックリスト付き】|ecforce blog
セキュリティ対策
ECサイトでは顧客の個人情報やクレジットカード情報などの機密情報を取り扱うため、セキュリティ対策は非常に重要です。
不正アクセスや情報漏洩のリスクは常に存在し、ひとたび事故が発生すると、顧客からの信頼を大きく損なうリスクがあります。
具体的な対策としては、通信の暗号化(SSL/TLS)やファイアウォールの設置、不正アクセス検知システムの導入、定期的な脆弱性診断などが挙げられます。
特にクレジットカード情報の非保持化やトークン化といった対応は、近年のECセキュリティにおいて標準となっています。
安心して利用できるサイト運営のためには、初期構築段階からこれらの対策を講じておく必要があります。
配送と出荷
ECで商品を販売する場合、注文された商品を正確かつ確実に顧客の手元に届けるための配送と出荷の体制構築が欠かせません。
配送は顧客満足度に直結するため、信頼できる配送業者との提携や、効率的な在庫管理体制の整備が重要です。
とくに商品発送が遅延したり、誤配送が起こると、顧客の不満や離脱に直結します。
地域別の送料設定や、販売戦略と連動した配達スケジュール設計など、運用の工夫も求められます。
近年では、置き配や時間指定配送など、顧客のニーズに対応した多様な配送オプションの提供も競争力を高める要素となっています。
返品・クレーム対応の体制整備
商品が到着してからの返品対応やクレーム処理も、ECサイト運営における重要な課題のひとつです。
とくにアパレル・化粧品・食品など、顧客の期待と異なるケースが発生しやすいカテゴリでは、返品ポリシーを明確にし、丁寧な顧客対応を心がける必要があります。
返品受付や返金対応のスピード、代替品発送のスムーズさなども、顧客満足に大きく影響します。
カスタマーサポート体制の整備やFAQの充実などにより、トラブルを未然に防ぐ仕組みづくりが求められます。
まとめ
ECは、単なる「オンラインでモノを売る仕組み」にとどまらず、ビジネスの在り方そのものを変える大きな可能性を持っています。
たとえばBtoCやD2Cのようにブランドと消費者が直接つながるモデルもあれば、BtoBや越境ECのように新たな販路を切り開く形態も存在します。
それぞれの特徴を理解し、自社に最適な方法を選択することが成功への第一歩です。
また、サイトの開設や運営においては、事前の計画立案から商品登録、決済対応、セキュリティ対策、配送体制の構築など、段階ごとに求められる準備と配慮があります。
こうしたステップを一つひとつ丁寧に進めることで、顧客体験の質を高め、長期的な成果につなげることができるでしょう。
今後もEC市場は国内外での拡大が見込まれており、業種・規模を問わず参入のチャンスがあります。
本記事を通じて、ECへの理解を深め、自社ビジネスにとっての最適な形を見つけるきっかけになれば幸いです。
※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比
※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月











