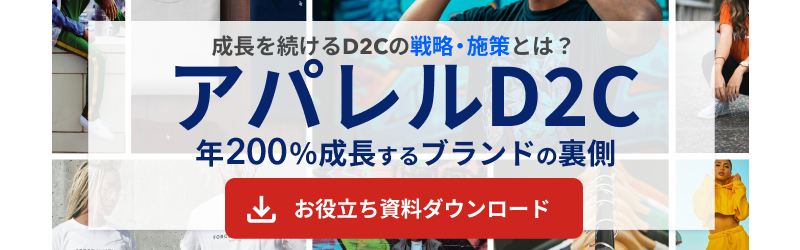この記事でわかること
「コストを抑えて高品質な商品をつくりたい」──そんな企業のニーズに応える手段として、中国OEMが改めて注目されています。
製造大国・中国には、アパレルや雑貨、美容家電など多様なカテゴリのOEM工場が集積しています。
小ロット対応や短納期化も進んでおり、近年では、専用のプラットフォームを活用することで、個人や中小企業でもOEMが実現しやすくなっています。
一方で、工場の選定ミスや品質管理の甘さがビジネスの失敗に直結するケースも少なくありません。
この記事では、OEMとODMの違い、中国OEMの最新市場動向、失敗しないための工場選びや手順、成功するための具体的なポイントまでを網羅的に解説します。
関連するテーマについては、下記の記事もぜひチェックしてみてください。
海外OEMを成功させるためには?手法や注意点を詳しく解説
越境ECとは?メリットや注意点・成功事例まで徹底解説
そもそもOEMとは?ODMとの違いとビジネスモデルの基礎

OEMやODMという言葉はよく耳にするけれど、その違いや仕組みを正確に理解できていない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、OEMの基本的な定義から、ODMとの違い、さらに中国OEMと国内OEMの違いについて、ビジネス初心者にもわかりやすく整理して解説します。
OEMの定義とメリット
OEM(Original Equipment Manufacturing)とは、企業が自社ブランドの商品を外部の工場に製造委託するビジネスモデルです。
商品の企画やデザイン、販売は自社が担い、製造だけを外注することで、コスト削減と効率的な商品展開を実現できます。
【OEMを導入する主なメリット】
- 自社で生産設備を持たずに商品開発が可能
- 少ないリソースでもオリジナル商品を持てる
- 製造コストを抑えながら利益率を確保できる
- 市場ニーズに合わせて柔軟な商品改良が可能
上記のメリットに加えて、とくに中小企業やD2Cブランドにとって、OEMはリスクを抑えながらスピーディに市場投入できる強力な武器となります。
OEMとODMの違い
OEMとよく似た概念に「ODM(Original Design Manufacturing)」があります。どちらも製品の製造を外部に委託するという点では共通していますが、最も大きな違いは「誰が設計・仕様を決めるか」です。
OEMでは、発注側が商品の企画や仕様を決めます。その内容に基づいて、工場が製造を担当します。
つまり、「作りたいものが決まっているけれど製造できない」というケースにぴったりです。
一方、ODMは、工場側が商品の企画・設計・試作までを行います。発注側はその完成品に自社のブランド名をつけて販売します。
「とにかく売れる商品を素早く展開したい」「製品開発のノウハウがない」という場合に適しています。
OEMとODMの主な違い
- OEM:発注者が仕様やデザインを決める
- ODM:工場が仕様やデザインを決めて提案する
- OEM:自由度は高いが、そのぶん手間もかかる
- ODM:手間は少ないが、独自性やブランド設計には限界がある
つまり、「自社のこだわりを形にしたい」のか、「とにかくスピーディーに商品を出したい」のかで、使い分けるのがポイントです。
中国OEMと国内OEMの違い
OEMの委託先を中国にするか日本国内にするかで、製造コストや取引のしやすさに違いがあります。
どちらにもメリット・デメリットがあるため、自社の目的に合った選択が必要です。
まず、中国OEMの強みは、なんといってもコストの安さと工場の多さです。特にアパレルや雑貨、ガジェット系などは、素材調達から組み立てまでを一貫して対応してくれるため、大量生産にも向いています。
世界的な製造拠点であるため、選べる工場の選択肢も圧倒的に多いのが魅力です。
ただし、以下のようなデメリットもあります。
- 距離があるため納期や輸送コストに影響が出やすい
- 言語や文化の違いで意思疎通が難しい場面がある
- サンプルと実物の仕上がりに差が出るケースもある
- 品質管理や検品体制の整備が発注側にも求められる
一方、国内OEMは、以下のようなメリットがあります。
- 工場とのコミュニケーションが日本語でスムーズ
- 品質基準が高く、精度の高いものづくりが期待できる
- 小ロットや短納期にも柔軟に対応してもらえる
- トラブル発生時の対応が迅速
ただし、国内OEMは中国OEMと比較すると製造コストは高めで、対応できるカテゴリや工場数が限られている点がネックです。
つまり、コスト重視・規模重視なら中国OEM、品質重視・管理のしやすさ重視なら国内OEMという棲み分けになります。
中国OEMが注目される理由【メリット編】

なぜ今、多くの企業やEC事業者が「中国OEM」を選ぶのでしょうか?
それは単なるコストの安さだけではなく、ビジネスの成長を加速させる多くのメリットがあるからです。
ここでは、中国OEMを導入することで得られる主なメリットを4つの視点から紹介します。
コスト優位性が高く、利益を確保しやすい
中国OEMは、人件費や原材料費が比較的安いため、製造原価を大きく抑えられます。
その結果、販売価格に対する利益率を高く保ちやすく、スケールアップ時にも価格競争に耐えうる商品設計が可能になります。
同じ仕様の商品でも、日本国内で製造するより中国OEMの方が数十〜数百円単位で原価を削減できることが多く、EC販売においてはこの差が利益を大きく左右します。
販促費や外注コストに予算を回しやすくなる点も含めて、全体的なビジネスの収益構造を健全に保ちやすいのが中国OEMの大きな魅力です。
独自ブランドの商品開発がしやすい
OEMを活用することで、自社オリジナルの商品をゼロから開発できます。
既製品の仕入れ販売ではどうしても価格競争に巻き込まれがちですが、OEMなら自社のブランド戦略に基づいた商品開発が可能です。
「ブランドの世界観に合う素材を使いたい」「差別化できるデザインにしたい」といった要望も、設計段階から反映できるため、競合に埋もれない商品作りが実現できます。
結果として、ブランドの認知や信頼性が高まり、リピート購入やファン獲得にもつながりやすくなります。
戦略的にロングセラーを育てやすい
OEMで作ったオリジナル商品は、他社が簡単にマネできない設計になっているため、長期間にわたって販売を継続しやすい特徴があります。
定番商品としてロングセラー化させたり、バリエーションを追加してシリーズ展開したりと、中長期的な戦略に基づいた商品展開が可能になります。
トレンドに依存せず、安定した収益源を確保したいと考えている事業者にとって、OEMは非常に相性の良い仕組みです。
販売資産としての価値を構築できる
OEMで開発した商品が市場でヒットすれば、それは単なる商品ではなく、「売れる仕組み」としての資産となります。
Amazonや楽天などのプラットフォーム上でレビューや販売実績が蓄積されていくことで、ブランド全体の価値が高まっていきます。
こうした仕組みを持つブランドは、事業売却(バイアウト)や資金調達の際にも高く評価されるポイントになります。
また、一定の仕組み化が進めば、オーナーが現場から離れても売上が上がる「自走型ビジネス」にも発展可能です。
中国OEMのメリットは、単なる製造コストの安さにとどまりません。
オリジナル商品の開発、ブランド構築、長期的な販売展開、そして資産価値のあるビジネスづくりまで、幅広い可能性を秘めています。
こうした強みがあるからこそ、多くの企業がOEMを軸に事業成長を図っているのです。
ところで、EC・D2Cビジネスを総合支援するecforce consultingをご存じですか?
2022年1月時点で50件近くの支援実績があり、有名ブランドを陰で支える知る人ぞ知るサービスです。常に最新のトレンド・情報にアップデートしているので、まずはお気軽にご相談ください。
ecforce consultingへのお問い合わせ
中国OEMの注意点【デメリット編】

中国OEMには多くのメリットがありますが、一方で導入前に知っておくべきリスクや注意点もあります。
コストや納期だけに目を奪われてしまうと、思わぬトラブルにつながる可能性も。
ここでは、よくある落とし穴や想定しておくべきコスト・工数について解説します。
一定の初期費用が必要
中国OEMは製造単価こそ安いものの、初回発注時にはある程度まとまった初期費用が必要です。
多くの中国工場は「最低ロット(MOQ)」を設けており、製造単価が安くても、一定数量をまとめて発注する必要があります。
商品や工場によりますが、1商品あたり50万〜100万円前後の費用が発生するケースも少なくありません。
これには製造費のほか、サンプル費、金型費、輸送費、関税なども含まれるため、トータルの予算感を事前に把握しておくことが重要です。
「とりあえず小さく始めたい」という方は、小ロット対応可能な工場を見つけることがカギになります。
収益が出るまでにある程度の時間がかかる
OEMは、既製品をそのまま販売する仕入れ型ビジネスとは違い、販売開始までに「企画→製造→輸入→販促」のプロセスが必要です。
さらに、初期段階では商品レビューやブランド認知もゼロからのスタートとなるため、販売初期に思うような収益が出ないケースもあります。
以下のような準備段階を経てようやく収益化がスタートします。
- 商品コンセプトの設計
- サンプル制作と修正
- 工場との価格交渉
- 販売ページや広告の準備
- 発売後のレビュー・評価の蓄積
だからこそ、初月から黒字を出すというよりも、「最初の1〜3ヶ月はテスト期間」と割り切り、中長期目線での投資回収を前提に動くことが重要です。
販売開始までの準備工数は多め
OEMはオリジナル商品を開発する分、既存商品を仕入れて売るよりも準備にかかる工数が圧倒的に多くなります。
たとえば、以下のような作業が必要です。
- 商品設計や仕様書の作成
- 複数の工場への見積もり依頼と比較検討
- サンプル確認と修正指示
- 検品体制の確認
- 輸入に関する通関手続き
- 商品ページのライティングと撮影準備
これらはすべて一度やれば終わりというわけではなく、量産体制に入るまでは調整や確認が繰り返されます。
とくに中国との取引は、言語の壁や文化の違いによって想定外のやり取りが発生することも多く、余裕を持ったスケジュールと体制づくりが重要です。
中国OEMには確かに手間や費用のハードルがありますが、それらは事前に把握しておけば、戦略的に乗り越えることが可能です。
短期での収益を期待するのではなく、「半年〜1年でブランドを育てる」という視点で取り組むことで、結果的に大きなリターンを得られるようになります。
中国OEMの始め方と具体的な流れ

中国OEMの開始にあたっては、メリットやデメリットを十分に理解し、具体的な手順を踏むことが重要です。
ここでは、商品企画から販売、そして継続的な改善に至るまでの具体的な流れをステップごとに解説します。
ステップ1|商品アイデアの企画とリサーチ
最初に取り組むべきは、どんな商品を作るのかという企画・設計のフェーズです。
「売れる商品をつくりたい」という想いがあっても、市場のニーズを把握せずに進めてしまうと失敗のリスクが高くなります。
まずは以下のような観点でリサーチを行いましょう。
- 競合商品はどんなスペック・価格帯か
- 商品レビューにある不満点は何か
- SNSやECサイトで人気の商品傾向は?
- どの販路(Amazon・楽天・自社EC)で勝負するのか
この段階でコンセプトが固まれば、次に進む際もぶれずに判断がしやすくなります。
ステップ2|OEM工場(メーカー)の選定
商品企画が決まったら、次は中国のOEM工場を探すフェーズに入ります。
代表的な探し方は以下の3つです。
- 1688.comやAlibaba.comなどのBtoBサイトで検索
- 中国OEMに詳しい代行業者に依頼
- 展示会や貿易商社を通じて紹介を受ける
はじめてOEMを行う場合は、工場探しから交渉、検品や輸送までワンストップで対応してくれる代行業者を使うのが安心です。
工場選定時に必ずチェックすべきポイントは次の通りです。
- 日本企業との取引実績があるか
- 小ロット・カスタマイズ対応が可能か
- 日本語での対応または通訳体制があるか
- 検品・品質管理のフローが明確か
ステップ3|見積もり依頼と価格交渉
工場候補が見つかったら、具体的な仕様書(サイズ・素材・数量・納期など)をもとに見積もりを依頼します。
ここで注意したいのは、見積もり時点であいまいな条件を残さないことです。
曖昧な内容のまま進めると、あとから追加費用や納期遅延につながるリスクがあります。
見積もりは最低でも2〜3社から取り、コスト・対応スピード・レスポンスの質などを総合的に比較しましょう。
可能であれば初回は最小ロットで発注し、様子を見るのも一つの手です。
ステップ4|サンプル商品の確認と修正
見積もりに納得できたら、サンプル品の製作を依頼し、実物を確認します。
ここがOEMの最重要工程のひとつです。写真や仕様書だけでは分からない、「質感」「使い心地」「サイズ感」「色味」などを細かくチェックしましょう。
【チェックポイントの例】
- 仕様通りのパーツ・素材が使われているか
- パッケージ・ラベル・印刷内容に誤りがないか
- 使用上の問題や違和感はないか
- 壊れやすい箇所、組み立て精度に問題はないか
修正が必要であれば、細かくフィードバックを返して納得のいくサンプルが完成するまで妥協しないことが大切です。
ステップ5|量産依頼と輸入準備
サンプルが問題なければ、いよいよ本番製造(量産)を依頼します。
量産に入ると後戻りが難しいため、契約内容や納期、検品方法、納品仕様などを事前に細かく確認・合意しておくことが必須です。
また、この段階から輸入に向けた準備も並行して行いましょう。具体的には以下のような内容です。
- 輸入通関の手続き(HSコードの確認など)
- 国際輸送(航空便・船便)の選定
- 関税・消費税の見積もり
- FBA納品や倉庫配送の調整
初心者のうちは、輸入代行業者や通関業者と連携して進めるのが安全です。
ステップ6|販売の準備(商品ページ・プロモーション)
量産の発注が終わった段階で、商品が届くまでの期間を使って、販売に向けた準備を整えていきます。
とくにEC販売では、商品そのものの魅力だけでなく、「どう見せるか」=ページ作りやプロモーション戦略の質が売上を大きく左右します。
まずは商品ページの制作です。
撮影はスマートフォンでも可能ですが、できればプロのカメラマンに依頼して、商品の魅力を最大限に引き出す写真を用意しましょう。
また、商品説明文は「スペック紹介」だけでなく、ユーザーが使用するシーンやベネフィットを具体的に描写すると購買率が高まります。
そして、SNSやLINE、メルマガなどでの事前告知、広告の配信計画、インフルエンサーとのタイアップなど、事前に販促施策を計画しておくことで、販売開始直後のスタートダッシュに差が出ます。
商品が届いてから慌てて準備するのではなく、届いた瞬間に売り出せる状態にしておくことが理想的です。
ステップ7|販売開始と初期の運用
いよいよ販売スタートです。OEMはここからが本番です。
初期段階では「商品が売れるかどうか」よりも、「どんな人が、なぜ買ったか」「どこに改善点があるか」を見つける期間と捉えることが大切です。
販売初日にアクセスが集中するケースもありますが、多くの場合は反応が鈍いこともあります。
焦らずに初期の売れ行きを観察しながら、広告の出し方や商品ページの表現、価格設定などを少しずつ調整していきましょう。
また、購入者に対しては丁寧なフォロー対応を行い、できる限りレビューを集めていくことが重要です。
レビューはただの星の数以上に、「安心して購入できるかどうか」の判断材料になるため、特に新規の商品においては優先して取り組むべきです。
この段階で得られた初期の反応が、次の改善や拡張の方向性を決める重要なヒントになります。
ステップ8|販売データの分析と改善
商品を販売し始めたら、次に取り組むのは販売実績の振り返りと改善です。
ただ売れて終わりではなく、顧客の声を吸い上げてより良い商品へと進化させることが、OEMビジネスの最大の強みでもあります。
まずは、商品レビューをチェックして、良い点と悪い点の両方を把握しましょう。
「思ったより小さい」「梱包が分かりにくかった」など、ユーザーの声には次回改善につながるリアルなヒントが詰まっています。
また、広告の費用対効果(クリック率や購入率)や、どのチャネルからの流入が多かったかといったデータも重要です。
これらのデータをもとに、商品ページの文言を見直したり、次回ロットで仕様を変更したりすることで、販売効率はどんどん上がっていきます。
販売は「売って終わり」ではなく、「売りながら改善し、さらに売れるようにする」プロセスです。
この改善サイクルを意識的に回すことで、OEM商品は資産として育っていきます。
中国OEMでよく使われる工場探しのプラットフォーム比較3選
中国OEMを始める上で最初の壁となるのが、どの工場に製造を依頼すべきかという点です。
そこで役立つのが、信頼できるOEM工場を検索・比較できるプラットフォームの活用です。
ここでは、実際に多くの企業が利用している主要なプラットフォームを紹介し、それぞれの特徴や違いを解説します。
1688.com
1688.comは、アリババグループが運営する中国国内向けのB2Bプラットフォームです。
製造業者や卸業者が多数登録しており、工場との直接交渉によって低価格な仕入れが可能です。
ただし、日本語や英語には対応しておらず、中国語でのやり取りが前提のため、日本の企業が利用する際は輸入代行業者を通すのが一般的です。
サイト内では「実力商家」や「スーパー工場」など、工場の信頼性を示すマークが表示されており、これを参考に仕入れ先を選定することが推奨されています。
Alibaba.com
Alibaba.comは、グローバル展開向けに設計されたB2B取引プラットフォームです。
中国をはじめ世界中のサプライヤーが登録しており、多くの工場がOEM・ODM製造に対応しています。
公式には「Verified Supplier(認証済みサプライヤー)」や「Onsite Check(現地確認済み)」などのラベル表示があり、信頼性のある企業を見分けやすくなっています。
さらに、一部の工場は動画による工場紹介や生産ラインの可視化も提供しており、海外バイヤーにとっての使いやすさが年々向上しています。
Made-in-China.com
Made-in-China.comは、中国製造業を専門に取り扱うB2Bマッチングサイトで、OEM・ODM製品に特化したカテゴリが豊富に用意されています。
商品ジャンルや対応ロット数など、詳細な絞り込みが可能で、初めてのOEM利用にも適した設計です。
各製造企業のページには、企業規模・輸出国・生産能力・品質認証などの情報が細かく記載されており、比較検討しながらパートナーを選ぶことができます。
出典:Made-in-China.com公式サイト|Focus Technology Co., Ltd.
中国OEMを成功に導くためのヒント

中国OEMはコストやスピード面で優れた選択肢ですが、成功させるためには工場の見極めや準備体制においていくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
ここでは、実際の発注や運用の際に役立つ判断基準を紹介します。
日本企業との取引実績がある工場を選ぶ
はじめてOEMを依頼する際は、工場の信頼性が最も重要です。
なかでも、日本企業との取引実績がある工場は、品質基準や納期の意識が高く、日本市場向けの感覚を理解している可能性が高いため安心です。
中国と日本ではビジネスマナーや製品に対する感覚に違いがあり、これを理解していない工場では「細かすぎる指示が伝わらない」「仕上がりのクオリティに差が出る」といったトラブルに繋がりかねません。
製品ページや工場の公式情報で「Japan experience(日本との取引経験)」などが記載されているか、代行業者を通じて確認しておくと良いでしょう。
最初は最小ロット数で見積もりを行う
初回から大きな数量を発注してしまうと、万が一商品に不備があった場合、大きな損失に繋がる可能性があります。
そのため、まずは最小ロットでのテスト製造から始めるのが鉄則です。
小ロット対応を行っている工場であれば、初期コストを抑えながら製品クオリティの確認や市場の反応をテストできます。
また、小ロットからスタートして信頼関係が築ければ、次回以降のロット単価の交渉や納期短縮にもつながります。
価格交渉の前提として「最低注文数量(MOQ)」をあらかじめ確認し、柔軟な対応が可能な工場を選びましょう。
可能であれば現地で直接確認する
実際に現地へ足を運び、工場の生産体制や作業現場を自分の目で確認することは、最も信頼性を高める方法の一つです。
特に製品に細かいこだわりがある場合や、継続的な取引を見据えている場合は、初回だけでも現地訪問を検討する価値があります。
設備の清潔さ、作業員のスキル、検品の方法、梱包体制など、Webや資料だけではわからない部分が明確になります。
また、現地視察を通して担当者との信頼関係が深まり、コミュニケーションが円滑になる効果もあります。
優秀な通訳・仲介者を確保する
中国とのやりとりでは、言語の壁による誤解がトラブルの原因になることも少なくありません。
とくに製品仕様や細かいニュアンスを伝える場面では、精度の高い通訳が必要です。
単なる翻訳ではなく、製造工程や製品知識も理解したうえで橋渡しをしてくれる「ビジネス通訳」または信頼できる代行業者を確保しておくことで、やりとりの精度とスピードが格段に上がります。
担当者が変わるリスクも考慮し、1人に依存せず複数の連絡経路やサポート体制を準備しておくのが安心です。
代替可能な工場を用意しておく
中国OEMでは、一社依存のリスク回避も非常に重要です。たとえば以下のようなケースが現実に発生します。
- 原材料価格の高騰による急な値上げ
- 突然の工場閉鎖や生産ライン停止
- 担当者の変更で品質が不安定になる
これらのリスクに備え、あらかじめ代替可能な工場を2〜3社程度確保しておくことをおすすめします。
発注先の選択肢を複数持っておけば、交渉面でも優位に立ちやすく、納期調整や価格改善にも柔軟に対応できます。
中国OEMは高いポテンシャルを持つ一方で、事前準備や相手選びを間違えると、想定外のトラブルにつながります。
だからこそ、信頼できる工場選定、テストロットでの検証、通訳・代行の確保など、基本的な体制を整えておくことが成功の鍵です。
中国OEMのおすすめ商品カテゴリー
OEMはどんな商品ジャンルでも活用できますが、製造コストや市場ニーズを踏まえると、特に中国OEMと相性の良いカテゴリーがいくつか存在します。
ここでは、これからOEMを始めたい方に向けて、トレンド性・利益率・小ロット対応のしやすさなどを考慮した、おすすめのカテゴリーを紹介します。
アパレル
アパレルは、中国OEMの代表的なジャンルのひとつです。
中国は世界最大級の繊維・縫製拠点を持っており、生地の調達から縫製、プリント、刺繍まで一貫して対応できる工場が数多く存在します。
Tシャツやパーカーなどのベーシックアイテムから、ワンピース・セットアップなどのトレンド商品まで対応の幅が広く、小ロットにも応じてくれる柔軟な工場も多いため、初心者にも取り組みやすいジャンルです。
季節ごとの需要変動があるため、短サイクルで商品を回せる体制が構築できれば、売り切り型で利益を確保しやすい点も魅力です。
雑貨・アクセサリー
雑貨やアクセサリーもOEMに向いているカテゴリーです。
デザイン性が重視されるため、同じ用途の中でも個性や世界観の表現がしやすく、ブランド価値を付加しやすい特徴があります。
中国には、天然石や合金、レザー、樹脂などさまざまな素材を扱う工場が集まっており、複雑な形状やカラー指定にも比較的柔軟に対応してくれます。
低単価・軽量であるため、輸送コストを抑えられる点もEC販売との相性が良く、薄利多売ではなく高付加価値型のビジネスが構築しやすいジャンルといえます。
美容家電
美容家電は近年、特に注目されているOEM分野の一つです。
中国には電気小型家電を専門とする製造エリアが存在し、フェイススチーマー・美顔器・EMS機器などを製造できる専門工場が豊富にあります。
機能性の高さや最新技術の導入スピードが速く、日本市場でも「中価格帯〜高価格帯」の商品として販売されることが多いため、利益率も高く設定しやすいのが特徴です。
PSE認証やPL保険、検査証明の取得など、法規制や安全基準に注意が必要ですが、しっかり対応できる工場を選べばブランド構築にも適したカテゴリです。
アウトドア用品
コロナ禍以降で市場が拡大しているアウトドア用品も、OEMにおいて有望なジャンルです。
テント、チェア、ポータブル食器、ランタンなど、製造工程の異なるさまざまな製品に対応できる専門工場が中国には集積しています。
アウトドア市場はニッチな需要が多く、ユニークな機能やコンパクト設計、カラー展開などの工夫で差別化がしやすい点も魅力です。
商品サイズが大きくなりがちなため、輸送費・保管費のコスト設計には注意が必要ですが、中価格帯以上の商品が売れやすいため粗利を確保しやすいのも特徴です。
ペット用品
ペット用品市場は近年急成長を続けており、中国でも多くのOEM対応工場が登場しています。
特にペット用ベッド、キャリーバッグ、おもちゃ、グルーミングアイテムなどは種類も豊富です。
この分野は「かわいい・安全・快適」といった感情的な価値が購買動機になるため、OEMによってオリジナリティを出す余地が非常に大きく、ファン化・リピート購入につながりやすいという利点があります。
安全基準や素材選びには十分な配慮が必要ですが、ブランドを構築しやすく、長期的なリピーターを生みやすい点からも注目されています。
OEMでは、「どんな商品を作るか」で成功率が大きく変わります。
重要なのは、自社の得意分野や販売チャネルに合ったカテゴリーを選ぶことです。
そして、差別化できるポイントが明確なジャンルを選べば、価格競争に巻き込まれず安定したビジネス展開が可能になります。
まとめ
中国OEMは、ただの「安く作れる手段」ではなく、商品力・ブランド構築・収益モデルの安定化を実現するための戦略的な選択肢です。
特にECビジネスやD2Cブランドとの相性が良く、スモールスタートからスケールアップまで対応できる柔軟性があります。
一方で、成功のためには工場の選定、コミュニケーションの精度、販売体制の構築など、多くのポイントで計画的な準備が求められます。
ただ発注するだけではなく、自社の強みやお客様への価値をしっかりと商品に反映させる視点があってこそ、中国OEMは大きな成果につながります。
この記事で解説してきたポイントを踏まえ、ぜひ自社に合った商品開発と販売戦略を構築し、長期的にビジネスを育てていく第一歩として活用してみてください。
※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比
※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月