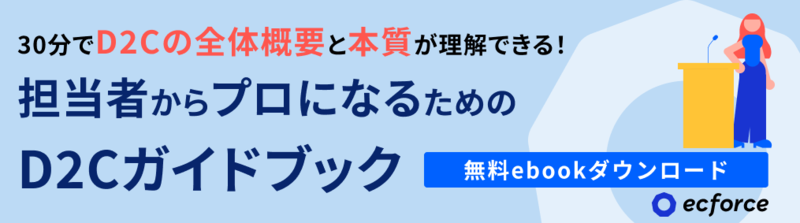この記事でわかること
※この記事は 時点の情報をもとに執筆しています。
OEM(Original Equipment Manufacturing)は、製造を外部に委託しながらも自社ブランドの商品を展開できる、現代ビジネスにおいて非常に有効な手段です。
特に日本では、化粧品や食品、自動車など幅広い業界でOEMが浸透しており、その活用方法や成功事例には多くの学びがあります。
しかし、ただOEMメーカーに依頼するだけでは、継続的な成長や収益にはつながりません。
事業として成功するためには、「どのようにOEM商品を企画し」「どのようなパートナーを選び」「どんなリスクに備えるか」といった視点が不可欠です。
この記事では、OEMの基礎知識から、トレンドを踏まえた最新の業界動向、成功事例、さらには最適なメーカー選びのポイントまでを解説します。OEMを活用して自社ブランドを成長させたい方に向けて、実践的な情報をお届けします。
関連するテーマについては、次の記事もあわせてチェックしてみてください。
【基礎知識】OEM生産のメリット・デメリットを分かりやすく解説
OEMとODMの違いは?選び方やメリット・デメリットを解説
OEMとは?

OEMを成功させる第一歩は、その仕組みを正しく理解することです。
OEMの意味や、ODMやPBとの違いといった疑問を解消し、自社にとって最適な活用方法を考えるための基礎知識を押さえていきましょう。
OEMの定義
OEM(Original Equipment Manufacturing)は、自社ブランドの商品を、他社(メーカー)に委託して製造してもらうビジネスモデルです。
製造を担う側はOEMメーカーと呼ばれ、委託者側のブランド名で製品を生産します。
たとえば、身近な化粧品や食品、自動車部品なども、多くがOEM商品として市場に流通しています。
特に近年は、D2C(Direct to Consumer)モデルの普及により、OEMの需要が急速に高まっています。
OEMは単に「製造を外注する仕組み」ではなく、ブランドの価値を高めるための生産戦略のひとつとして重要視されています。
ブランド側が持つ世界観や顧客理解を、メーカーの技術力で具現化すそれが現代におけるOEMの本質です。
OEMとODM・PBとの違い
OEM(Original Equipment Manufacturing)は、自社ブランドの商品を外部のメーカーに製造してもらう仕組みです。
製品の企画や仕様はブランド側が決め、メーカーはその指示通りに製造を担います。
一方で、ODM(Original Design Manufacturing)は、商品開発のほとんどをメーカー側に任せるモデルです。
ブランド側はざっくりとした方向性を伝えるだけで、設計・処方・試作・製造までメーカーが行います。
特に自動車や電子機器、健康食品など、専門的なノウハウが求められる業界でよく見られます。
また、PB(プライベートブランド)は、主に小売業者が自社名義で展開する商品で、製造はOEMメーカーに委託するものです。
ブランド力のあるスーパーやコンビニが、独自のラインナップを構築する際によく使われています。日本では「トップバリュ」や「セブンプレミアム」などがその代表例です。
これらの違いを整理すると、OEMはブランド側が商品の企画・開発を主導し、製造だけをメーカーに依頼するスタイルです。商品のコンセプトやパッケージにこだわりたい企業に向いています。
対してODMは、商品の設計から製造まですべてメーカーが行い、ブランド側は方向性やターゲット層を伝えるだけという形です。開発リソースが不足している企業やスピード重視で商品を出したいケースで選ばれます。
PBは、小売業者が主導して商品を企画し、自社ブランドとして販売するモデルです。製造は外部に委託しますが、売り場や価格設定をコントロールしやすいのが特徴です。
このように、それぞれの方式には主導する側・関わる範囲・向いている事業形態が異なるため、自社の体制や目指す商品像に応じて、最適なモデルを選ぶことが重要です。
ODMとの違いについては次の記事でも解説しています。
OEMとODMの違いは?選び方やメリット・デメリットを解説
ODMとは?ODMの成功事例やメリット・デメリットを解説
OEMの種類
OEMには主に「ブランド主導型」と「メーカー提案型」の2つの進め方があります。
ブランド主導型OEMは、ブランド側が商品の企画・設計を行い、製造のみをOEMメーカーに依頼する方法です。
たとえば、成分や処方にこだわったスキンケア商品を自社で設計し、OEMメーカーに量産を任せるようなケースが該当します。
この方式のメリットは、ブランドの世界観や差別化ポイントを明確に商品に反映できる点です。
ただし、開発や品質管理などに自社の関与が必要なため、一定の体制やノウハウが求められます。
メーカー提案型OEMは、OEMメーカーがあらかじめ開発した商品を、ブランド側が採用して自社名義で販売する方法です。
トレンドを取り入れた試作品をベースに商品化できるため、スピード感やコスト面に優れています。
ただし、他ブランドと類似商品になりやすく、オリジナリティは出しづらい点に注意が必要です。
自社に合ったOEMのスタイルを選ぶには、「自社は何に強みがあるのか」「どこまで商品づくりに関わりたいのか」を見極めることが大切です。独自性を重視するならブランド主導型、スピードやコスト優先ならメーカー提案型が適しています。
OEMのメリットとデメリット

OEMは、自社で工場や製造ノウハウを持たなくても商品を展開できる強力な手段です。
ただし、便利さの裏には見落としがちな課題も潜んでいます。ここでは、ブランド側の視点から、OEMの利点と注意すべきリスクを整理します。
OEMのメリット
OEMの最大のメリットは、製造に関わるコストや手間を削減できる点にあります。
自社で工場を構える必要がないため、初期投資や人件費、設備管理などの負担を大幅に軽減できます。
たとえば、化粧品や食品のように、製造に専門技術や衛生基準が求められる商材でも、OEMメーカーに委託することで専門知識がなくても参入が可能になります。
さらに、製造工程を持たないことで、企画・販売・マーケティングといったブランド本来の強みに集中できるのも大きな利点です。
また、OEMは小ロット生産や短納期対応が可能なケースも多く、市場テストやD2Cブランド立ち上げ時にも柔軟に対応できます。
需要の変化に応じて生産量を調整しやすいため、在庫リスクの低減にもつながります。
OEMのデメリット
一方で、OEMには外部依存によるリスクも存在します。
製造工程をOEMメーカーに任せている以上、品質トラブルや納期の遅延が発生した際に、ブランド側で即座にコントロールすることは難しくなります。
また、OEMでは製造ノウハウや技術が自社に蓄積されにくいため、将来的に自社開発に移行したい場合や、より高度な商品を展開したい場合に障壁となることもあります。
さらに注意したいのは、OEMメーカーが同様の商品を他ブランドにも供給している可能性がある点です。
差別化の難しさや模倣リスクがあるため、契約段階で製造範囲や供給条件を明確にしておく必要があります。
便利で効率的な仕組みだからこそ、「任せきりにしないバランス感覚」がOEM活用の成功を左右します。
OEMの業界別事例
OEMの注意点3つを踏まえて、業界別のOEMメーカー事例を見ていきましょう。
OEMメーカーによって得意な領域は異なりますが、近年ではOEMメーカーがD2C向けにラボ施設やサービスを始めているケースが見られます。
(1)コスメ業界
カラーコスメの開発・OEM製造を行う株式会社トキワは2021年8月から超高速・小ロットオリジナルコスメブランド開発サービス「TOKIWA KOBO」の提供と開発・生産拠点「APD Lab.」を設立しています。
「APD Lab.」は、品質を維持して小ロット対応を可能にする受託生産事業モデル(アジャイル プロダクト デベロップメント、即時対応型製品開発)専用の開発・生産拠点です。
「TOKIWA KOBO」は、超高速・小ロットオリジナルコスメブランド開発サービスです。
通常5,000個以上の生産ロット対応を最小1,000個から対応する、製品開発にかかる期間を大幅に短縮するなど、D2Cブランド立ち上げ時に押さえるべきロット数や開発期間に関する重要なポイントが分かります。
(参考:「カラーコスメOEM最大手のトキワが埼玉県川口市に市場ニーズへの即時対応を可能にする化粧品開発・製造の専用ラボ『APD Lab.』を新設」)
(2)スキンケア業界
スキンケア化粧品の開発・OEM製造を行う株式会社サティス製薬は2023年4月よりスキンケア化粧品のOEMサービス「WITH BRAND Project」を立ち上げています。
「WITH BRAND Project」は、最小数量100個30万円から商品が作れるサービスです。
相談・試作開発が無料で発注まで費用発生しない点や、成分に関する知識やブランド開発経験がない場合でも専門スタッフが伴走する点から、複数のD2Cブランド立ち上げを支援していることが分かります。
(参考:「個人でもオリジナルのスキンケア化粧品が作れるOEMサービス『WITH BRAND Project』をサティス製薬が開始」)
(3)健康食品業界
健康食品と化粧品の開発・OEM製造を行う株式会社東洋新薬は2022年2月より試作から評価・エビデンス取得までが可能な「クイックラボ渋谷(QLS)」を開設しています。
「クイックラボ渋谷」では専門スタッフとともに健康食品・化粧品の開発試作をし、試作品の確認が可能です。
専門スタッフと一緒に試作を行うことができ、その場で味や色、香り、テクスチャーを確認できます。
原料を豊富に保管しており、希望の素材を配合した粉末品をラボ造粒機にて試作し、色や匂い、味、溶解性などを確かめられます。
また、副素材を配合した複数のタブレットを試作し、崩壊性や硬度なども確認できます。
試作商品の評価やエビデンスの取得以外にも、商品開発の様子を撮影可能であり、D2Cブランドの宣伝素材についても配慮されていることが分かります。
(参考:「【東洋新薬】健康食品・化粧品の試作・エビデンス取得をお客様とともに行う施設『クイックラボ渋谷(QLS)』開設 ーものづくりの過程をコンテンツとして販促・プロモーションにも活用可能ー」)
OEM製造時の注意点
OEMを活用してスムーズに商品化を進めるためには、単に信頼できるメーカーを見つけるだけでは不十分です。
ブランドとして求める品質や納期、コスト感をしっかり守るためには、製造過程においてもいくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
特にEC/D2C企業にとっては、OEMメーカーとの関係性や進行管理のスタイルが、そのまま商品のクオリティやブランド評価に直結します。
ここではOEM製造を進める上で、トラブルを未然に防ぎ、より効率的に開発を進めるための3つの注意点を詳しく解説します。
製造スケジュールは早めに押さえる
OEMメーカーとの取引では、製造スケジュールの確保をいかに早く行うかが成功を左右します。
なぜなら、OEMメーカーの生産ラインには限りがあり、人気商材の依頼が集中すると、希望する時期に製造枠を押さえられなくなることがあるからです。
特に化粧品や食品など、季節やトレンドに合わせた商品展開を行う場合、販促タイミングがずれるだけで売上に大きな影響を及ぼします。
製造開始が数ヶ月遅れることで、企画全体のスケジュールを見直さなければならなくなるケースも少なくありません。
そのため、OEMメーカーとの打ち合わせ段階で、以下の点を明確にしておくことが重要です。
- 初回の製造希望数と納品希望日
- 試作〜承認までの目安期間
- 生産ラインの仮押さえが可能かどうか
こうした情報を早めに共有しておけば、OEMメーカー側もスケジュールを調整しやすくなり、リードタイムの延長リスクを大きく減らせます。
OEMは「依頼したらすぐ作ってもらえる」という単純な仕組みではありません。
事前に動き、製造枠を確保することこそが、安定した商品供給の第一歩です。
とくにD2CやECブランドのようにスピード感が重要なビジネスでは、製造スケジュールの早期確定が成功の鍵となります。
契約・発注に関するエビデンスを残す
OEMでよくあるトラブルのひとつが、「言った・言わない」「そんな内容は聞いていない」といった確認漏れや認識のズレによる問題です。
たとえば「納期は○月末」と口頭で合意していたはずが、メーカー側では「検討中」扱いになっており、希望納期に間に合わなかったというケースも。
こうしたリスクを回避するには、以下のような形でエビデンス(証拠)をしっかり残すことが重要です。
- 発注書を事前に発行する(納期や仕様を明記)
- 可能であれば業務委託契約や製造契約を交わす
- メール・チャットなどで要点の記録を残す
契約書がなくても、メールや発注書ベースでの取り決めでも十分有効です。
特に、最近ではフットワークの軽いOEMメーカーも多く、形式張った契約は不要というケースもありますが、それでも要所は文書化しておくのが鉄則です。
OEMは外注先との商取引ではありますが、もはやパートナー関係といえるほど密接な連携が必要な関係性です。
だからこそ、最初の握り方が後々の信頼とトラブル防止につながります。
見積もりは必ず複数社から取る
OEM製品は、同じような内容であってもメーカーによって価格や納期が大きく異なるのが一般的です。
たとえば、化粧品のように容器やバルクの価格が原価に大きく影響するジャンルでは、仕入れルートや在庫の違いだけで価格に2〜3割以上の差が出ることもあります。
このため、OEM依頼時には必ず複数社から相見積もりを取得することが基本です。
また、見積書を受け取ったら「総額」だけで判断するのではなく、内訳(原料費・容器費・人件費・ラベル代など)を確認し、原価構造を把握することも非常に重要です。
中でも注視したいのは以下の2点です。
- ロット数の違いによる単価変動:ロット数を増やすことで原価を下げられる場合もあります。
- マージン率の高さ:OEMメーカーによって利益率が異なるため、価格の妥当性を見極める視点が必要になります。
健康食品やサプリメントなども、配合成分によって原料コストが大きく変動するため、得意分野のメーカーを見極めることで無駄なコストを省き、利益率を高めることが可能になります。
最初は分からないことも多いですが、見積もりを比較する中で相場感と価格交渉力を自然に身につけることができます。
OEMを戦略的に使いこなすには、このような仕入れの目利き力も必要です。
OEMメーカーと良い関係を築くために
近年、様々なD2C商品が誕生しており、OEMメーカーの需要は高まっています。
つまり現状OEMメーカーは受託数に困っておらず、OEMメーカー側が依頼を断ることができる強い立場になりえるということです。
どのビジネスにも言えますが、相手に対する敬意を忘れずお互い大切なパートナーシップを組める関係になりましょう。
OEMメーカーは自社にはない製造技術を持った企業です。
「OEM=下請け」という考え方は捨てて、丁寧に対話を続けつつ、押さえるべきところは押さえる付き合い方が、円滑に商品を作るポイントです。
EC業界で生き残るためには、他社製品との違いを明確にアピールすることが必要です。
OEMで削減できたコストや時間で企画・販売を強化し、メーカーに常に新たな提案や企画を提出できる努力をしましょう。
メーカーを下請け扱いすることなく、努力と成長を続けることが何より重要です。
メーカーを発注先ではなく「パートナー」として捉える
OEMメーカーは、単にブランドの要望に沿って商品を作るだけの存在ではありません。
むしろ、ブランドの想いや価値を実際の製品として形にする、共創のパートナーです。
しかし実際には、ブランド側がメーカーを「製造をお願いする下請け」として扱ってしまい、関係が一方通行になってしまうケースもあります。
このようなスタンスでは、コミュニケーションがすれ違い、結果的に品質面や納期面でのトラブルにつながりやすくなります。
近年はD2Cや小規模ブランドの参入が増えたことで、OEMメーカーの需要は年々高まっています。
つまり、今やメーカーが取引相手を選べる立場にあるということです。
依頼内容が曖昧だったり、無理なスケジュールを押し付けたりするブランドは、優先度を下げられてしまう可能性があります。
メーカーとの関係を良好に保つためには、「お願いする側」ではなく「一緒に作る側」という意識が大切です。
企画段階からメーカーの意見を取り入れ、試作やコストの調整も協議ベースで進めることで、信頼と連携の強い関係を築くことができます。
信頼関係がより良いモノづくりを生む
メーカーとの信頼関係が深まると、双方の知見を生かしたより良い製品づくりが可能になります。
メーカーは製造現場のプロとして、原料の選定や処方の工夫、コスト削減策など、ブランドが気づかない視点から提案してくれることもあります。
たとえば化粧品であれば、「この成分なら安定性が高く品質が長持ちする」「このパッケージなら小ロット対応がしやすい」など、実務的で精度の高いアドバイスをもらえることがあります。
食品OEMにおいても、製造現場の工夫によって歩留まりが改善され、結果的にコスト削減につながることもあります。
こうした前向きな関係性は、一度の取引で終わらず、次の新商品や別ライン開発への発展にもつながります。
OEMは一方的な委託関係ではなく、ブランドとメーカーが互いの専門性を持ち寄って価値を高める共同開発の形で進めることが理想です。
メーカーを下請けとしてではなく、パートナーとして尊重する姿勢が、最終的にはブランドの信頼や顧客満足度を高める結果につながります。
OEMメーカーの情報収集
自社のコンセプトを実現し、競争力のある商品を生み出すためには、信頼できるOEMメーカーを見つけることが欠かせません。
しかし、数多くのメーカーの中から「品質・対応力・コスト・スピード」を兼ね備えたパートナーを選ぶのは簡単ではありません。
ここでは、実際にOEMメーカーを探す際に役立つ、3つの効果的な情報収集方法を紹介します。
紹介やコンサルティングを活用する
もっとも確実で効率的なのが、信頼できる第三者からの紹介です。
すでにOEM取引のある企業や、ECコンサルティング会社、仕入れ先などに相談することで、自社の商材に合ったメーカーを紹介してもらえます。
たとえば、EC構築やD2C支援を行うコンサルティング企業では、製造から販売までを一貫して支援している場合が多く、商品ジャンルやロットに応じて最適なメーカーを提案してくれます。
また、同業者や既存のパートナー企業を通じて紹介を受けることで、信頼性の高いOEMメーカーとスムーズにつながることができます。
紹介を受ける前に、以下の点を整理しておくとスムーズです。
- 商品のジャンルと求めるクオリティ
- 想定ロット数と販売時期
- 自社が重視する要素(価格、納期、開発スピードなど)
こうした条件を明確にしておくことで、紹介先の精度が高まり、打ち合わせ時のミスマッチを防げます。
展示会や見本市に参加する
OEMメーカーを探すもう一つの有効な手段が、業界展示会への参加です。
化粧品や食品、雑貨など、各業界では年に数回OEM関連の展示会が開催されており、最新の技術・原料・パッケージを一度に確認できます。
たとえば、化粧品業界では「化粧品開発展(COSME Tech)」が代表的で、原料や容器メーカー、OEMメーカーが多数出展しています。
食品業界では「健康博覧会」など、健康食品・機能性素材を扱うOEMメーカーが多く出展しており、新規開発の相談や試作品の確認もその場で可能です。
展示会のメリットは、直接担当者と話せること。ウェブサイトでは分からない製造背景や得意領域、開発姿勢を実際に確認できるため、信頼度の判断材料になります。
参加前には、主催者サイトやジェトロ(日本貿易振興機構)の「J-messe」などで開催情報を調べ、興味のある出展企業をリストアップしておくのがおすすめです。
出典:
化粧品開発展(COSME Tech)公式サイト|RX Japan株式会社
健康博覧会(Health and Beauty Week)公式サイト|インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社
J-messe(世界の見本市・展示会情報)公式サイト|独立行政法人日本貿易振興機構
ベンチマーク商品の製造元を確認する
気になるブランドや競合他社の商品パッケージを観察するのも、OEMメーカーを探す手がかりになります。
特に化粧品や健康食品などは、製造販売元の記載が義務付けられているため、パッケージ裏面を見れば製造元の情報を確認できます。
たとえば、化粧品では「製造販売元:○○株式会社」と明記されており、それがOEMメーカーである場合が多いです。
この情報から企業サイトを調べることで、そのメーカーがどのような分野に強いかを把握できます。
加えて、ベンチマーク商品の成分表や特徴を分析することで、「このレベルの品質を作れるメーカーを探したい」という明確な目標設定にもつながります。
気になるOEMメーカーが見つかった場合は、公式サイトのお問い合わせフォームから直接相談するのが確実です。
最近ではオンライン商談に対応している企業も多く、初回から打ち合わせを行うことも可能です。
OEMメーカーの選定は、ただ「作れるメーカーを探す」ことではなく、ブランドの価値を共有できる相手を見つけるプロセスです。
紹介・展示会・製品調査といった複数の手段を組み合わせ、候補を比較検討することで、自社に最適なパートナーを見つけやすくなります。
景品表示法については、下記の記事を参考にしてみてください。
景表法と特商法、正しく理解し攻めるためのリスクマネジメント
まとめ
OEMは、自社で製造設備を持たなくても商品を展開できる強力な仕組みです。
化粧品・食品・自動車など、あらゆる業界で活用されており、ブランドにとって新しい可能性を広げる手段のひとつとなっています。
しかし、OEMは依頼すれば簡単に作ってもらえるわけではありません。
製造スケジュールの管理、エビデンスの取り交わし、原価構造の把握といった地道な準備と信頼関係の構築が欠かせません。
また、メーカーを下請けではなく、共にブランド価値を形にするパートナーとして捉える姿勢が、長期的な成功につながります。
成功しているブランドは例外なく、OEMメーカーと密に連携し、得意領域や市場トレンドを理解した上で開発を進めています。
そして、そうしたパートナーシップが、結果的に高品質で信頼される商品を生み出しているのです。
OEMの可能性を最大限に引き出すには、「誰に作ってもらうか」ではなく、「誰と一緒に作るか」という視点が重要です。
メーカー選定・情報収集・信頼構築、この3つを丁寧に進めることで、自社ブランドの強みを活かしたOEM展開が実現できます。
あなたのブランドに最適なOEMパートナーを見つけ、理想の商品づくりを一緒に進めていきましょう。
※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比
※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月