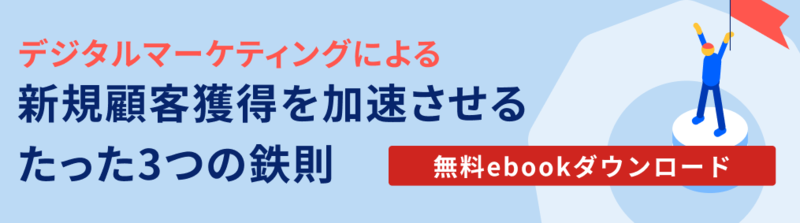この記事でわかること
ライブコマースとは、ライブ配信を使ってリアルタイムに商品を紹介・販売する、新しいスタイルのECマーケティングです。
視聴者と配信者がコメントを通じて直接やり取りできるため、ただ情報を届けるだけでなく、双方向のコミュニケーションを活かした「オンライン接客」に近い体験を提供できるのが特長です。
最近ではアパレルや化粧品、食品といった業界を中心に、多くの企業がライブコマースを取り入れ始めています。
特に中国やアメリカなど海外ではすでに主流の販売手法として定着しており、日本でも今後さらに広がっていくと注目されています。
この記事では、ライブコマースの仕組みやメリット、導入時のポイント、成功事例などを幅広くご紹介します。
関連するテーマについては、次の記事もあわせてチェックしてみてください。
ECサイトの売上を伸ばすマーケティング戦略|集客・CVR改善・リピーター獲得のポイント
UGCとは?マーケティングで注目される理由と活用方法・事例を解説
インフルエンサーマーケティングとは?効果・手法・注意点と成功事例を紹介
ライブコマースとは?

ライブコマースは、「ライブ配信」と「eコマース(EC)」を組み合わせた販売手法です。
リアルタイムの映像で商品を紹介しながら、視聴者とコメントを通じて会話をし、その場で購入につなげられる点が特徴です。
最近ではスマホ1台と無料の配信ツールがあれば誰でも始められるようになり、個人から企業まで導入のハードルが一気に下がりました。
配信者と視聴者がリアルタイムでやり取りできることから、いわば「オンライン接客」に近い感覚で購買体験を提供できるのがライブコマースの魅力です。
ここでは、基本的な仕組みとともに、従来のテレビショッピングとの違いを見ていきましょう。
ライブコマースの3つの特徴
ライブコマースは、よくテレビショッピングと比較されますが、実は大きく異なる点がいくつもあります。
中でも重要なのが「双方向性」「購入のしやすさ」「導入のしやすさ」です。
まず、ライブコマース最大の特長は視聴者とリアルタイムでやり取りできる双方向性です。配信中に寄せられるコメントや質問にその場で答えることで、疑問を即座に解消し、納得感を持って購入してもらうことができます。
次に、購入までのスムーズな導線もポイントです。多くの配信では、画面上に表示された商品リンクをタップするだけで購入ページに遷移できるため、「見てからすぐ買う」という流れをつくることが可能です。
そして最後に、スマホと配信アプリさえあれば始められる手軽さです。テレビショッピングのようにスタジオや撮影スタッフを揃える必要はなく、ECサイト運営者が自ら出演する形でも十分に成立します。
これら3つの特徴は、ライブコマースをこれまでの販売手段と差別化する大きな要素となっています。
ライブコマースの市場規模と将来性
ライブコマースは、世界的に見ても急成長を遂げている注目のマーケティング手法です。
特に中国やアメリカでは、EC市場の一大トレンドとして定着しており、日本国内でもその影響を受けて導入企業が着実に増えています。
ここでは、ライブコマース市場の動向や調査データをもとに、海外と日本それぞれの成長状況や将来性について詳しく見ていきます。
海外で急速に拡大する市場
中国では、ライブコマース市場がここ数年で大きく拡大しており、すでに1つの巨大な産業として定着しつつあります。
たとえば、2023年時点で中国におけるライブコマースのEC浸透率は約37.8%に達していると報じられており、ネットユーザーの多くがライブ配信経由で商品を購入する状況が定着してきました。
また、日本貿易振興機構(JETRO)のレポートによると、中国では国や地方自治体がライブコマースを地域活性化の手段として支援しているケースもあり、今後もこの領域の成長が継続すると予測されています。
さらに、アメリカでもライブコマース導入が進んでおり、Meta社(Instagram、Facebook)やAmazonがショッピング機能を強化するなど、欧米圏でも徐々に存在感を高めています。
出典:
AFPBB News|中国で拡大するライブコマース市場
日本貿易振興機構(JETRO)|中国ライブコマース事情
日本国内における市場の現状と今後の予測
日本でも、ライブコマースに対する関心はここ数年で高まりつつあり、ECを活用する企業の中でも導入を検討する動きが増えています。
矢野経済研究所の調査によると、2025年には動画コンテンツビジネス全体の市場規模が6,300億円に達する見込みであり、その中にはライブ配信アプリやライブショッピングといった領域も含まれていると見られています。
こうした背景には、5Gの普及やスマートフォン利用の一般化に加え、コロナ禍を経て「自宅で商品を詳しく知りたい」という消費者ニーズの高まりがあります。
また、楽天市場・Yahoo!ショッピングなどのモール型ECや、自社ECサイトに導入可能なライブ配信ツールなど、各社が提供するソリューションの進化も、今後の成長を後押ししています。
出典:矢野経済研究所|動画コンテンツビジネス市場に関する調査
企業がライブコマースを導入する5つのメリット

ライブコマースは動画を使った接客という感覚に近く、商品やブランドの魅力をダイレクトに伝えられることから、さまざまな業界で注目されています。
従来のECサイトでは難しかった商品に対するリアルな印象や顧客とのつながりが生まれやすく、売上に直結する成果を期待できる点が大きな強みです。
ここでは、企業がライブコマースを導入することで得られる5つの代表的なメリットについて、具体的に解説します。
商品の魅力や使用感をダイレクトに伝えられる
ライブ配信を通じて、商品そのものの質感や使い心地を視覚的に伝えられる点は、ライブコマースの大きな魅力のひとつです。
例えばアパレル商品であれば、着たときのシルエットや素材の動き方、化粧品であれば肌に乗せたときの質感や発色をライブで見せることで、視聴者は自分が使うイメージを持ちやすくなります。
こうしたリアルな商品体験の共有は、静止画やテキスト中心の従来型ECでは難しかったポイントであり、視聴者の購買意欲を高める要因になります。
視聴者とリアルタイムで交流し信頼関係を築ける
ライブコマースの大きな特徴は、配信者と視聴者がコメント機能を通じてリアルタイムで交流できる点にあります。
視聴者からの質問やコメントにその場で丁寧に答えることで、一方的な商品説明に終始するのではなく、対話を通じたコミュニケーションが生まれます。
このようなやり取りは、視聴者に親近感や安心感を与え、配信者個人やブランドに対する信頼関係の構築を促進します。
顧客とのエンゲージメントが深まることで、単なる購入者に留まらない長期的なファン(ロイヤルカスタマー)の育成も期待できます。
視聴者の疑問や不安をその場で解消し購入を後押しできる
ECサイトでの購入をためらう原因の多くは、「商品へのちょっとした不安」です。
サイズ感、使い方、相性、自分に合うかどうか?こうした疑問を、ライブ配信では即座に解消できます。
視聴者が気になると思ったタイミングで質問し、配信者が実演を交えて答えることで、購入までの心理的なハードルが下がるのです。
その結果、「あとで考える」のではなく「今買おう」という気持ちを引き出すことができ、コンバージョン率の向上につながります。
配信動画をアーカイブ化して二次利用できる
ライブコマースの魅力はリアルタイム性だけではありません。
配信が終わったあとも、その動画をアーカイブ化して二次利用することで、マーケティング資産として活用できます。
たとえば、次のような形で再活用すれば、1回のライブ配信が中長期の販促に貢献します。
- 自社ECサイトの商品ページに埋め込む
- YouTubeやInstagramで再編集して投稿する
- 社内教育や研修に使う
特に「商品の使い方を詳しく知りたい」というニーズが強い商材では、アーカイブ動画が24時間接客できる動画マニュアルとして機能します。
インフルエンサー起用で新たな顧客層へアプローチできる
ライブコマースでは、自社と親和性のあるインフルエンサーを起用することで、これまでアプローチできていなかったユーザー層にもリーチできます。
インフルエンサーが自分の言葉で商品を紹介することで、その信頼や影響力が購買意欲に直結しやすくなります。
とくにZ世代など、ブランドよりも人を重視する層には非常に効果的です。
また、インフルエンサー自身のフォロワーが視聴者となるため、認知拡大と売上促進の両面で大きな効果を発揮します。
導入前に知っておきたいライブコマースの4つの注意点

ライブコマースは多くのメリットを持つ販売手法ですが、始めればすぐに成果が出るわけではありません。
とくに初めて導入する企業にとっては、事前に把握しておくべき課題やリスクがあります。
たとえば、視聴者を集める仕組みや、配信者のスキル、リアルタイムならではのトラブル対応など、計画性が求められる要素は少なくありません。
ここでは、ライブコマース導入時に起こりやすい4つの注意点をピックアップし、対策とあわせて解説します。
ライブ配信を視聴してもらうための集客が必要になる
ライブコマースの成果は、いかに多くの視聴者に配信を見てもらえるかに大きく左右されます。
魅力的な商品やトークを準備しても、そもそも配信の存在を知られていなければ意味がありません。
そのため、配信前からの集客戦略が不可欠になります。たとえば、以下のような手段が有効です。
- 自社SNSアカウントでの事前告知(Instagram、X、LINEなど)
- メルマガでの通知
- ECサイト上のバナー掲載
- 配信当日に向けたカウントダウン投稿
- 限定クーポンやプレゼントの案内
特に初回配信時には、「なぜ視聴する価値があるのか」「得られるメリットは何か」を明確に伝えることが、集客率を高めるポイントとなります。
配信者のスキルや人選が売上を大きく左右する
ライブコマースでは、誰が配信するか=誰が接客するかという視点が非常に重要です。
商品知識はもちろんのこと、リアルタイムでの会話力や、視聴者を惹きつけるトーク力が求められます。
また、視聴者のコメントに即座に反応できなかったり、商品の魅力をうまく言語化できなかったりすると、ライブ配信の魅力は半減してしまいます。
配信の構成に工夫がないまま進行すると、視聴者は途中で離脱してしまう可能性も高まります。ライブコマースでは、おもに以下のようなスキルが求められます。
- コメントを拾ってすぐに返す反応力
- 商品の良さを的確に言葉にするプレゼンテーション力
- 長時間の配信でも視聴者を惹きつけ続ける構成力
こうしたスキルが欠けている場合、せっかく集めた視聴者が途中で離脱し、売上やブランドへの信頼に影響を与えることにもつながります。
配信内容によってはブランドイメージを損なうリスクがある
ライブ配信はリアルタイムで行われるため、編集ができません。
そのため、配信者の不適切な発言や誤った情報提供、視聴者からのネガティブなコメントへの対応の誤りなどが、そのまま配信されてしまうリスクがあります。
これらの事態は、企業のブランドイメージを大きく損なうことにつながりかねません。
事前に配信のガイドラインを設け、想定される質問やネガティブなコメントへの対応方針を決めておくことが重要です。
また、配信者にはブランドの代表であるという意識を持ってもらうための研修も有効な対策となります。
通信トラブルなど不測の事態への備えが欠かせない
ライブ配信には、どうしても通信環境や機材トラブルといったテクニカルなリスクが伴います。
【よくあるトラブルの例】
- Wi-Fi接続が不安定で音声や映像が乱れる
- マイクの不調により聞き取りづらくなる
- アプリや配信ソフトがフリーズする
こうしたトラブルが起きると、視聴者は不満を感じて離脱し、ブランドへの信頼も損なわれてしまいます。
トラブルを最小限に抑えるためには、下記のような運用面での備えが重要です。
- 事前の機材チェックとテスト配信
- 有線回線やモバイルルーターのバックアップ確保
- トラブル発生時のアナウンススクリプトの準備
- 複数人での配信サポート体制
ライブコマースで成果を出しやすい商品と業界

ライブコマースは、あらゆる商材に応用できる可能性を持つ手法ですが、とくに高い効果が出やすい業界や商品カテゴリーが存在します。
共通しているのは、写真やテキストだけでは伝えづらく、実演することや使用感を視覚的に見せることで魅力が伝わる商材であることです。
ここでは、ライブ配信と相性が良く、すでに多くの事例がある4つの業界を紹介します。どのような点がライブコマースとマッチするのか、その理由とあわせて解説します。
アパレル|着用感や素材感を伝えやすい
アパレルはライブコマースと非常に相性の良い業界です。
ECサイトでは服のサイズ感やシルエット、素材の質感などが伝わりにくいという課題がありますが、ライブ配信ではモデルが実際に着用しながら紹介することで、視覚的にわかりやすく伝えられます。
さらに、視聴者から「このパンツは低身長でも履ける?」「透け感はある?」といった質問が寄せられ、それに対してその場でスタッフが実演を交えて回答することで、リアルな接客体験が生まれます。
その結果、自分に合うかどうかがイメージしやすくなり、返品リスクの軽減や購入率の向上にもつながります。
コスメ・化粧品|使用方法や仕上がりをライブで実演
化粧品もライブコマースとの親和性が高い商材です。
ファンデーションのカバー力、リップの発色、アイシャドウのラメ感などは、実際に肌にのせることで初めて伝わる魅力です。
美容部員やメイクアップアーティストが、使い方のコツや色選びのポイントを実演しながら紹介すれば、商品への理解度が深まり、購入の後押しにもなります。
また、「この色はどのパーソナルカラー向け?」「敏感肌でも使える?」といった視聴者のリアルな質問に対して即答できるのもライブならではの強みです。
食品|調理や試食シーンでおいしさを伝えやすい
食品分野では、調理の様子や食べるシーンを見せることで五感に訴える「シズル感」を演出できます。
たとえば、焼き上がる音や立ちのぼる湯気、試食した際のリアクションなどが、視聴者の食欲を刺激し、「自分も食べたい」と感じさせる強い動機づけになります。
さらに、生産者が登場して素材へのこだわりや産地の特徴を語ることで、商品のストーリー性や信頼性が増し、価格以上の価値を感じてもらうことができます。
家具・雑貨|サイズ感や使い方を具体的に見せられる
家具やインテリア、雑貨のような商材は、実際のサイズ感や使い方を視覚的に伝えることで、購買の後押しにつながります。
視聴者が自分の生活に取り入れたときのイメージを持ちやすくなるため、ライブコマースとの相性が非常に良いカテゴリです。
たとえば、以下のような見せ方が効果的です。
- 収納ボックスに実際に物を入れて、どれくらい入るかを見せる
- 照明を点灯させて、部屋全体の明るさの変化を比較する
- キッチングッズを調理中に使い、その使い勝手を紹介する
こうした視覚的な情報は、商品選びの不安を解消し、「思っていたものと違った」といった購入後のミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
ライブコマースを成功に導く5つの重要ポイント

ライブコマースは、ただ配信をすれば成果が出るというものではありません。
事前の設計・準備・実行・振り返りまでを丁寧に行うことで、視聴者とのエンゲージメントが高まり、購入率やリピート率の向上につながります。
このセクションでは、ライブコマースをビジネスの成果に結びつけるために押さえておきたい、5つの重要なポイントを解説します。
ターゲットに合わせた配信者を選定する
ライブ配信で誰が商品を紹介するかは、成果に直結する最も重要な要素の一つです。
商品のジャンルや想定する視聴者層によって、最適な配信者のタイプは異なります。
たとえば、若年層向けのアパレルであれば、同世代に人気のインフルエンサーを起用することで共感を得やすくなります。
一方、専門性の高い商品であれば、自社の開発担当者や販売スタッフなど、商品知識が豊富で情熱を持って語れる人物のほうが信頼を得やすいケースもあります。
単に知名度のある人物を選ぶのではなく、ブランドイメージや商品コンセプトとの親和性が高いかどうかを軸に、慎重に人選することが成功の鍵です。
視聴者が集まりやすい時間帯に配信する
ライブ配信の成果を最大化するには、「誰が話すか」と同じくらい「いつ話すか」も重要です。
ターゲット層のライフスタイルを踏まえた配信時間の設計は、視聴者数や反応率に大きく影響します。
たとえば主婦層を狙う場合は、家事が一段落する平日の昼下がり。会社員層がターゲットなら、仕事終わりの夜20時以降が有効です。
また、過去の配信実績やSNSインサイトから、ユーザーが最もアクティブな時間帯を見極めることも有効です。
定期的に配信を行う場合は、「毎週月曜日の20時」など時間を固定することで、習慣的な視聴を促すこともできます。
視聴者が参加したくなる限定企画を盛り込む
ライブ配信を見てもらうだけで終わらせないためには、視聴者の参加意欲を高める仕掛けが必要です。
とくに「今見ているから得られる体験」を演出できると、ライブならではの価値を強く訴求できます。
具体的には、以下のような施策が効果的です。
- 配信中のみ使える限定クーポンの発行
- 数量限定商品の先行販売
- 購入者限定のプレゼント企画
- 視聴者のコメントから次の商品紹介を決める参加型構成
こうした仕掛けを組み込むことで、視聴者が当事者意識を持ちやすくなり、購買やSNS拡散などのアクションにもつながりやすくなります。
スムーズに購入できる導線を設計する
ライブコマースでは、視聴者が欲しいと思った瞬間を逃さず購入につなげるために、導線設計が非常に重要です。
どれだけ商品の魅力を訴求できても、購入までのプロセスにストレスがあれば離脱されてしまいます。
理想は、配信画面からワンクリックで商品詳細ページや購入画面に遷移できる状態です。さらに、以下の点にも注意が必要です。
- カート投入から決済完了までのステップ数は最小限にする
- ユーザー登録などの必須入力は必要最低限にする
- スマホ閲覧でも見やすく・操作しやすいUIにする
視聴者の「今買いたい」という熱量を逃さないためには、シンプルで迷わせない導線設計が鍵になります。
SNSやECサイトでの事前告知を徹底する
ライブ配信の成果を大きく左右するのが、配信前の準備です。
特に、事前告知の量と質が視聴者数に直結します。
告知では、「いつ・どこで・誰が・何を・どんな内容で話すのか」を具体的に伝えることが重要です。
加えて、「限定企画あり」「プレゼントあり」などのインセンティブ要素がある場合は、明確に伝えることで視聴者の期待感を高められます。
自社SNS(Instagram、X、LINE公式など)だけでなく、メールマガジンやECサイト上のバナー、ポップアップ通知など複数のチャネルを活用し、できれば数日前から複数回告知を行うのが理想です。
【5ステップ】ライブコマースの始め方と配信までの流れ

ライブコマースを始めるにあたっては、思いつきで配信を始めるのではなく、目的やターゲットの設定から配信後の振り返りまでを一連の流れとして設計することが重要です。
ここでは、ライブコマース未経験の企業でも実践しやすいように、準備から配信、分析までの流れを5つのステップに分けて解説します。
ステップ1|目的とターゲットを明確にする
ライブ配信を始めるにあたり、まず取り組むべきは「何のためにライブコマースを行うのか」という目的の明確化です。
目的が曖昧なままでは、配信内容や測定すべき成果指標も定まりません。
目標の例には以下のようなものがあります。
- 新商品の販売促進
- ブランドの認知拡大
- 既存顧客とのエンゲージメント強化
- ECサイトへの送客強化
また、視聴者=誰に届けたいのかというターゲット像も具体的に定義する必要があります。
- 年齢層や性別
- ライフスタイルや関心ごと
- 購入を迷うポイントや解決したい悩み
目的とターゲットが明確になることで、配信テーマや登場人物、使うプラットフォームの選定もブレずに決められるようになります。
ステップ2|配信プラットフォームを選定する
配信の目的とターゲットに応じて、最適な配信プラットフォームを選定することも重要です。
プラットフォームごとに特性や得意な集客手法が異なるため、特徴を理解した上で使い分ける必要があります。
主な種類と特徴は以下の通りです。
- SNS(Instagram、YouTube、TikTokなど)
フォロワーに対して直接発信でき、手軽に始められる - ECモール(楽天市場、Yahoo!ショッピングなど)
既存のモール内ユーザーにリーチしやすく、購買導線も整っている - 自社ECサイト連携型の専用ツール
独自ブランディングや高度な販売機能、データ分析が可能
どのプラットフォームを選ぶかによって、配信の演出や導線設計も変わるため、自社の戦略やリソースに合った選択が重要です。
ステップ3|配信機材(スマホ・マイク・照明)を準備する
視聴者にとって快適なライブ体験を提供するためには、最低限の配信機材を整えておくことが欠かせません。
スマホ1台で手軽に始められるとはいえ、配信の品質は視聴者の離脱率やブランドイメージにも関わります。
必要な機材の例は以下の通りです。
- 三脚(手ブレを防ぎ、安定した映像を確保)
- 外部マイク(ノイズを減らし、クリアな音声を届ける)
- ライト(商品や出演者を明るく照らし、映像の印象を向上)
- 予備バッテリー、延長コード(長時間配信への備え)
また、回線が不安定だと視聴者の離脱を招くため、安定したWi-Fi環境かモバイルルーターなどの予備通信手段も用意しておくと安心です。
ステップ4|配信内容の台本・進行表を作成する
ライブ配信は即興性が魅力ですが、視聴者を飽きさせずに最後まで見てもらうには、配信の流れをあらかじめ設計しておくことが大切です。
台本・進行表に含めるべき項目は以下のようなものがあります。
- 配信の全体構成(オープニング、商品紹介、Q&A、クロージングなど)
- 商品ごとの紹介順・訴求ポイント・価格
- コメントに答えるタイミングや方法
- トラブル発生時の対応方針や切り替え案
- 出演者間の役割分担と進行管理
こうした準備によって、配信中のテンポや伝えるべき情報の抜け漏れを防ぎ、視聴者満足度を高めることができます。
ステップ5|配信後に効果を測定・分析する
ライブ配信を実施したら、必ず振り返りを行い、次回以降の改善点を洗い出すことが成功の積み重ねにつながります。
主にチェックすべき指標には以下のようなものがあります。
- 総視聴者数、平均視聴時間、離脱タイミング
- コメント数や「いいね」などのリアクション数
- 商品ページへの遷移数、購入数、CVR(コンバージョン率)
- 売上の変化(配信前後の比較)
また、アーカイブ動画として再編集し、ECサイトの商品ページやSNSで再配信することで、1回の配信を中長期的な販促コンテンツとして活用できます。
【業界別】国内企業のライブコマース成功事例3選
ライブコマースは、日本国内でもさまざまな業界で導入が進み、多くの成功事例が生まれています。
具体的な企業の例を見ることで、自社でライブコマースを活用する際のヒントを得ることができます。
ここでは、特にライブコマースとの親和性が高い「百貨店」「アパレル」「家具・インテリア」の3つの業界から、それぞれの特徴を活かした成功事例をピックアップして紹介します。
これらの事例から、効果的な活用のやり方を学びましょう。
百貨店|店頭レベルの接客力で高価格帯商品を販売
老舗百貨店の三越伊勢丹では、公式企画「三越伊勢丹ライブショッピング」を通じて、各売り場の専門スタッフによるライブ配信を継続的に実施しています。
リアルタイムで商品を紹介しながらコメントにも対応し、その場で購入まで完結できる仕組みを構築しています。
なかでも注目されたのが、2020年に行われた「お中元ライブコマース」です。
配信にはゲストとして人気イラストレーターを起用し、商品背景や贈答シーンを丁寧に解説。視聴者は3万人を超え、ライブ配信経由の売上は過去最高を記録したと発表されています。
出典:
三越伊勢丹公式|ライブショッピング紹介ページ
三越伊勢丹 お中元ライブコマース プレスリリース
アパレル|人気スタッフを活用しファン化促進
ファッションブランドSHEL’TTERを運営するバロックジャパンは、自社ECサイト「SHEL’TTER WEB STORE」内でライブ配信機能を導入し、実店舗スタッフが出演するスタイルのライブコマースを実施しています。
視聴者はライブ配信を見ながらそのままEC内で商品を購入でき、配信中にはコーディネート提案や着用感への質問にも対応。
オフライン店舗での接客体験に近い形を再現することで、EC利用者の購入率向上につなげています。
出典:
SHEL'TTER公式オンラインストア
バロックジャパンリミテッド|ライブコマース導入記事
家具・インテリア|使い方を実演するライブ演出
家具・インテリア業界でも、ニトリが「NITORI LIVE」としてライブコマースを実施しています。
配信では、出演者が実際に家具を配置したり、インテリアコーディネートの工夫を見せたりしながら、視聴者のコメントにリアルタイムで対応するスタイルを採用。
商品の機能や使い方を「生活空間の中でどう活かせるか」という視点で伝えることで、購入の不安や迷いを解消しています。
また、動画をアーカイブとしてSNSやECサイトで再利用するなど、コンテンツ資産としての活用も進めています。
代表的なライブ配信プラットフォームの種類
ライブコマースを導入する際には、「どのプラットフォームで配信するか」を選ぶことが非常に重要です。
選ぶプラットフォームによって、集客力・販売機能・ブランディング自由度が大きく異なるため、自社の目的やターゲットに合ったものを選ぶ必要があります。
ここでは、代表的なライブコマース配信プラットフォームを3つのタイプに分類し、それぞれの特徴と選び方のポイントを解説します。
SNSプラットフォーム|フォロワーに直接アプローチできる手軽さが魅力
Instagram LiveやYouTube Live、TikTok LiveなどのSNSプラットフォームは、既存のフォロワーにリアルタイムで情報を届けられる点が大きな利点です。
スマートフォン1台で配信が可能で、アカウント開設後すぐに運用を開始できるため、初期導入のハードルが低いことも特徴です。
一方で、各プラットフォームの販売機能には違いがあります。
例えば、TikTok LiveではTikTok Shopとの連携により、ライブ配信中に商品を販売できる仕組みが整っています。
視聴者はライブ動画内に表示された商品をタップするだけで購入手続きに進むことが可能です。
Instagramではショッピング機能があり、投稿やストーリーズ、リールに商品タグを設置できます。
これにより、ユーザーは商品の詳細を確認し、アプリ内や外部のECサイトへ遷移して購入することができます。
また、Instagram Liveを活用したライブコマースでは、ライブ配信中に商品を紹介し、購入を促すことも可能です。
YouTube Liveでもライブコマース機能が提供されており、企業はライブ配信中に商品を販売できます。
ShopifyなどのECプラットフォームと連携することで、オンラインストアの商品をYouTubeチャンネルや動画に連携させ、ライブ配信中に商品を販売することも可能です。
【こんな企業におすすめ】
- 各種SNSフォロワーが一定数いる
- 配信コストを抑えてスモールスタートしたい
- 認知・ファンづくりを重視したい
出典:
Bytedance株式会社|TikTok Shop
YouTube ヘルプ|YouTube のライブ ショッピングについて
Meta ヘルプセンター|Instagramショッピングについて
モール系プラットフォーム|既存顧客への訴求に強い
楽天市場やYahoo!ショッピングなど、大手ECモールが提供するライブコマース機能を活用する方法もあります。
モールが持つ集客力を活かし、プラットフォーム内で購買まで完結させやすい点が強みです。
また、モール側で視聴・購入・決済までのフローが最適化されているため、導入企業側の運用負担が比較的少ないのも利点です。
ただし、モール独自の制限や手数料、ブランディングの自由度の低さなどが課題になることもあります。
【こんな企業におすすめ】
- すでにモール内でショップを展開している
- 新規顧客獲得よりも既存顧客への接触を強化したい
- 販売機能や導線設計に手間をかけたくない
専用ライブコマースツール|高度な機能とブランド構築に最適
自社ECサイトに埋め込める専用ライブコマースツールは、ブランディングを重視しながら販売効果も最大化したい企業に向いています。
これらのツールは、配信画面内でのカート操作や質問受付、分析レポートといったEC連携に特化した機能が揃っており、マーケティングやPDCA運用にも活用できます。
【こんな企業におすすめ】
- 自社ECを主軸にライブ配信を展開したい
- データ分析やCRM連携など、マーケティング強化も行いたい
- 高単価商材やリピーター戦略に注力している
代表的なツールには、以下のようなサービスがあります。
TAGs(タグス)|株式会社Moffly
ブランドEC向けのライブコマースツール。コメント管理・同時配信・購入導線の最適化などに対応。
公式サイト:https://tags-video.com/
HandsUP|株式会社17LIVE
17LIVEが提供するライブコマース専用SaaS。投げ銭・購入機能・CRM連携などを搭載。
公式サイト:https://handsup.17.live/
まとめ
この記事では、ライブコマースについての基礎知識から、国内外の市場動向、導入のメリットと注意点、成果を出しやすい商品ジャンル、成功事例に加え、活用できるプラットフォームまでを総合的に解説しました。
ライブコマースは、単にライブで商品を紹介するだけの施策ではありません。
視聴者との双方向のコミュニケーションを通じて、商品の魅力をより深く伝え、納得感のある購買体験を提供できることが最大の強みです。
だからこそ、配信前の準備、配信者の選定、企画設計、視聴者参加の仕掛け、購入までの導線設計、配信後の振り返りといったすべてのプロセスにおいて、丁寧な設計が求められます。
今後、オンライン上での購買体験がますます進化していくなかで、ライブコマースはECやマーケティング戦略の中でも重要な役割を担う存在になるでしょう。
まずは自社の商品や顧客との相性を見極め、小さく始めて改善を重ねながら育てていくことで、ブランドの魅力をより多くの人に届けられる強力なチャネルになっていくはずです。
※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比
※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月