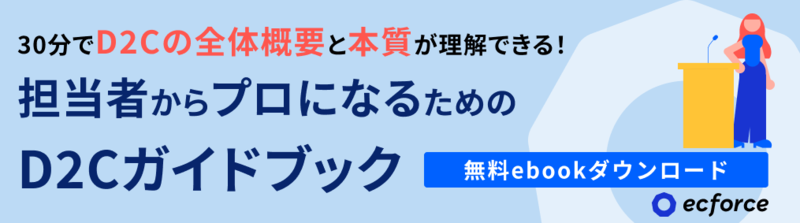この記事でわかること
※この記事は 時点の情報をもとに執筆しています。
インターネットの普及により、私たちの買い物の在り方は大きく変わりました。スマートフォンひとつで、国内外のさまざまな商品が手に入る時代。
こうした変化の中心にあるのが「EC販売」です。
この記事では、EC販売の基本から、実際の始め方、事業者・購入者それぞれのメリット・デメリット、成功させるためのポイントまでを幅広く解説していきます。
これからEC販売を始めたい方や、改善を図りたい方の参考になる情報を盛り込みました。
関連するテーマについては、下記の記事も合わせてチェックしてみてください。
EC事業とは?今始めるべき理由と失敗しない始め方・成功のコツ
【2025年最新版】物販ビジネスの始め方|儲かる仕組み・利益を出す6ステップ
EC販売の概要

EC販売とひと口に言っても、その形態は多岐にわたります。
どの形式を選ぶかによって、運営体制やコスト構造、ブランディングの自由度、集客のしやすさなどが大きく異なります。
この章では、主に「自社ECサイト」「モール型EC」「D2C・BtoB・CtoC」「併用(ハイブリッド)型」の4タイプに分けて、それぞれの特徴や適性を解説します。
EC販売とは
EC販売(Electronic Commerce)は、インターネット上で商品やサービスを売買することを指します。たとえば、アパレル、食品、美容アイテム、家具、デジタルコンテンツなど、ほとんどの商材がオンラインで販売可能です。
近年は、実店舗を持たずにオンライン完結型で商品を展開する事業者が増えており、小規模でもスタートしやすいビジネスモデルとして注目されています。
インターネット環境さえあれば、時間や地理的制約を受けずに全国、さらには海外市場への展開も可能です。
特にスマートフォンの普及とSNSの影響力拡大により、個人ブランドやスタートアップがECを通じて短期間で急成長するケースも少なくありません。
ECサイトとは
EC販売を実現するのが「ECサイト」です。これは、ネット上に構築されたオンラインショップで、ユーザーが商品を閲覧・選択し、購入手続きを完了できるよう設計されています。
- 商品の一覧表示・詳細情報の提供(価格・素材・サイズなど)
- 決済機能(クレジットカード、コンビニ支払いなど)
- 顧客管理機能(マイページ、購入履歴など)
- 在庫管理や発送ステータスの通知
最近では、単に「売る場」としての役割にとどまらず、ブランド体験を伝える「世界観の演出」や、顧客ロイヤルティを高める「CRM(顧客関係管理)」の場としても重視されるようになっています。
EC業界の市場規模と成長性
日本国内のEC市場は、右肩上がりで成長を続けています。
経済産業省の調査によると、BtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場は2023年に約24.3兆円に達し、前年比で8.4%増加。特に物販系分野が堅調に成長しており、今後も拡大が見込まれています。
- スマートフォン利用者の増加
- 新型コロナウイルスによる生活様式の変化
- SNSの普及による「ソーシャルコマース」の台頭
- 決済・物流インフラの進化
一方で、企業間取引を対象としたBtoB-EC市場も大きな伸びを見せており、2023年には420兆円を突破。
多くの業種でデジタルシフトが進む中、EC販売は「当たり前の販売手段」としてその存在感を増しています。
出典:経済産業省「電子商取引に関する市場調査(2024年5月発表)」|https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240925001/20240925001-1.pdf
今後の展望
EC販売の未来には、さらなる多様化と高度化が待ち受けています。今後注目されるトレンドは以下の通りです。
- D2C(Direct to Consumer):メーカーが小売業者を介さずに、直接顧客に販売するビジネスモデル。ブランド独自の価値を伝えやすく、リピーターを獲得しやすい。
- 越境EC:日本国内から海外へ、または海外から日本への販売。特にアジア圏での日本製品需要が高く、拡大余地が大きい。
- ライブコマース:インフルエンサーやスタッフがリアルタイムで商品を紹介し、その場で購入に誘導する手法。中国での急成長を受け、日本でも導入が進んでいます。
このように、EC販売は単なる「ネット通販」を超えて、ブランド価値の表現やグローバル展開、顧客との長期的な関係づくりまで視野に入れた戦略的チャネルとなっています。
EC販売の種類

EC販売と一口に言っても、様々な形態が存在します。どのような形式でEC販売を行うかは、事業の規模や目的に応じて選択することができます。
ここでは、ECサイトの種類、そしてその他の販売形式について詳しく見ていきましょう。
自社EC
自社ECサイトとは、自社の独自ドメインを用いて構築・運営するECサイトのことです。
Shopify、BASEなどのASPカートを利用するケースが多く、カスタマイズ性が高いのが特徴です。
最大のメリットは、ブランドイメージや販売戦略を自社の裁量で自由に設計できる点です。
顧客データもすべて自社で蓄積・分析できるため、リピーター施策やLTV(顧客生涯価値)を高めるマーケティングが行いやすくなります。
一方、集客をゼロから行う必要があるため、SNS運用やSEO、広告運用などのマーケティング施策が欠かせません。
また、デザインや機能の実装には一定の知識やコストがかかる場合もあります。
自社ECは、中長期的にブランド価値を育てたい企業や、独自の商品を販売するD2Cブランドに特に適しています。
モール型EC
モール型ECとは、楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングといった大手プラットフォーム内に出店する形態です。いわば「オンライン上の巨大ショッピングモール」に出店するイメージです。
モールの最大の魅力は、高い集客力と信頼性です。既に多くのユーザーが訪れているため、比較的早い段階で売上を確保しやすい特徴があります。
また、決済や物流などのインフラが整備されているため、運営の手間が少ない点もメリットです。
ただし、出店手数料や販売手数料がかかるため、利益率は圧迫されがちです。
モール側のルールやテンプレートに沿って運営する必要があるため、ブランドの世界観を自由に表現するのが難しいケースもあります。
短期的に売上を上げたい事業者や、初めてEC販売を行う初心者には、比較的導入しやすい手法といえるでしょう。
その他の販売形式:D2C・BtoB・CtoC
EC販売の形は、近年さらに多様化しています。その中でも注目されているのが、D2C、BtoB、CtoCの3つのビジネスモデルです。
D2C(Direct to Consumer) は、製造者(メーカー)が中間業者を介さずに、自社サイトなどを通じてエンドユーザーに直接販売するモデルです。
商品開発から販売、顧客管理まで一貫して行えるため、ブランドの価値を明確に伝えやすい利点があります。
BtoB(Business to Business)EC は、企業間取引をオンラインで行うモデルです。
製品部品や業務用備品、原料などを扱うケースが多く、紙のカタログやFAX受注からのデジタルシフトが進んでいます。
最近では、受注から決済・在庫管理までを一元化できるBtoB向けECシステムの導入が加速しています。
CtoC(Consumer to Consumer)EC は、個人間での売買をネット上で行う形態で、メルカリやラクマなどのフリマアプリが代表格です。
近年は副業として利用するユーザーも増え、特に20〜30代のスマホユーザーを中心に定着しています。
ハイブリッド型(モールと自社ECの併用)
最近では、モール型と自社ECを組み合わせて活用する「ハイブリッド型」の販売戦略をとる事業者も増えています。
たとえば、モールでの集客力を活かして新規顧客を獲得し、その後は自社ECに誘導してリピーター化・ファン化を図るという導線設計です。
このような戦略を取ることで、短期的な売上と長期的なブランド構築の両方を実現できます。さらに、販売チャネルを複数持つことで、一方のチャネルに依存しすぎるリスクを分散できるのも大きなメリットです。
EC販売のメリット

EC販売は、単なる「オンライン上で物を売る手段」ではありません。うまく活用すれば、ビジネスの成長を加速させるための強力なツールになります。
ここでは、事業者にとってのメリットと、購入者にとってのメリットに分けて、それぞれの観点から解説していきます。
事業者にとってのメリット
EC販売は、商品を「売る」だけでなく、ビジネスの成長を加速させるための仕組みとして活用できます。
特に、物理的な店舗に比べて柔軟かつ低コストで始められる点が、多くの事業者にとって大きな魅力です。
ここでは、事業者視点でEC販売がもたらす代表的なメリットを具体的に紹介します。
1. 地理的制約を受けずに販売ができる
最大のメリットは、販売エリアに物理的な制限がないことです。
実店舗では商圏が限られますが、ECであれば日本全国、さらには海外への販売も可能になります。
たとえば、北海道の工芸品を東京の顧客に届けたり、九州の食品を台湾へ販売したりといった「越境EC」も簡単に実現できます。
2. 24時間365日販売が可能
店舗の営業時間に縛られることなく、ECサイトは常に開いています。
深夜や早朝など、通常の営業時間外にも注文が入る可能性があるため、売上機会を逃すことがありません。
ユーザーにとっても「思いついたときにすぐ買える」利便性があります。
3. 実店舗に比べて初期費用・固定費が抑えられる
実店舗では、テナント賃料や人件費、光熱費など多くの固定費が発生しますが、ECではその多くが不要です。
特に自社ECサイトの場合、初期費用無料のASPカートを使えば、月数千円の運用費から始めることも可能です。予算を抑えつつスモールスタートできるのは大きな魅力です。
4. 顧客データの蓄積と分析ができる
ECでは、顧客の購入履歴、閲覧履歴、カート放棄率、離脱ページなど、あらゆるデータを取得できます。
これらの情報を活用すれば、パーソナライズドなマーケティングや商品改善、リピーター施策に活かすことができます。
CRMツールやマーケティングオートメーション(MA)との連携も容易です。
5. ブランドの世界観を自由に表現できる
特に自社ECの場合は、デザインやコンテンツを自由に設計できるため、ブランドのコンセプトやストーリーをサイト全体で表現できます。
これにより、ただの販売ではなく「体験」として商品を届けることが可能になります。SNSと連動すれば、より強固なファンベースを築くこともできます。
購入者にとってのメリット
購入者にとってもEC販売は利便性と自由度の高い買い物手段として日常に定着しています。
時間や場所にとらわれずに、好きなタイミングで商品を探して購入できる体験は、実店舗にはない大きな魅力です。
ここでは、消費者視点から見たEC販売のメリットを詳しく見ていきましょう。
1. いつでも・どこでも買い物ができる
ECの最大の魅力はその「手軽さ」です。通勤中や休憩時間、就寝前のベッドの中でも、スマートフォンひとつで買い物ができます。
店舗まで足を運ぶ必要がないため、忙しい現代人にとって非常に効率的です。
2. 商品の比較検討がしやすい
複数のショップや商品を同時に比較できる点も、オンラインならではの強みです。
価格、レビュー、素材、サイズ感などを調べながら、自分に最も合った商品を選ぶことができます。
また、検索機能やフィルター機能により、欲しい商品を短時間で探せます。
3. 決済手段が豊富に用意されている
クレジットカードや銀行振込、コンビニ払い、PayPay、あと払いなど、ECでは多様な決済方法に対応しています。
自分のライフスタイルに合わせた支払い方法を選べるため、利便性が非常に高いです。
4. セールやクーポンが豊富でお得に買える
ECでは、タイムセール、期間限定割引、ポイント還元などの販促施策が頻繁に実施されています。
実店舗ではなかなか出会えない「オンライン限定価格」や「先行販売商品」にアクセスできるのも魅力です。
5. ギフトや定期便などの利用が簡単
近年は、ギフト配送やサブスクリプション型の定期便など、ユーザーのニーズに合わせた機能が充実しています。
たとえば、離れて暮らす家族にプレゼントを贈ったり、毎月決まった日にコーヒー豆を届けてもらったりといった使い方も一般的になってきました。
EC販売のデメリット・課題

EC販売には多くのメリットがある一方で、運営にはいくつかの課題も伴います。
これらの課題を正しく理解し、事前に対策を講じることが、安定したEC運営の鍵となります。
ここでは、全体的なデメリットと、モール出店・自社ECそれぞれ特有の課題を整理して紹介します。
EC販売に共通する課題
まず、EC販売全体に共通する課題として、「商品を手に取れない」「送料の負担」「価格競争の激化」「配送のタイムラグ」が挙げられます。
購入前に商品の質感やサイズ感が確認できないことから、返品やクレームにつながるケースも。写真や動画の工夫で、情報不足を補うことが求められます。
また、送料無料施策は購入率アップにつながる一方、送料を誰が負担するかで利益に大きな差が出ます。
さらに、同じ商品が多く出回る中では、価格競争を避ける工夫も不可欠です。
モール出店の課題
モール出店は集客力に優れる一方で、「手数料負担」「競争の激しさ」「ブランドの個性が出しづらい」「顧客情報が得にくい」といった制約があります。
特に差別化が難しく、価格やレビューでの評価が売上に直結するため、設計に工夫が必要です。
自社ECサイトの課題
自社ECは自由度が高い反面、「集客力の確保」「信頼性の構築」「運用負荷の高さ」が課題です。
特に開設初期はアクセスが伸びにくく、SEOやSNSなど地道なマーケティング施策が欠かせません。
また、決済・在庫管理・発送体制の整備も含め、幅広いリソースが求められます。
EC販売の運営業務

EC販売は、サイトを立ち上げた後の運営体制こそが成功を左右します。
商品が売れ始めると、毎日のように発生するルーティン業務をどれだけ効率よく、かつ顧客満足度を保ちながら回していけるかが重要です。
運営業務は大きく分けて、「フロントエンド業務」と「バックエンド業務」に分類され、それぞれが密接に連携しています。
フロントエンド業務(売上をつくる業務)
フロントエンド業務(顧客に見える業務)
フロントエンドとは、売上をつくるための“見える活動”です。主に以下のような業務が含まれます。
- 商品企画・仕入れ・撮影
- 商品ページの制作(画像・コピー・価格設定)
- サイトデザインの更新
- キャンペーンやクーポン企画
- 広告運用(Google広告・SNS広告など)
- SEO対策・SNS投稿・メールマガジン配信
特に中小規模のECサイトでは、ひとりで複数業務を兼任するケースも多く、作業負荷が集中しがちです。時間のかかる作業は外注やツールで効率化し、戦略設計や売上改善に時間を充てることが理想です。
ECの運営体制を整えるには、各業務の役割を正しく把握することが大切です。具体的なフローや注意点については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
ECサイト運営の基本業務と必要スキルとは?【初心者向けガイド】|ecforce blog
バックエンド業務(顧客に見えない支える業務)
バックエンドの業務は、注文から商品到着・問い合わせ対応まで、EC体験の“裏側”を支える業務です。主な内容は以下の通りです。
- 受注処理(注文確認・決済ステータス確認)
- 在庫管理・システム連携(倉庫・モール・店舗)
- 梱包・出荷指示・納品書発行
- 配送業者とのやり取り(ヤマト、佐川、日本郵便など)
- 顧客からの問い合わせ対応
- 返品・交換処理
- アフターサポート(レビュー依頼・リピート促進)
この部分のクオリティが、ECサイトの「信頼」と「再購入率」に直結します。
たとえば、注文から出荷までのリードタイムが短く、問い合わせにすぐ対応できるショップほど、リピーター化が進みやすいです。
効率化のカギ:運営フローの可視化とツール活用
ECサイトの規模が拡大してくると、人的リソースだけでは運営の安定を維持することが難しくなります。
そこで重要になるのが、業務の可視化と業務支援ツールの活用です。
作業工程を明確にし、属人化を防ぎながら、各工程をツールで自動化・効率化することで、少人数でもミスのない運営体制を実現できます。
代表的な支援ツールとしては、以下のようなものがあります。
- OMS(受注管理システム)
複数モールや倉庫との在庫・受注情報を一元管理し、出荷指示まで自動化できます。 - WMS(倉庫管理システム)
入出庫・在庫数の精度を高め、誤出荷や在庫ずれといった人的ミスを防ぐことができます。 - CRMツール(顧客管理システム)
購入履歴や行動履歴をもとに、リピート促進のためのメルマガ配信やクーポン施策を最適化できます。 - チャットボット・FAQ自動応答システム
顧客対応の一次対応を自動化し、カスタマーサポートの負担を軽減します。
これらのツールを適切に組み合わせることで、業務の負荷を減らしながら、顧客満足度を維持・向上させることが可能になります。
効率的な運営体制を構築することは、単なる作業量の削減ではなく、顧客体験の品質を安定させるための投資でもあります。
ECの競争力は裏側で決まることを意識して運用体制を整えていきましょう。
ECサイト開業の仕方と成功のためのポイント
ECサイトを開設するには、ただサイトを作れば良いというものではありません。販売計画や体制づくり、ツール選定、商品調達まで含めた事業設計が求められます。
ここでは、EC販売をこれから始めたい方に向けて、開業前に押さえるべき7つのステップを紹介します。
準備不足によるつまずきを防ぎ、スムーズに立ち上げられる状態を整えましょう。
1. 予算とスケジュールを設計する
まず最初に決めるべきは、「どのくらいの費用をかけるのか」「いつまでに始めたいのか」です。
個人の副業や小規模な会社でEC販売を始める場合、初期費用を抑えつつ手軽に始めたいと考える方が多いかもしれません。
その場合は、初期費用が無料のASPカートやクラウドECシステムを利用するのがおすすめです。
ある程度の予算を確保でき、納期にも余裕がある場合は、パッケージ版のシステムを導入したり、ゼロからシステムを開発したりといった選択肢も考えられますが、費用や開発期間は大きく変動します。
サイトの規模や必要な機能を考慮し、現実的な予算と納期を設定することが重要です。
また、個人で始めるのか、会社として取り組むのかによっても、かけられる費用や準備期間は変わってきます。
2. 運営にかかる作業量と体制を見積もる
ECサイトは開設したら終わりではなく、毎日運用が発生します。
注文確認・在庫更新・梱包・出荷・問い合わせ対応などのバックエンド業務は、想像以上に手間がかかることもあります。
あらかじめ、どんな業務がどれくらい発生するのかを洗い出し、1人で回せるのか、外注やツール導入が必要かを見積もっておきましょう。
ECの運営業務について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
ECサイト運営の基本業務と必要スキルとは?【初心者向けガイド】|ecforce blog
3. サイトイメージとブランドの世界観を固める
どのような顧客に、どんな印象を持ってもらいたいかを考えながら、サイトのデザイン方針を固めましょう。
カラー・レイアウト・フォント・写真のトーンなど、細部まで一貫性を持たせることで、ブランドの世界観を強く印象づけることができます。
参考になるECサイトをピックアップし、「どこが良いのか」「なぜ惹かれるのか」を具体的に分析しておくと、デザイナーとのすり合わせもスムーズです。
4.自社に合ったプラットフォームを決める
サイトの方向性が見えてきたら、どのプラットフォームで構築するかを決めましょう。
選択肢は、大きく「自社ECを構築する」か「ECモールに出店する」かの2つに分かれます。
自社ECの場合、手軽なASPカート、拡張性の高いSaaS型、開発自由度のあるパッケージ型・オープンソースなどがあります。
モール出店ではAmazonや楽天市場などが代表的で、高い集客力が魅力です。
費用、機能、運用体制、ブランド戦略などを総合的に比較し、自社に最適な方法を選定しましょう。
5. 取り扱い商品と調達方法を明確にする
どんな商品を売るかは、EC販売における戦略の出発点です。ジャンル、単価、回転率、リピート性などによって、ターゲット層やマーケティング手法、在庫・物流の仕組みまでが変わります。
商品が決まっている場合は、ECに適しているかを改めて精査しましょう。たとえば、サイズが大きすぎる、割れ物で破損リスクが高い、消費期限が短いなどの商材は、物流や返品対応に工夫が必要です。
商品が未定の場合は、以下のような手段で調達を検討できます。
- 国内・海外問屋からの仕入れ:手軽に始められるが、利益率は低め。競合性が高くなりやすい。
- OEM・ODMによるオリジナル開発:ブランド構築には有利だが、製造リードタイムや初期ロットに注意。
- ドロップシッピング:在庫リスクを最小限にできるが、納期や品質にばらつきが出やすい。
- クラウドファンディング:先行予約で需要検証しながら資金調達が可能。スタートアップ的アプローチに有効。
いずれにしても、商品選定時には「誰に、どんな価値を、なぜ届けるのか」を明確にした上で、調達コスト・在庫管理・配送対応までを一貫して設計することが重要です。
6.決済手段と配送方法を事前に整備する
ユーザーが購入までスムーズにたどり着くためには、「支払い」と「受け取り」の体験設計がカギになります。この2つは地味に見えて、カート離脱率やリピート率に大きく影響する要素です。
まず、決済手段は、できる限り複数用意しておくのがベストです。ECにおける主要な支払い方法には以下があります。
- クレジットカード(VISA、Master、JCB など)
- コンビニ決済
- 銀行振込
- 代引き(対面受け取りに強い)
- あと払い(後払い.com、Paidy など)
- スマホ決済(PayPay、楽天ペイなど)
顧客の年齢層や購入シーンに応じてニーズは分かれるため、ターゲットに合った支払い手段を用意しましょう。特に「あと払い」や「スマホ決済」の導入は、若年層や衝動買い需要にも効果的です。
また、EC販売における決済方法については以下の記事で詳しく解説しています。
オンライン決済、どれを選ぶ?選び方と比較ポイントを徹底解説【導入時のチェックリスト付き】|ecforce blog
次に配送方法は、商品サイズ・重量・価格帯に応じて最適な手段を選びます。代表的な選択肢には以下があります。
- ヤマト運輸(宅急便・ネコポス)
- 日本郵便(ゆうパケット・ゆうパック)
- 佐川急便(飛脚宅配便)
- クリックポスト、レターパック(小型商品向け)
配送業者との契約内容(料金・追跡・再配達対応)によって、コストと利便性のバランスを調整することも大切です。
また、送料設計(無料ライン、地域別送料など)も購入率に直結するため、慎重に設定しましょう。
最後に、配送遅延や支払いエラーなどが発生したときのサポート体制も忘れずに準備しておきましょう。
顧客との信頼関係は、「不満が起きたときの対応」で決まります。
7.価格設定と売上目標を立てる
価格設定は、EC販売における利益構造を左右する最重要ポイントのひとつです。
適正価格をどう設計するかによって、利益率・購入率・リピート率すべてに影響を及ぼします。
まず、基本となるのは「原価+販管費+利益」をもとにした原価積み上げ式の設計ですが、それだけでは不十分です。
以下のような複数の観点を加味して、価格に説得力を持たせる必要があります。
- 競合商品の相場
- 自社ブランドのポジショニング(高級志向か、コスパ訴求か)
- 送料・手数料込みの最終利益率
- 販売チャネル別(モールと自社ECで価格を変える等)
- リピーター向けの価格設計(定期便、まとめ買い割引)
また、単に価格を決めるだけでなく、売上目標との連動設計も重要です。たとえば「月商100万円を目指す」と仮定した場合、以下のように逆算して販売戦略を組み立てます。
- 平均注文単価:5,000円
- 購入件数:200件/月
- 必要な訪問数:20,000(CVR 1%の場合)
- 必要な広告費:15万円(月)
こうして売上目標から必要なアクセス数・CVR(購入率)・広告投資を逆算することで、感覚ではなく論理に基づいた施策判断が可能になります。
さらに、実際の運営では「新商品は最初に割引価格で提供し、その後正規価格へ戻す」「セールと通常価格を意図的に使い分ける」「レビュー数を増やすために初回購入者特典を設ける」といった価格を軸にした販売戦略も効果的です。
最初から完璧な価格に設定するのは難しいですが、「仮説 → 販売 → 分析 →調整」のPDCAを繰り返すことで、徐々に最適な価格帯と商品構成が見えてきます。
まとめ
商品やサービスをインターネットで販売するECは、今や多くのビジネスにとって欠かせないチャネルです。
アイデア次第で全国、さらには海外へと販路を広げられる一方で、準備なしに始めてしまうと、運営の途中でつまずくことも少なくありません。
運用の負担、価格競争、集客の難しさなど、ECには現実的な課題がいくつもあります。だからこそ、はじめにどのような方法で展開するか、自社にとって適切な販売形態や構築プラットフォームは何かを見極めておくことが重要です。
特に、ECサイトの開業準備では「何を売るのか」だけでなく、どうやって届けるか、どうやって収益化するか、どんな体制で運用するかまで視野に入れておく必要があります。必要な工程をひとつずつ丁寧に積み重ねていくことで、無理のないスピードで、安定した運営に近づくことができます。
また、価格や商品だけで勝負するのではなく、ユーザーが購入にいたるまでの体験や、購入後の満足感を設計する視点も欠かせません。ECサイトを「売るだけの場」にせず、ブランドの価値や考え方を届ける場として活用することで、価格に頼らない選ばれ方が生まれていきます。
ECは、一度作って終わりではなく、運営しながら整え、育てていくものです。
すぐに売れるかどうかよりも、長く続けていける仕組みかどうかを大切にしながら、自社にとって最適なかたちで取り組んでいきましょう。
※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比
※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月