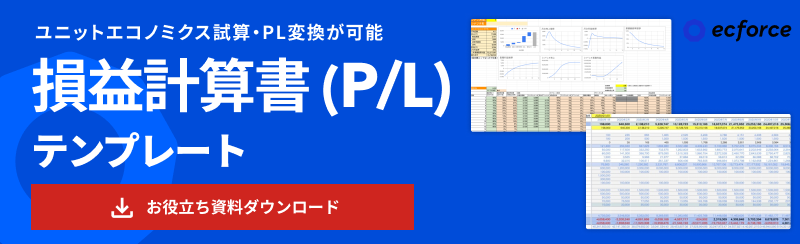この記事でわかること
スタートアップや新規事業開発を行っていると「ユニットエコノミクス」という単語がよく耳に入ってきます。
ユニットエコノミクスとは、PL(損益計算書)やCF(キャッシュフロー)の考え方を脱却して、開始したサービスを飛躍させるために、非常に重要な概念です。
今回は経営をされている方、及び新規事業(D2C事業)の担当者の方のために、その考え方を紐解いていきます。
関連するテーマについては、下記の記事もあわせてチェックしてみてください。
EC事業計画に役立つ損益計算書(PL)の作り方|損益分岐点や見方を事例で解説
ユニットエコノミクスとは何か
ユニットエコノミクスとは、簡単に言うと「顧客一人を獲得した時に、儲かっているのか損をしているのか」を客観的に判断する指標です。
D2C事業では、現在、特に定期通販モデルが多く存在しておりますが、定期通販モデルはまずは顧客を獲得し、その後、長く顧客に継続購入してもらうことで利益を得ます。
したがって、最初は先行投資をし、その後、時間をかけて利益を回収していくので顧客単体のPLで見ると、どうしても最初は赤字で、かつ、その状態で顧客獲得を続けると、一定期間、赤字が続いてしまいます。
しかし、中長期目線で儲かることが分かるのであれば、現状赤字だとしても顧客の獲得は進めた方が良いという判断基準になります。
即ち、赤字であることが悪いのではなく、「中長期目線で儲かる顧客獲得・事業モデルである」という根拠を持って経営していく必要があります。
その根拠となる経営指標が「ユニットエコノミクス」なのです。
この「ユニットエコノミクス」が健全ではないという状態は、「得られる利益を想定しても、顧客を得るごとにお金を失っている」もしくは、「利益に対して、顧客の獲得コストが異常に高い」ことを意味します。
アメリカの有名VCであるY combinatorのポール・グラハムは「その事業がデフォルトで生きているのか、死んでいるのか?」という言葉を使って、事業及びその企業の成長性・投資価値を測っています。
見かけの成長率だけを追い求めてスケールしようとしても、ユニットエコノミクスの状態が悪いということは、お金の利用効率が悪いため、十分な利益が取れていない状態と判断されるのです。
もちろんD2C事業はスタートアップ企業のように、初期段階では赤字を出しながら事業の急成長を狙うので、この段階で健全でないのは仕方がないことです。
しかし上述のような課題があるため、なるべく早い段階でユニットエコノミクスの健全性は確保していかなければなりません。
まさに、この健全性は、D2C事業が最初に追うべきKPIと言っても過言ではないでしょう。
評価方法(ユニットエコノミクスの考え方)
一般的にユニットエコノミクスの計算では、
・解約率(チャーンレート)
・ARPU(顧客一人あたりの平均売上)
・LTV
という3つの指標を使います。
※細かくするとさらに細分化、詳細な数字が計算可能ですが、今回は入門編で一般的な計算式とします。それぞれの指標の計算をしていきましょう。
解約率の計算式
これは非常に簡単で、
解約率=月末の解約者数 / 月初の利用者数
上記数式で計算可能です。
例えば、月初に1000人が課金をしていたとして、月末までに150人解約してしまったとします。
この場合の解約率は、150人÷1000人で15%となりますね。
解約率については、スタートアップ界隈でSaaS系のサービスの場合に特に重要視されます。
なぜなら、後々、ユーザーを獲得していくのにあたり、どのくらいのユーザーが残ってくれるのかによって成長の効率が大きく変わってくるからです。
もちろん、この解約率というものは低ければ低いほど良いです。
ARPUの計算式
こちらはAverage Revenue Per Userの略で、顧客一人あたりの平均売上であり、月次で計測していくものが多い指標となります。
D2C事業でよくある初回をチャレンジ価格、二回目以降を定期価格というモデルで計算してみましょう。
例えば、初回1500円で、二回目以降の価格が3000円の商品で、毎月ユーザー比率でいうと20%が新規、80%が継続ユーザーだったとします。
その場合の計算方式は、(1500円×20+3000×80)÷100=2,700円
こちらも当然高い方が良いのですが、あまりに高額だと解約率も高くなるため、解約率を見極めてプライシングをしていく必要があります。
LTVの計算式
これはよく聞く単語ですね。Life Time Valueの略となります。
この計算式も非常にシンプルです。
LTV=ARPU÷解約率
となります。
※ただし、上記ARPUと解約率の同一の期間にしなければ数字が変わってきますので注意が必要です。
例えば、上述したサービスで、
- 解約率が15%
- ARPUが2,700円
だった場合、LTVは
2,700円÷15%=18,000円
となります。
ユニットエコノミクスの健全化を評価
それでは上記例を元に、ユニットエコノミクスを評価していきたいと思います。
・解約率が15%
・ARPUが2,700円
・LTVが18,000円
ということで、顧客獲得単価(CPA)が10,000円だったとしても得をしている状態となりますが、効率の良い稼ぎ方は出来ていない状態となります。
まず、大原則として、ユニットエコノミクスについては勿論プラスである必要があります。
スタートアップ企業の初期フェーズのように、まだマネタイズ出来ていない特殊な状況下の場合は、マイナスになることもありますが、基本はプラスとなるように顧客獲得単価を調整していく必要があります。
一般的には、ユニットエコノミクスが健全な状態というものは、LTVが獲得単価の3倍以上だと言われています。
例えば上記のLTVが18,000円の場合なら、CPAは6,000円ほどで獲得すべきだということになりますので、中期的に自分たちが目指す指標が分かりますね。
ところで、EC・D2Cビジネスを総合支援するecforce consultingをご存じですか?
2022年1月時点で50件近くの支援実績があり、有名ブランドを陰で支える知る人ぞ知るサービスです。常に最新のトレンド・情報にアップデートしているので、まずはお気軽にご相談ください。
ecforce consultingへのお問い合わせ
ユニットエコノミクスを指標にする理由(お金の使い方を身に付けよう)
なぜ、D2Cをはじめとした新規事業・スタートアップではユニットエコノミクスが注目されるのか。
新事業の初期段階では、何よりも成長することが求められます。
黒字を出しながらスモールビジネスのように成長するのではなく、赤字を出しながらも、日々成長することの方が重要とされているからです。
そのうえで、ユニットエコノミクスという考え方を理解すれば、月額3,000円の商品だとしても、獲得単価が3,000円までしか使えないということにはなりません。
成長曲線を実感し、5,000円、6,000円と支出してもしっかりと黒字になるという根拠の元に顧客獲得を目指していくことが可能となります。
ここまで読んでいただければ、冒頭のポール・グラハムの言葉が理解出来るかと思います。
新規事業というものは、大体が赤字です。そのため、PERやROEといった成熟した企業への投資への判断とは全く異なる、将来性というものを見極めねばなりません。
その将来性を判断する指標がユニットエコノミクスなのです。
ユニットエコノミクスが健全な企業であれば、たとえ現在ユーザー獲得のために赤字だったとしても、そのお金は後々回収することが出来ます。
しかし、ユニットエコノミクスがマイナスのサービスだった場合は、そのお金は回収することは不可能だということが見えているわけです。
それは、デフォルトで死んでいるということになりますね。
そのため、新規事業担当者は多額の資金を調達したり投下する前に、まずはユニットエコノミクスを健全な値まで持っていくことが最重要KPIのとなるのです。
最後に
ここまで説明してまいりましたが、LTVやCPAは常に変わり続けるというものであり、「たとえ一度健全化したユニットエコノミクスでも、時間が経てば不健全になってしまう」ということは、経営者もしくは事業責任者は常々、意識においておくということが重要です。
そのため、
・獲得コストについては常に貪欲に新しいチャネルや手法を模索し続ける
・LTVを上げるために、アップセル・クロスセル・販売方法の変更等考え続ける
・運営コスト(原価・外注等)の適正化
を考え続けることが使命となります。
ユニットエコノミクスの健全化は、事業の成長性そのものです。
ぜひ事業開始時期から意識して、攻めと守りを兼ね備えた事業運営を心がけてください。
※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比
※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月