この記事でわかること
EC(electronic commerce)が一般的な言葉となって浸透してきた昨今、巷では新たにCCといった言葉を聞くことが増えました。
CCはConversational Commerce(会話型コマース)の略で、従来のECがECサイトと呼ばれるWebページを経由して商品を購入するのに対して、CCではFacebook MessengerアプリやLINE、そしてチャットボットを通じてコマースを行う点に違いがあります。
この新たな潮流においてチャットボットは不可欠な要素であり、これからのECは「チャットボットを制する者がECを制す」と言っても過言ではないのです。
そして、チャットボットを活用する上で“シナリオ”と呼ばれる、ユーザーの選択によって条件分岐が起こる導線を攻略することこそ、ECの事業成長に欠かせないこと。本稿ではこの潮流を踏まえてチャットボットを導入すべき理由をおさらいしつつ、シナリオ設計について詳しく見ていきます。
関連するテーマについては、以下の記事もあわせてチェックしてみてください。
ECチャットボット活用のすべて|導入・運用・成果最大化ガイド
チャットボット導入でCSコスト15%削減。具体的な事例や導入課題とメリット、注意するべき点とは?
D2C・ECブランドがチャットボットを導入すべき3つの理由とメリット

以前お伝えした「チャットボット最適化による成功事例」でも触れましたが、チャットボットを導入するメリットには、主に以下の3つがあります。
- 業務効率化
- 解約抑止率の向上
- LTVの上昇
以下で、ひとつずつ簡単に解説していきます。
業務効率化
人が行っていた業務をチャットボットに置き換えるだけで、簡単に業務効率化を図ることができる。この点は、チャットボット導入の大きな魅力のひとつです。
以前はお客様の問い合わせをコールセンターで受けていたEC事業者が、チャットボットを導入したことで業務効率化を実現したケースは枚挙にいとまがありません。さらに、単純に業務効率化をしただけではなく、同時にチャットボットを活用することでコスト削減につなげた事例もあります。
以下で紹介している事例では、コールセンターで1コールあたり約500円〜600円かかっていた費用を削減することで、合計15%ものコストカットを実現しています。
<参考記事>
チャットボット導入でCSコスト15%削減。具体的な事例や導入課題とメリット、注意するべき点とは?
解約抑止率の向上
さらにコールセンターに比べてチャットボットでの応対は均一、かつPDCAを回すことで改善し続けることができます。
このチャットボットの性質によって解約抑止率の向上を実現し、チャットボットツールの「ecforce chat」・「ecforce efo」をAPI連携したECプラットフォーム「ecforce」では自動解約抑止率19.6%といった実績も出ています。
LTVの上昇
解約抑止率の向上が実現できるので、当然ながらLTV上昇も見込めます。
LTV=年間購入回数(継続率)× 購入あたり単価 × 解約抑止率
これはLTVを求める計算式ですが、=(イコール)の右に3つの要素があります。この中でも以下の2つは大きなインパクトが出やすく、チャットボットはこの2つのどちらに対しても改善できる可能性を秘めています。
- 解約抑止率を上げる
- 購入あたり単価を上げる
解約抑止については先述した通りですし、チャットボットを活用することでクロスセルやアップセルも可能なため、購入あたり単価を上げることもできます。
つまり、チャットボットを活用して成果を上げることで、LTV上昇に大きく貢献する可能性を秘めているのです。具体的なアプローチ方法は、ぜひ以下の記事を参考にしてみてください。
<参考記事>
ECチャットボット活用のすべて|導入・運用・成果最大化ガイド
ここまでチャットボット導入のメリットをお伝えしましたが、もちろん導入しただけで成果が上がるわけではありません。チャットボット導入後に重要なのは、成果が出るための「シナリオ設計」をすることです。
チャットボット導入の実績:月商540%増を達成
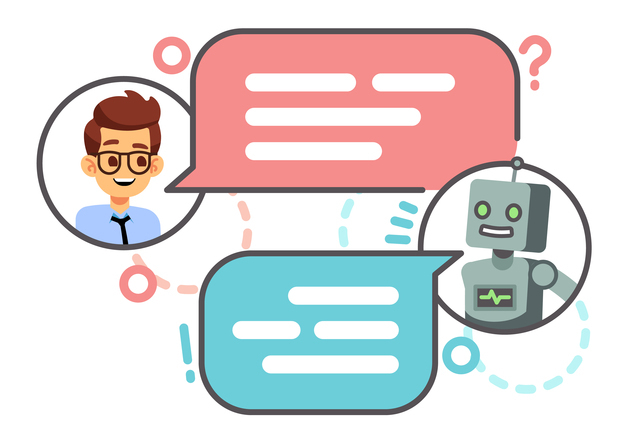
ここでは、シナリオ設計がうまくいった場合にどのような成果を上げられるのか、その点をお伝えします。
この事例では、ECプラットフォーム「ecforce」とチャットボットツール「ecforce chat」をAPI連携。コールセンターで人力で行っていた顧客情報の更新や問い合わせ管理を、全て自動化することに成功しました。さらに取得した顧客情報を活用してシナリオを設計することで、お客様1人1人に合わせたコンテンツを届けることもできるようになったのです。
これらの改善の結果、月商540%増を達成しました。
以前は施策のPDCAを回す際に、現場となるコールセンターへ直接出向き、オペレーターと細かいコミュニケーションをとるといった労力が必要でしたが、ecforce chat導入後は全て自社で完結。改善がスムーズに行われるようになっただけでなく、オペレーターに依存していた解約抑止も、ecforce chatで最適なシナリオを設計することで改善しました。
この事例について、詳しくは以下をご覧ください。
「チャットボット導入でCSコスト15%削減。具体的な事例や導入課題とメリット、注意するべき点とは?」
ところで、成長中のEC・D2Cブランドがこぞって使うECカートの存在をご存じですか?
- 平均年商2億円以上
- CVR380%アップ
- 導入後の成長率265%アップ
これらの数字が気になったら、ぜひ以下をチェックしてください。
ecforce(イーシーフォース)
チャットボットのシナリオ設計に必要なものとは?

ここから早速、シナリオ設計のノウハウをお伝えしたいものの、「このシナリオを作れば百発百中」といったシナリオは残念ながらありません。
その代わり、重要事項をヒアリングすることで、最終的に成果が上がるシナリオを導き出すことは可能です。しかし、一般的にはその“重要事項”が何を指すのかが明らかにされていません。実はここがポイントで、初心者がシナリオを考える上で陥りがちな穴でもあります。
重要事項を理解しないままシナリオ設計を作るのは、道標がないまま森を歩くようなもの。シナリオは各分岐点において、用意すべき最適な選択肢が異なります。そのため、整理・把握をした上でシナリオの全体像をまず理解する必要があるのです。
そこで、本稿ではシナリオを作る上で重要な要素を洗い出したヒアリングシートを共有することで、皆様のシナリオ設計の一助となれればと考えています。
このヒアリングシートがあれば、すくなくともシナリオ設計をする上で「何から手をつければいいかわからない」といったことにはならないで済みます。
シナリオ設計に必要な6個の重要事項
それではここから、ヒアリングシートで洗い出すべきシナリオ設計に必要な6個の重要事項を解説していきます。
基本情報
最初に確認すべきは、基本情報。「当たり前でしょう」と思うかもしれませんが、ここでも大事なポイントがあります。それはショップの基本情報の中でも以下をおさえることです。
- ショップドメイン
- 問い合わせメール先アドレス
- 問い合わせ電話番号
- マイページのURL
- 配送業者
ここで気になるのは、「配送業者」ではないでしょうか。これを確かめる理由は、例えばヤマト運輸か佐川急便で、お客様が追跡する際に問い合わせ先が異なるため。あらかじめ聞いておくことで、シナリオ分岐の際にリンク先を明確にしておく目的があります。
さらに、問い合わせメール先アドレス/ 問い合わせ電話番号 / マイページのURLも同様です。シナリオの分岐点で、ユーザーに対して適切な設問をしたり、正しいリンク先に遷移してもらうために基本情報をおさえます。
基本設定
基本設定の項目で聞くことには、大きな目的があります。会員情報からユーザーを特定して、購入回数・総購入金額などのステータスを得ることで、顧客ごとにシナリオを出し分けるためです。
言い換えるなら、一人ひとりに対して最適なコミュニケーションをとることで“One to Oneマーケティング”を可能にすると言えるでしょう。そのために聞くべき基本的な設定情報をここでは確認します。
解約抑止
LTVを高めるために、主な解約理由をヒアリングすることで、それに沿った抑止オファー・トークをシナリオに組み込んでいきます。
基本的にはコールセンターのコール件数・解約希望者数・実際の解約理由・個数といった定量化されたデータを元に、優先度の高い解約理由を洗い出します。
基本的にはインパクトが大きい解約理由、つまり最多の解約理由から抑止するのが、鉄則です。
解約希望以外の問い合わせ(定期購入者)
つづいて「解約希望以外の問い合わせ」。ここでは、シナリオに組み込むために、チャットボットでも答えられる内容の問い合わせを洗い出します。
たとえば「成分に関する質問」「商品の特長」など、チャットボットで解決できる質問であれば、コールセンターで受けるよりもチャットボットが答えるべきです。コールセンターのコストは受電1件300-500円程度ですが、チャットボットであれば実質0円です。
たとえ問い合わせの数が多くなっても、絞り込まずシナリオに組み込みます。
もちろん定期購入者以外に、以下の情報も確認しましょう。
- 問い合わせ(単品顧客向け)
- 問い合わせ(未購入者向け)
それぞれ重複もありますが、主な問い合わせ内容が異なるため別カテゴリの質問として用意します。
ちなみにecforceの場合、新規顧客獲得に特化したLPでは「ecforce efo」を使い、未購入者が多い検索から流入するようなページやブランドサイトでの接客ツールとして「ecforce chat」を使うことで、目的別にチャットボット・シナリオを使い分けています。
SKU
SKUも確認します。これは複数商材を買っていた場合、どの商品かがわからなくなるためです。ここでは商品名、SKUを洗い出しておくことで該当商品を特定します。
解約・SKU変更NG条件
「解約・SKU変更NG条件」ですが、これは次回配送予定日を確定するために確認します。
定期購入の場合、配送開始してしまうと、キャンセル不可。そのため、例えば「次回配送予定日 7日以内」など、ユーザーに対してポップアップでキャンセル不可の表示を出すことができます。※
※これは「ecforce efo」「ecforce chat」とシステム連携ができるecforceをECカートとして導入している場合の話です。
最後に大事なこと:シナリオは長くしすぎないこと

シナリオ設計をする上で、ここまでお伝えした重要事項を最初に確認しましょう。
その上で、各項目で聞いた内容からユーザーを特定し、ユーザーのニーズを理解できるように分岐を用意。その上で問い合わせに対する回答や、その他の選択肢を提示できるようシナリオを設計していきます。
さらに、最後に大事なことをひとつお伝えします。
最初につくるシナリオは、「長くしすぎないこと」。ユーザーに聞きたいことに要点を絞り、引き算でつくることが大事です。これはシナリオ設計に慣れていないのに、分岐が多いと複雑化して、メンテナンスが大変になってしまうからです。
新商品が出たり、解約理由の割合が変わってきたりといったタイミングで、データを分析しながら徐々に分岐を見直していきましょう。
※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比
※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月











